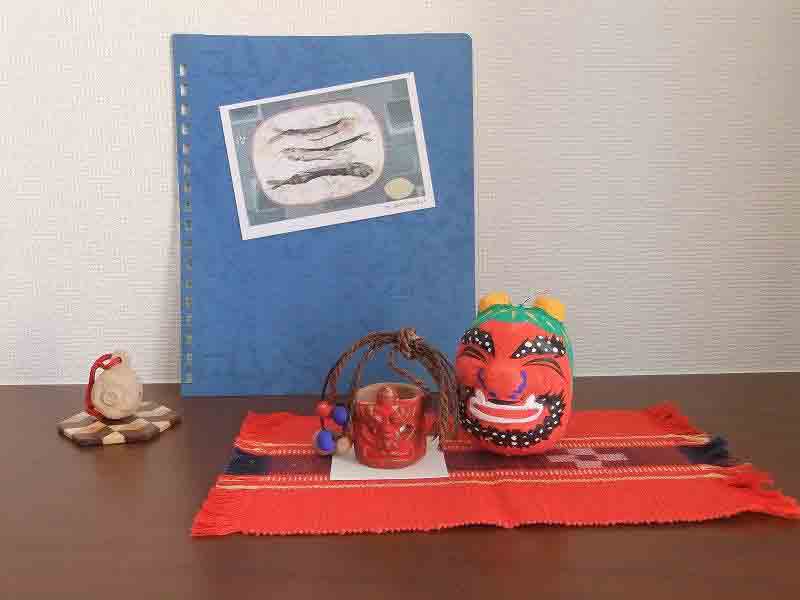�R�[�q�[�u���C�N�R
�@�P�X�X�U�N�̂S���ɓ����̎ł��������{�����Y���ƒ����A�����J��g�̃����f�[�������s�����L�҉�ɂ��āA�Q���P�V���t�̐M�Z�����V����ʂ̃R�����u�Ζʁv�ŐG��Ă��܂��B
�@�g���V�Ԕ�s����T�N����V�N�ȓ��ɑS�ʕԊ҂���A�Ɩ��������B�i�����j���\�̌���ł͉���ɐV������n���o����Ƃ͎��Ȃ��h�@�g���ꂪ�A���̊Ԃɂ������H�������h�Ȕ�s�ꂪ�Ӗ�ÂɌ��݂���邱�ƂɂȂ����B�h�@�����Ɂu�r������v�̎l���n����[�ĂĂ��܂��B
�@�����t���̒n���ʂɂ́A���̂Q�����A��c�s�́u�M�B����m�v�Ƃ����O���[�v���A���悻�P�T�N�̊������o�ĕm���邱�ƂɂȂ����Ƃ����L��������܂����B����ɂ��Ă��낢��Ɗw�K�����Ă����O���[�v�ŁA�m���͉���o�g�̈ɔg�q�j����i�V�T����Ɓj�ł��B
�@�m�̗v���̈�͂Ȃ�Ƃ����Ă����Ԃ����̍���A��������Ґ���ֈ����p�����Ƃ��o���Ȃ��������ƁA�Ƃ̂��Ƃł��B�ɔg����͉���ɖ߂邻���ł����A�u���܂ł����Ȃ������̐S�Ɩڂ��A����Ƃ��Ȃ��̑����̐M�B�ɒ����ł��������v�ƒ��߂�����̉�Ō���ꂽ�����ł��B
�@�~�̉��������čs�����̎����ɂӂƎv���o���̂́A����̐V���_�Ђ̋����ɂ�������{�̔ꊦ���̖B����قǑ傫���͂Ȃ������̂ł����A���̍g���Ԃ͏��߂ĉ����K�ꂽ�Ƃ��Ɍ����ԂƓ������Ǝv���܂����B�����A�����Ԃ�ƑO�̂��Ƃł��B����́A�����������牫��ꊦ���������̂ł͂Ȃ�������B
�@�u�����v����u����v���v���A�X�̌��߂������ȓ_�Ƃ��Ẳ���A���������ԍׁX�Ƃ������B�_�������Ȃ�ΐ��������Ȃ�̂ł��傤�ˁB
�@���̉��̌��c�݂��q����̘A�ځA�u����ʐM�v�Ō���ł̎��Ԃ�m�鎄�́A�u�����̐M�B�v�Ƃ����w�E��^���Ɏ~�߂܂����B���ꂩ��͉�������Ă̂ǂ��ɕ�炵�Ă��鑺�l�ɂ́A�Ӗ�Â̌������ǂ̂悤�Ɍ�����ł��傤���B�������܂߁A���{������I�����ĉ������悤�Ƃ��Ă���̂��A�l���邫�������ɂȂ�ƁA�A�ڂ��Љ�Ă��܂��B
���@��
��������
�@�Q�O�P�U�N�Ɋ؍��̍ϏB���Ɋ؍��C�R��n�����݂���Ă��炸���ƁA�u��n���₪�ē��S�̂̌R�����ɂȂ���̂ł́v�ƃQ�[�g�O�ŃA�s�[���s�������Ă���l�����܂��B
�@����s�ŊJ���ꂽ���@���l����W���ŁA���{�̂X�������ɔ�����l�����Ƃ̘A�т�[�߂����Ɨ����������̐l�A�I���犈���̂��b�����A�Ɠ`����V���̏����ȋL���������܂����B�Q���҂͂Q�O�l�قǂ̏��l���ł������A��Â����̂́u�쒆���X���̉�v�𒆐S�Ƃ����u�s���A�N�V�����쒆���v�ł��B�n���Ȋ������Ȃ��Ă䂫�����ƁA����ւ̊��҂��q�ׂ��̂͋�����\�̓c��������B
�@���c�M���Ə㐙���M������������g�쒆���h�������o�āA���ł͏Z��X�ł��B���̈�p�Ɂu�Ђƃ~���[�W�A���@��쐽�ʼn�فv�Ƃ������p�ق�����A�ْ��͑O�q�̓c��������ł��B����̒�ɔނ��l�Ō��Ă��Ƃ������p�قł����A���݂ł͂m�o�n�@�l���^�c���Ă��܂��B
�@��쐽�͓����l�X�⏗���A�q�ǂ��A�����ĕ��a���e�[�}�Ƃ����ʼn�ƂŁA��i�͎�Ƀ��m�N���ŁA�i������̂��X�g���[�g�Ɋ��������܂��B���̔��p�ق̂Q�K�ɂ́A�i�`�X�E�h�C�c�̎�����������ʼn�Ƃ̃P�[�e�E�R�����B�b�c�̍�i���W������Ă��܂��B�ޏ����܂��n�����l�X�̐����⏗���A��Ǝq�A�����ĕ��a����i�̃e�[�}�ɂ��Ă��܂��B
�@����A���̔��p�قōÂ��ꂽ�A�}�`���A�̔��p���D�҂����̍�i�W�ŁA�ْ��Ɛe�������b������@����̂ł����A�n���Ɏc����j�I�����`����f�ނɂ��Ċْ������Ă����A�����t�̏���������S�������u�k���̑啧�l�v�Ƃ����G�{�������Ă��������܂����B�ǂ̕ł��߂��̎����Z���^�[�̎q�ǂ��������`�����G�ō\������Ă��܂����B
�@�����̌ܓ��E�R��E�u���W�X�g���Ȃǂ̑���Ƃ��^�c������p�ق̑��݂͂ƂĂ��M�d�ł����A��n���Ōl���u�������ė����グ�����p�ق͂���ɋM�d�ł��B�������A������i���ǂ�Ȃɖ��͓I�ł����Ă��K���l�͏��Ȃ��A���ٗ������ł͉^�c��������ł��B�Ȃ�ƌ����Ă��ْ��̂��l�����ǂ����āc�@�ׂ��͓�̎��Ƃ������܂����B����s�ւ��z���̍ۂ͐����������B
���@��
��������
�@�u���̐l�͒��J�Ȑl�ŁA�X�։��l�A�ƌh��ŌĂ�ł����˂��v�Ƃ����b���܂����B����͗X�ǂƂ��������̎d���Ɍg�����ւ̑��h�̔O�����������炾�Ƃ������Ƃł��B���Ă̗X���Ȃ͍��ł͓��{�X�֊�����ЂƂȂ�܂����B
�@��N�A���̗X�֊�����Ђ���c�Ƃ̎�҂��K��A���̔z����Ђ�����������ƔM�S�Ɋ��߂��ē���䂤�p�b�N�̌_������܂����B
�@��̂T�L���E�P�O�L�����𑽂����ɂ͂P�T�`�Q�O���W�ׂ���A���悻�R�����Ԃɂ킽��A���̎d���ł��B�Ŋ��̗X�ǂ���͒��N�Ƃ������A����������Ǝv���鏗�����y�����Ԃŗ��Đςݍ���ōs���܂��B���Ԃ�A�ޏ������̓p�[�g�E���ł��傤�B
�@�Ƃ��낪�A���N�̏t����X�������l�グ����܂����B�����̓ۋC�Ȃ������͊e�_��҂ʂɐV�����\�Ƃ��������̂��͂����̂Ǝv�����݁A�������ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��������߂ɒl�オ������O���A��̑�������N���l�ňē����܂����B
�@�V�[�Y�����́u����v�����������������Ăт�����B�قƂ�ǔ{�z�ł͂Ȃ����Ƃ����l�オ��ł��B�N���l�R����Ȃǂ͂��łɍ�N�l�グ�������̂ł����A�X�֊�����Ђ͊�ƂƂ��Ă̋����̂��߂ɉ��i��}���Ă����̂ł��傤�B
�@�l�グ�̌����͐l����̍����H�@���������A����ł̓p�[�g�̍Œ�������グ�Ƃ����j���[�X�͕����܂���B�A�����J�̃C�������قɂ�錴���̕s���ŗA��������ނ���H�@���������A����ȑO�̘b�ł����B
�@���Y���̉��i��著���̕��������c����ł͎Y���i���w������l�͂Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�@���������ǂ̂悤�Ȍo�ϊw����绂��Ă�����̂��B�����̒l�グ�������N�����o�ϘA���B�����ł́u��������~�X�v�������̂ŐԎ����o�債�܂������A�_�Ƃ���낤�A�Ɠs��𗣂ꂽ��҂������撣���ė������K�͉c�_���A�O���ɏ�����Ƃ���łԂ����̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ł��B
�@���̉Ă̖ҏ����������őς��Ĕނ炪��Ă���̗��h���������ƁB���A�I�c�ɂ̓n�T�ɂ�����ꂽ���F�̂��Ă����ꂢ�ł��B
���@��
��������
�@�R�̊G�`������ƌ����钆���D��������̕`���u��ԎR�v��\���ɗp�����w�J��r���Y�@���ǂ݉_���̂��@�k�y���E��ԍ������с@�P�X�S�X�|�Q�O�P�W�x�i���Õוҁj�Ƃ����{����ɂ��܂����B���Ƃ����낤�ɁA��������ցu���́A���͍D���ł͂���܂���v�ƌ���Ȃ��Ă��ǂ����Ƃ������Ă��܂��A���������Ă��܂��B
�@�Ȃ�����Ȃ��Ƃ������Ă��܂����̂��ƌ����A���̒J��r���Y���́u����̘N�ǁv���āi���āj���܂�������Ȃ̂ł��B
�@����͕����O����̋Ȃ������t��ł����B�q�Ȃ���A������ő�̃����O�h���X�i�ѓ��߁H�j���܂Ƃ����J�삳����ւƏオ��A��i��N�ǂ��܂����B���̎p�Ɛ��ɓ��̒��Ɂ~��t����ł��܂����̂ł��B
�@�I�f���Z�C�A��C�[���A�X�A���邢�͐_�ȂȂǂ̏������͕���Ƃ��Ċy���߂�̂ł����A�w�Z�̎��Ƃł������Ď�ɂ������̂قƂ�ǂ́A���I�ȑ̌������I�ɕ\�������A���������Ȃ�ԗ��X�ɕ\��������i�������A�d�����Ăǂ�����������Ȃ��Ə�ɂ����Ɠ����o���̂��I�`�ł����B
�@�D���ł͂Ȃ��ƌ����Ȃ���A�{�I�ɂ͎��W����������܂��B�R��搉̂������N�̎R������̍�i������܂����A��Ԃ̖������̎��l�̑S�W�A�Љ����^���ʂ�����グ����i�A�q�ǂ���ΏۂƂ����i���X�A�O���̂��̂��܂߂ăy�[�p�[�o�b�N����n�[�h�J�o�[�̂��̂܂ŁA���������ȍ���������ł��܂��B
�@����A�͌��Ή~�`�z�[���Ńs�A�m�̉��t���܂����B�V���p���̋Ȃ̒��Ƀ|�[�����h�̃~�c�L�G���B�b�`�̎�����슴�č�����Ƃ����u�v�������[�h�v������܂����B�ȑO�A���̎��l�̒��ҏ������u�p���E�^�f�E�b�V���v�̉f������Ă����̂ŁA���̉f���i�`�E���C�_�ēj�̉e�����傫�������̂��Ǝv���̂ł����A���̃v�������[�h�͓����ʂ���ɉf�����t�̐F��������悤�ł����B
�@���͂��̖ҏ��̒��A��ނȂ�����̓����a�@�֒ʂ���������������A�Ȃ�Ɓu�哇�����L�O�فv�������܂����B���߂ĖK�₵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�@���́A�D���ł͂���܂���c�@�ł����˂��B
���@��
��������
�@���̑ς��������ҏ��ɂ�������ł��̂߂���Ă����̂ł����A�v�������Ȃ��m�E�[���J�d������������̉Ԃ�݂艺���A�R�O���قǂ̃q�I�E�M���Q�₠�ǂ��Ȃ�����i�ȉԂ��炩���Ă���̂��A�������Ȃ�܂����B
�@�m�E�[���J�d���͑҂��ƂP�R�N�A�q�I�E�M�͂R�N�ł��B
�@���́A�A������Ă�̂͋��ł��B�g��t�̂������h�ƌĂ��K��̔��̐l����A�W���X�~�������̂��菉�߂ɁA���͂̃o�����ŋ��߂��K�N�A����ꂽ�V�N�������A�߂��̉ԉ�����Ŏ�ɓ��ꂽ�����ƁA���ׂČ͂炵�Ă��܂����Ƃ����u��r�v�̎�����ł��B
�@�y�ɐA��������Ǝ��R����ĂĂ���邾�낤�ƁA�]���̐܂Ƀm�E�[���J�d���̓p�[�S���̒��̋߂��ɐA���t���A�q�I�E�M�̎�͂��������ɂ玪���Ė��߂܂����B
�@���̔N�A�m�E�[���J�d���͂Ђ��Ђ��Ɩ������������̂́A�ƂĂ��ׂ��ĕn��ł����B�t����������o��Ό��������\���ɏo����̂ɁA����ς�_���Ȃ̂��ȁA�Ƒ�����������߂̋C���B����ɁA�q�I�E�M�Ɨ������̏o��C�z���炠��܂���ł����B
�@�m�E�[���J�d���͂����P�O�N�ȏ���O�ɁA�v�̎��Ƃ���@�����Ă������̂ł��B���A���ɖڈ�̖_�𗧂ĂĒ�ɒu�����̂ł����A���x�������@�Ŋ����āA�A���������Ƃ��ɂ́A���͂��������̂́A�n�㕔�͂قƂ�ǂ���܂���ł����B
�@�q�I�E�M�́A�O��̃S���t�ꐮ���Ŏ�������q�I�E�M���c�����Ɓu���R������v���������Ĉ�Ă銈�����n�߁A���̐^���Ȏ�i�k�o�^�}�j���������������̂ł��B��������ɂ��������J���~�����̂ŁA��͗�����Ē蒅�ł��Ȃ��������̂Ǝv���Ă��܂����B
�@����ł��Q�N�ڂɂ́A�m�E�[���J�d���͔�������ėt���L���܂����B�ł��A�Ԃ��炩���܂���B�q�I�E�M�͂ق�̂Q���������t���o���A���ꂼ���̉Ԃ��炩���܂����B�����ĂR�N�ځB�ǂ���炵������Ƒ�n�ɍ��t�����̂ł��傤�B
�@���A�ǁA���Ԃ̎R���A�s���N�̐���A�������A��h�A�j�A�܂��܂��������̂��ꂩ�炪�y���݂ł��B
���@��
��������
�@�W���r�[�W���r�[�A�O�`���O�`���`���B
���ւ̊O�Ńc�o���̖��������܂����B�p�ɂɔ�ь����p��ڂɂ��Ă͂��܂������A���ɑ����̏ꏊ�����߂��̂�������܂���B
�@�c�o���̗���Ƃ͉��N���ǂ��ȂǂƁA�N�������o�����̂ł��傤�B�������ȁc��������Ăق����Ȃ��̂�����ǁB
�@�c�o���͐l�̏o����̑����ꏊ�ɑ�������K�������邻���ł��B�܂��ɁA���փh�A�̏�B�����͑D��V��ɂȂ��Ă��镔���ŁA�J��������ʂ��͗ǂ��ƍD�����ł��B
�@�O�������Č��グ�Ă݂�ƁA�l�����Ă��|����Ȃ��c�o���̂��ƁA�ǂɐ����ɂƂ܂��Ă����Ƃ���������Ă��܂��B�ǂ��������̂��Ƙr�g�݂����Ă����̂ł����A�����ނ��𔗂�C���ɕ������̂��A��ы���܂����B�ǂ������A����ŋS�k�̂悤��ⴂ������Ēǂ����ɍς݂܂����B
�@�߂낤�Ƃ���Ƒ����ƂɁu�����v������̂ł��B�Ђ�`�A�ցB�c�o���̂�����̕��ւP�O�Z���`�������������āA������������Ƃ��ē����܂���B�ւ͎���ɗ����Ă��������ȓy�̉��ׂ����Ȃǂ���A�������n�߂邱�ƂɋC�Â��Ă����悤�ł��B
�@���쑺�̏d�S�y���̓y�͉^�Ԃ̂ɏd�����ł��傤�ɁA�c�o���͉ʊ��ɂ��d���ɂ��������悤�ł��B�Q���Ԃقnjo�ƁA�ǂɂ͓_�X�ƓD�̉h������Ă��܂����B
�@���\�N���O�̂��Ƃł����A���ڂɐ��A���o����Ƃ������A�����M�[���o�����܂����B����ȗ��A���ɂƂ��Ē��͖]�����Ŋy���ނ��́A���Ɋ���ė��Ăق����Ȃ��Ώۂł��B�C�̓łł������A�ǂɕt�����D�̉����菜���A����т��Ēʂ���ځB�D�ꕔ���ւ̏o������֎~���܂����B
�@���X���A���x�͐��ʏ��̏o������̏�ɑ������n�߂Ă��܂����B�����߂ɂ��������菜���܂����B���ꂩ�疈���A�l���̕ǂ��`�F�b�N���Ă���̂ł����A�����̓h�A���J���ė������Ƃ����T���_���̂��������[���R�ɂ��܂�Ȃ��Ďւ��c�B�����A�₾���I�@�����畗���ł͉��N���ǂ��ƌ����Ă��˂��B
�@���������āA�ނ��܂��A�_���ׂ����̂Ƃ��ăc�o���̑����`�F�b�N���Ă���̂�����B
���@��
��������
�@������ɒ�Z���Ă���A�n�����̐M�Z�����V����ǂ�ł��܂��B
�@��o���Z���w��R�̐V���l�@�ː��I�X�x�i��g�V���j�ɂ́A���̐V���Ђ͖����U�N�ɑn������Ă���A�B�X�����M���u�M���v���͂��ė��j��z���Ă����Ƃ���܂��B
�@���ɎR�H���R�Ƃ�����M�́u�А��̂ق��ɐM�B�ɖ����ꂽ�j���̔��@�͓I�ɍs���A���킹�ĈɒB�����L�A���R�F��Y�A�剖�����Y�Ȃǔ����I�ȓƓ��̎j��ɂ���Đ����ȏ�̘A�ڂ𑱂��A�����ɐ��Ȏh����^�����v�����ł��B���R�ɋL�ҍ���h���Ԃ�ꂽ�e���̋L�҂����ꂼ��ɗ͂̂��������T�K�L�����A���Ƃ��Α����I���L�҂ɂ��s�o�~���ꒃ�t�́A�ꒃ���u�ʑ����l����m�ԁA�����ƕ��ԑ��݂Ɉ����グ������������ʂ������v�Ƃ���܂����B
�@�����͂�����V���ɂ́A��ʉ��i�A�����Ɂg�����̈��h�Ƃ����P�W�V�������݂̈͂�����܂��B�o�l�A�y�삠���q����̑I�o��Ƃ��̉���ł��B������A���グ��ꂽ��𗝉��ł��Ȃ��܂܉����ǂ݁A�傫�ȏՌ����܂����B�f��̓O���X�̒��œ����Ă��܂����������߂Ă��܂��B��������A�s��ő���ꂽ�V�x���A�ł̔ߎS�Ȑ�����ǂݎ���Ă����̂ł��B���̎��A�����גj����̊G�A�V�x���A�V���[�Y���v���o���܂����B�قƂ�Ǎ��ŕ`���ꂽ��ʁA���J���ꂽ���A�S��Ԃ̃V���G�b�g�c�B
�@���ǂ����тɉ���҂̋��{�̐[���ɋ�������܂��B�ÓT���w�E�_�b�E���Ƃ��Ȃ��Ȃǂ͗m�̓������킸�A�܂����E�A�����͂��ߋC�ہA�V�́A�C�m�A��w�A����A���j�A�������X�ɒʂ��A���̓��ɂӂ��킵����������o���̂���ςȎd���Ǝv���̂ɁA�����Ȕo�l���疳���i���̓��̐l�͂����m���j�̓��l�܂ŁA�g�����h���ׂ������o���āA���Ȃ������ł�����Ɨ��t����������������Ă��܂��B
�@�S�O�ł�����V���̂������P�W�V�����ł���A�ː��I�X����M�ɏ��ق����n���V���Ђ̖ʖږ��@�H�@�ǂ݂ł̂���V���ł��B
���@��
��������
�@�G������ʂɉԂ��炩���Ă��܂��B�N���[�o�[�E�q���I�h���R�\�E�E�z�g�P�m�U�E�C�k�t�O���E�X�~���A����Ȃ���ӂꂽ�G���ł��Q���ƂȂ�Ɩ{���ɔ������A����������Ă��܂��̂��Ƃ��ߑ�������Ŏd���ɂ�����܂����B����Ɠ_�X�ƍL�����čs�������s���R�ȓ������ڂɓ���܂����B
�@����[�A�ǂ������́B�e�w�̒܂قǂ̑傫���̉J�^�̏W�c�����X�Ƃ��ĉ��o�����݂Ă����̂ł��B���̐��A�P�W�A�P�X�A�����ƁH
�@�u����ȂɍD������ɒ���ōs���Ă��܂�����A���ƂA��Ȃ��Ȃ�ł��傤�Ɂv�Ə����������Ȃ���A���������Ĕނ�͍��A����Ȃɏ����ȑ̂ő厩�R��ɖ��������������n�߂��̂��ƁA���̒ɂ��Ƃł����B
�@�J�^�͑̂̐F�����݂ɕς��܂��B���̊����x�̍����Z�ɂ͌��t������܂���B�͂�}��R�₵���D�̒�����͔��D�F�̊^�A�R���c��̎}�̉��ɂ����͍̂����܂���͗l������A����̊Ԃɂ͂��̐ƉZ��̊^�B�C�k�t�O���̐��F�̉Ԃނ炩��o�Ă����^�[�R�C�X�u���[�̊^�ɂ͂т����肳�����܂����B
�@�����Ĕނ�͎��ɉ����ɂł����܂��B�������Ƃ��~�߂�N���b�v�̌��ԂłR���������p���Œ��v�ٍl�̊^�B�����A��ɂȂ�Ƌ��Ԃʼn̂��Ă����̂́A�A���~�T�b�V�Ɗ����̌��Ԃʼn^�悭���Ă��܂����B���V���b�N�����̂́A���ւ̒��Ƃ̊ԂŃh�A�ɉ����Ԃ��ꂽ�܂܃J���J���Ɋ������Ă����^�ł��B�ڋʂ̔��������̊^�́A�Q�~���قǂ̌����̎�����B�v���X�`�b�N���̃L�[�z���_�[�݂����ŁA���A�w�����ς̂߂��܁x�Ƃ������b���v���o���Ă��܂��܂����B
�@�b���ɂ��V���l�ĂĎO�����l���A������������\�����炢�A�撣��ʂ����łɂ͐���Đl�ԂɂȂ��Ə��l�ɋ�����ꂽ�J�b�p�B���ȂтĊ����āA�Ƃ��Ƃ���̂��ڂ݂ɖڋʂ����ƂȂ��ăj�J�j�J�Ə��Ă����̂ł��B
�@���́g�����J�^�h�̂��܂�ɂ������ȑ��`�Ɏ藣���������A�ʐ^���B���Ă��疄�߂܂����B�ʐ^�́A�ق�ˁA�Ɛl�Ɍ�����x�Ɉ�����ƌ����A�s�폜�t�Ƒ�����܂����B
���@��
��������
�@�R�̉�̎Ⴂ���ԂɗU���āA�^���s�����������邽�߂ɒn���̑哴�E�ѓ�R�ɍs�����ƂɂȂ�܂����B�̂�т�ƍs���Ė߂��ĂP���Ԕ����炢�A�z�̂��邤���ɖ߂��ˁA�Ɣޏ��̎d�����I����������߂��ɎԂŏE���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B�O�̂��߁A�c��̗l�q�����ɍs���ƁA��̏������o�R���ɂ͗��������̗t�⏬�}���ނ��o���ƂȂ��Ă��ĕ����ɂ������ł��B�u�X�m�[�V���[�́H�ł��ˁA���̓c�{���ɂ��܂��v�ƃ��[���ŏ��𑗂��Ă����܂����B
�@�Ƃ���ŁA�ޏ����Ԃ��~�߂��͕̂ʂ̓o�R���B�ܑ����ꂽ�o�R��������t�߂ɂ͗��܂����Ⴊ����A���ݍ��ނƕG�܂Ŗ��܂��Ă��܂��܂��B�{�X�b�A�Y�{�b�A����?�@�ƃ|�[�������ł�낯�y����ł����̂ł����A�T�d�h�̔ޏ�����u�댯�ł��A����́B�_���ł��v�Ɛ�R�̃��b�Z�����ǂ��͑��֎~�œP�ޖ��߁B�����āu�������Ԃ�����悤�ł����甒�n�ɃR�[�q�[�����݂ɍs���܂��H�v
�@�Ƃ�����ŁA�R�����͐����̃R�e�[�W�������Ɖ��A���Ǝ��Ƃ��������Ȃ�����`���Ă݂Ē��ԏ�ɖ߂�Ƃ����R�O���قǂ̒��~�j�E�n�C�L���O�ɉ����A�������ȋi���X�ł������̃R�[�q�[���u�����͎��ɔC���Ă��������v�Ƃ��y���ɂȂ�������ł��B
�@�����ɂȂ��āA���������������t����̒�������̃R�[�X���������������������Ȃ��ƁA������̓o�R���������Ȃ������厸��ɋC�Â��A�\����Ȃ����c�O���B
�@���āA���̂܂������ł��B��Ő�̉�����o�Ă����͂�}��S�~�����Ă���ƗL�������̃`���C������܂����B���̍L��ۂ���̂��m�点�Łu�����A���A�������甐�y�ɂ����ăN�}�̖ڌ������܂����v�Ƃ������Ƃł��B���낻��Ƃ͎v���Ă����̂ł����A�N�}�̏o�����G�ߓ����ł��B���̓��A�c�{�����ʔ�������Ɣޏ��������A��ĎR�ɓ���A�����ŃN�}�ɏo����Ă�����A�ƂĂ������鑫����m�ۂ��邱�Ƃ͏o���Ȃ������ł��傤�B�ޏ��́u�R�v����u�R�[�q�[�v�ւ̔��f�͐����ŁA���ӂ�������ł��B
���@��
��������
�@�f��قʼnf��������̂́A���w���̍��ɂ��ׂ̉Ƒ��ɗU���čs�����u�Ɣn�V��v���ŏ��ŁA���̎��̋L���͍��Z�Q�N���̎��Ɋw�Z����o�������f��ӏ܉�́u�x���E�n�[�v�ł��B�Љ�l�ɂȂ��Ă�����f��قɂ͑����^�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��A��g�z�[����ǔ��z�[���Ȃǂŏ�f���ꂽ���̂��������������炢�B
�@�ߓ��A�V���̉f����Љ�闓�Łw�v���n�̃��[�c�@���g�x�����グ���Ă��܂����B���R�A�B�e�͂��̃v���n�i�`�F�R���a���j�ōs���Ă��܂��B
�@���́A�ƌ������̂ɂ͖����āA�v���n�͊C�O��l���̗B�ꖳ��̒n�Ȃ̂ł��B���̕��i���Ăіڂ̑O�̑傫�ȃX�N���[���Ō�����A�s���˂A�Ƒ������܂����B
�@�f��́u�h���E�W���o���j�v�̃I�y���ƃ��[�c�@���g�̐g�ɍ~�肩�������������d�˂������̕���ŁA�����悻�̌����͂��܂��B��������v���n�̊X�A����A�I�y�����������ƁA����͑P�����̕\�Q�����������݉��X�̃A�[�P�[�h�����ǂ��čs���܂����B
�@���ǂ��A����Ȃ̗L��H�Ƃ��̊O�ςɏ��Ȃ���ʏՌ����o�����f��ق͒z�P�Q�O�N���o�������ŁA���{�ň�ԌÂ��f��ق������ł��B���Ȃ͕ǂɂ`�`�m�Ǝ菑���̎���\�������̂P�P�U�ȁB�g�[�͂ނ��o���̃X�`�[���̊ǂŁA��f���ł����X�J���J���J���Ɖ��̂��邵����́B�ϋq�Ƃ����V�j�A�����Ώێ҂��V�C�W�l�̂݁B��������đI�т�����i�i�u������Ɛ�����v�����j����f����Ƃ����o�c�҂̎p�����_�Ԍ�������ł��B
�@�Ƃ���ŁA�v���o�̒n�v���n��ڂ̓�����Ɋy���߂����ƌ����ƁA�����ł��A�����͂k�d�c�̊X�����������킯�ł͂Ȃ��A�������f���o�����̂͂�����̊X�B��̍~��~�Ƃ���Ȃ�Ƃ��Â��Ă͂�����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂���B����ł��{�a�⌀��̒��ŌJ��L�����鉼�ʕ������I�y���̃V�[���͖��邭�A�����̓����̋��X�ɂ܂Ŏ{���ꂽ�������������A�v���n�s���t�B���n�[���j�[�nj��y�c�̉��t���A����͂���͂����Ղ�Ɗy���܂��Ă��炢�܂����B
���@��
��������

�@�����܂ȂԂ͒���s�o�g�̃V���K�[�\���O���C�^�[�ŁA�����������܂ł��炵�A���v�̂т�����Ƃ����p���c���b�N�A�����}�t���[���R�[�g�̏ォ�炴������Ɗ|���c�@���Â��߂̔ނ����ƌ�������悢�̂��A�|�\�E���ł͂��邨�Z����ł��B
�@����Ȏ�҂���N�̂P�Q���ɑ�Q�R�a�E�����W���[�i���X�g����܂̏���܂���܂����̂ł��B
�@�ނ͂Q�O�O�O�N�ɏ����N�ƁA�؍����o�̃v���f���[�X�Ńf�r���[���ĉ��y���������Ă��邻���ł����A�O�V�N�ɂ��c������̖��B�ł̐푈�̌����܂Ƃ߂���L����ɂ����b�c�u��z�v�������[�X���܂����B����ɂP�T�N����͂P�N���������Ē��쌧���V�V�s�����������āA���悻�X�O�l����풆�E���̑̌��k���Ƃ銈���𑱂��܂����B�����Ƃ�́w�ǂ��������V�V�̋L���x�Ƃ�������̖{�ƂȂ�A�M�Z�����V���Ђ���o�ł���Ď�܂̉^�тƂȂ����̂ł��B
�@�P�Q���W���̐M���ɂ͑S�ʍL�����o����A���ʂ̉E��ɂ́u�����^��ƁE�c�̗l����̂��x���ɂ�蒷�쌧���S���Z�ɂ��̖{������v�|�݂̈͂�����܂����B�������ɂ͋��^��Ƃƒc�̂̍L�����ڂ����Ă��āA����Ð�����A���{��R�c�z�e���A�g���������b�������@���Ȃ́A����O�����h�V�l�}�Y���X�A���쓌���Z������Ƃ����̂�����͔̂ނ̏o�g�Z�ł��傤���B���̑傫�ȃX�y�[�X���g���Č����E���g���́u�X���͐��E�̕�@�q�ǂ������ɐ푈�̂Ȃ����E���v�Ɠ��{�����@��X����Y�����L�����d�C�����ԗp�}���[�d��̔̔��㗝�X�i���j��ԂƂQ�����Ă��܂��B
�@����A���ꖳ���Ŏ��O�\��s�v�Ƃ����o�ŋL�O��M���̖{�Ђł���܂����B���M�̂����������ގ��̃G�s�\�[�h�A�푈�̌�����ނ��Ď��g�����������ƂȂǂ����̂��Ƃ������e�ł��B�����ɍs�����������̂ł����u���ԏꂪ�Ȃ��̂Ō�����ʋ@�ւŁv�Ƃ����Y���������c�@���̑����痘�p�ł���o�X���d�Ԃ�����܂���B�M���̌������̃p�`���R������̒��ԏ��_���ׂ����������ȁB
���@��
��������
�@�P�����̐��ɓ����邱�̑��̓y�ɓK�����哤�͐��R�哤�Ƃ����A���ł͏���앨�ƂȂ��Ă��܂��B���N�͒��J�̂������S�߂ȏo���ƂȂ�܂����B���̑哤�A���H�͑�L�삾�����̂ł��B�����Ŏ��݂��̂����ݖ��Â���B
�@�P�����ɂ���݉�����ɗa���čy��ۂ�t���Ă����������R�T�L���̑哤���R�����Ɏ茳�ɖ߂��Ă��܂����B�͂��P�T�ԂقǑO����X�O�g�p�̒M�i�v���X�`�b�N���j�ɂR�W�g�̐��ƂP�O�s�̉����Ȃ��܂��Ă����܂��B�����֍��܂݂�ł�������p��ς����哤���d���݂܂����B���߂̂P�O���Ԃ͂P�������ɓF�����đS�̂�������悤�ɂ��܂��B�G�ۑ�ŁA���͓��i��̎�@���Ŏo����i�k����H�j���Ԃ�A�������B���𒅂Ă��������ƁB��Ƃ͎_�f�Ƃ̐ڐG��}����悤�Ɂu�����Ƃ₩�v�Ɏ����^�т܂��B�P�T�`�Q�O��A�F�ŐÂ��ɏ㉺����������́A���ɋ�C��G�ꂳ���Ȃ����߂Ƀr�j�[���V�[�g�œ��̖ʂ��т���ƕ����A�M�ɂ̓e�B���p�j�̂悤�ȉ����o�邭�炢�ɂт����ƃr�j�[���V�[�g�œ��W��A���̏�ɒM�̊W�����A���̏�ɂق���Ȃǂ�h���ړI�ŕz�����Ԃ��܂����B
�@�T���܂ł͓���������Ȃ��A�J�̓�����Ȃ��A�O�C���̉e�����₷���A�Ƃ�����₱���������t���̏ꏊ�ɐݒu�B�ď�͉��x�����߂Ĕ��y�𑣂����߂ɒ��˂��������r�j�[���n�E�X�ɒu�������A�������x���S�O�x���炢�ɂȂ�悤�ɂ��܂��B�U�O���܂ł͂T���ɂP�x�A���̌�͍Ăь��̏ꏊ�ɖ߂��ĂV���ɂP�x�A�������킹�܂��B���x�������Ƃ���݂̌������S�`�T�Z���`�قǂɂȂ�܂��B���̌��݂����������̌��ߎ�Ƃ��B
�@���ɂ��̂P�P���ɍi��̍�Ƃɂ��ǂ蒅���܂����B�����b�����Ē��������̓��̐�y�̂���̒�Ɋ������炦�A�����i���ďo�ė������ݖ����W�Q�x���炢�ɂ������߂ĎE�ۂ����܂��B�����c���Ă����ĉ�ʂ��Ȃ��M�d�ȁu�����ڂ�v�����܂����B
�@���́u���`�ށA����c�v�Ɗ��S����o���オ��ł����B�߂Ă����A�߂Ă����I
�@�ł��A�S�O�g���o��������āA�ǂ����悤�B
���@��
��������
�@�����ɉ������d�˂Ď�ɓ��ꂽ�ō��̎R���a�ɁA�̒r���甒�n��ƁA���@�؎R�ւƏo�����܂����B
�@���[�v�E�G�C�𗘗p���āA�W���P�W�T�O���قǂ̍������U�邱�Ƃ̂ł���̒r���R�����o�R�̏o���_�ł��B�R�����͊��ɏ������܂����}���鎞���ōg�t�͍�������Ƃ���A�����̂��̓����܂��Ƃ����o�R�҂�ό��q�łɂ�����Ă��܂����B
�@���̓��͔��n��r�Ɉꔑ���A�����A�����ɉו���u���ċ�g�ŏ��@�؎R�ɁB��͓V�̐���A������ΎR�ƍg�t���B�e����Ƃ����o���ȊO�̖ړI�������āA���s�̓�l�͈��t�J�������Q�B���鎄�͕v�̂�������̃R���p�N�g�J�����ł��B
�@����Ȃɗǂ��V�C������̂��Ǝv���قǂ̐��V�B�R�U�O�x�̑�W�]�Ɉ��|����A��ʑ̂�I�ԂƂ��\�}���l����Ȃ�Ă��悻���p�Ƃ��������R�̑�ՐU�镑���ɁA���ՂɃV���b�^�[������ł����B
�@���R�̂��ƂȂ���A�ʐ^�̒m���̂Ȃ����̓J�����������Ă��邢�����̋@�\�̂Ȃ��́g�I�[�g�h�ɂ��C���ł��B�Ƃ����킯�ŁA�o���オ�������i�́u���`��A�ǂ����Ⴄ�Ȃ��c�v�B�����̂��̏�ʂɂ͋y�т܂���B����ł��A����ɍs���Ȃ���Ύ�ɓ�����Ȃ��Ƃ��������ɑ������M�d�ȃV���b�g�ł��B������Ƌ����āA�������悭�B�ꂽ�ʐ^�Ɂu�{���͂����������Ƃ�_�����͂��ł����v�ƌ������Y�������ăJ�����ɏڂ����l�w���[���𑗂�ƁA���������Ƃɂ��낢��ƋM�d�ȃm�E�n�E��ԐM�ł��������������܂����B
�@�[���⒩���̃I�����W�F�͂���������A��ʂɍL������i�ɂ̓����|�C���g���A�傫������T�C�Y�͏��������āA���ʓI�ȋt���́c���X�A�ʐM����Ȃ�ʃ��[�������ł��B
�@�f�W�J���͍l�����ɎB��Ɣᔻ�����̂��������ł����A���S�҂����s��������邽�߂ɂ͕֗��ł��B���낢��Ǝ����Ă݂ĉ������Ƃ̃G�ꃋ�Ɋ������Ȃ��āA���������Ă݂悤�ƂV�O�̎�K���B������������ȁB
���@��
��������
�@���T�O�N���}���悤�Ƃ��Ă������A���a�ȂT�O�N�̗��j�B�����J�E���g�_�E������C�^�����܂��Ă��܂����B�����I���̊ԁA�푈�Ƃ����l�ނ̂����Ƃ��p���ׂ��s�ׂ����Ȃ��Ől�X�͕�炷���Ƃ��o�����̂��A�Ƃ����v�������݂��߂āA�������̒����燀�퇁�͖����Ȃ�̂��낤�Ǝv�������̂ł����B
�@�����A�n�l��̘N�nj��w���̎q�����̉āx�����낢��ȏꏊ�ʼn������Ă��܂����B���̐푈���q�ǂ������ɉ��������点���̂��A�ς�ҕ����҂Ɂu������x�Ƃ���Ȏv���́I�v�ƐS�ɍ��݂��镑��ł��B
�@���́A�R���ŕ��Ɋ��������Ă���w�Z�Ȃ���̂��ꂳ���������ق̕���ɏ��A�w���̎q�����̉āx��N�ǂ������Ƃ�����܂����B��{����Ɏ���ė��K���n�߂Ă݂�ƁA�Ƃɂ����܁A�܂ő呛���B�m��Ȃ������S���̋ꂵ�݂̍ו��܂ł������Ă���̂ł��B
�@�������A�n�l��n���ɌJ��L���Ă������Ƃ̖{�ӂɂ͍�������߂āA�[���v������������ł��B���̕���́A�S����l�X���ꂵ�݂Ȃ���ۂݍ��܂�Ă������푈���A���֍ۍs���Ȃ��̂��Ɗm�F���邽�߂̋@��ł͂���܂���ł����B�푈�̂Ȃ��T�O�N�𐔂��鐅�ʉ��ŁA�܂���Ɠ��������グ�����������h�̕��X�Ȃ�Ȃ��͂��������Ă̔��ւ̑i���������̂ł��傤�B
�@�����ɃC���N�푈���N����A���q�����Q�����鎖�ԂƂȂ�܂����B���x�͔���I�ԉ����l�̉�w�s�[�X���[�f�B���O�x�̓W�J���n�߂܂����B���X����錻�n�̏Ƀ��A���^�C���ŃX�|�b�g���C�g�Ă��\���ŁA��n�̍���m�炳��܂����B
�@����̗͂͐V���̌��o���̑傫�Ȋ�����e���r�ŗ����L���X�^�[�����̎��Ɋ���I�ɑ��肩�˂Ȃ��`�����Ƃ͈Ⴂ�A�������҂͂�����������Ŏ��̎�����~�߁A���̌�Ɏ����Ƃ̑Θb���o�āu�����Ȃ̂��v�Ǝ��Ȍ���𑣂��܂��B���̎v���͐[����邬�Ȃ����̂ɂȂ邱�Ƃ�̌����܂����B
�@���A�c�O�Ȃ��ƂɁA������ς�l�͂Ȃ�Ƃ����Ȃ��ł��ˁB
���@��
��������
�@�v�X�Ɏo���番�����������͂��܂����B�u�������育���������Ă��܂��܂����v�ƈ��܂�莆�́A�c�R�T�a�E���P�R�T�a�̘a���ɏ����ꂽ����^�̊G�莆�ł��B�����Ȕ��f�����͖��_�ɉE���ɕ`����A���قǂɂ��Q��������������}������܂��B���̊G�̌��Ԃ͂т�����ƓƓ��̕����Ŗ��߂��A���悻���N�Ԃ̔ޏ��̗l�q���`�����Ă��܂����B
�@�����Ԃ̘r�̒ɂ݂���ł̒ŊԔw���j�A���������ƁA�����̑��������V�X�������Ă��邱�ƁA�V���͓s�c�I�������˒[��c�̖Z�����������������āi�H�j�v�ƌƂ̖@����\�肵�Ă��邱�ƁA���߂ĉ���ɍs�����ƁA���ς�炸���ŋ������s���H������y����ł���A�Ƃ������Ƃł����B
�@���āA���̖@���ł����A���V������Ă��A���o���グ���A�������ցi�o�v�w�Ǝ��j�v�w�A���j�̉łƑ��Ɩ{�l�łV�l�j�ʼn�H�����Ďv���o�b������Ƃ����`���������ł��B
�@����A��]���O�Y����́u�M�̖����҂̋F��v�ɂ��ĐG�ꂽ������ǂ̂ł����A�M�̖������́A���́u�F��v�Ƃ��������o���܂���B�F��̑���Ƃ����͓̂��R�_���ł�����A�M�������Ȃ�����̍s�ׂ͐��藧���Ȃ��̂ł��B�`�[�������|�[�Y�͂������Đ_���Ɏ���̂悤�ɂ��v���C���i�݂܂���B
�@�Ă͐푈�Ɋւ��ԗ�Ղ��s���܂����A���N�N���鎩�R�ЊQ��傫�Ȏ��̌���ɂ͌��ԑ䂪�������A�����ŋF��l�X�̎p���e���r�ɂ���Ċe�ƒ�ɑ����Ă��܂��B�p�ɂɓ͂��F��̉f���ɁA�F��Ȃ����͂�����߂����悤�ȋC�����ɂ����Ȃ��Ėڂ����炵�܂��B�ł��A�ȂB���c�B
�@���̍�����ł��傤�A�����ɂ��F��̏ꂪ�ݒ肳��A�j���[�X�ƂȂ�A���f�����悤�ɂȂ����̂́B���������`���|�\���v�킹��悤�ɁA���������Ŏ���s�������e���r�͔O����ɏЉ�Ă���܂��B���{���ŋF�鍑���̃N���[�Y�A�b�v�c�B
�@���ꂪ�A�ǂ����A���ƌ����̂��A���߂̃g�[���Łu���������{�v�ƌĂ�鐺���摜�̉����畷�����ė���悤�ŁB
���@��
��������
�@���̈���ɏ���ɐ�����u�ق������v�ł����A���߂�l������̂ňꉞ�C�������Ĉ�ĂĂ��܂��B���̎��͗v��Ȃ��̂ł����A�O����^�����ȃ��[�X��̎p�ɕϐg�����܂��B������z�ɓ���A���ɂk�d�c�̏����ȓ��������ƁA�Ȃ��Ȃ��f�G�ȏ��蕨�ɂȂ�܂��B�������A���̂͐��Ƃł��B
�@�y�g�����~�܂��ăv�b�v�[�ƃN���N�V��������܂����B���������̔��̂x����ł��B���ɂ��鎞�Ԃ̎O���̈�͒ʂ肩�������l��߂܂��Ă͂�����ׂ�Ƃ�����m�B�u����ɂ��́B���ׂ��������ă}�X�N���͂����Ȃ��́v�ƈ��A�B�u�����������ׂ��Ђ��l�����イ�̂́A����͐H�ׂȂ�����̓_���ƌ����l����������A�ق�A��f���j���j�N�������Ȃ�Č����ĂȂ��Łc�v�ƒ��b�ւ̃C���g�����n�܂�܂����B
�@���Ƃł̓j���j�N��H�ׂ�K���͂���܂���ł����̂Łu��X�A�H�ׂĂ��܂���B�֎��R��ɂł͂Ȃ�����ǁA�j���j�N�̓��������ւ������������Ƃ͂���܂���ł�����v�Ƃ����Ɓu���̂c�m�`�����ׂɎア�̎�������Ă���v�ƁB
�@�j���j�N�͐H�ׂ܂��A���̎q���̂悤�Ȃ�����傤�͖��N�Ђ��܂��B��N�͎�ɓ��ꂻ�т�Ăx����̔��̂�����傤�������Ă��������܂����B�����ł����������������ɂł����̂ŁA����Ɂu�t�|��������{�܁v�Ƃ����萻�̃��x����\��A�F�l�ɂ�����������������ł��B���N�͐����ő��X�ɒ����B�Q�ӂ͉��Ђ��A�����ĂR���ڂɊÐ|�ɒЂ����ނƂ��������ł�����A���̂R���Ԃ͉Ƃ��イ��������傤�L���Ȃ�܂��B��͑��������������J�����܂܂ɂ��āA�������ɕ߂�Ƃ��������B���̕����̊������ƁB�֎��̂����ŕ��ׂ͒������̂ł��B
�@���Ȃ݂Ƀ��x���́u�t�|��������{�܁v�̂t�|�����́u���`�ށv�Ɠǂ݂܂��B�x����̉�������Ă�����{�~�c�o�`�̖I���̃r���ɂ́u���掩�^�{�܁v�Ƃ������x�����\���Ă���܂��B
���@��
��������
�@�P�T�Ԃ��o�Ă��b�Ɣw��������G����ގ��i�I�j����ɂ́A��͂�芙�ł͂Ȃ����͂�����������@�̂ق����͂��ǂ�̂͌��킸�����ȁB�O��̎���p�̑�����@���Ă��炢�܂����B
�@�Ƃ��낪�A���̂Q�T�C�N���łЂ��������ăG���W����������Ƃ����A����u�����v�̃X�^�[�^�[���䂷��͎̂���̋Z�ŁA�����������Ђ��������グ�Ă͎��s���A�@�B���g�����Ԃɂ��閘�ɂR�`�S�O����v���܂����B���������āA���������ɂȂ��āA�������肵�āA�u��������ȕ��A�g�����̂��I�v�Ɣ������ɂȂ�Ȃ���Ȃ��g���C�������A����ƃG���W�����������āc�B
�@�Ԃ͂ǂ̃��[�J�[���L�[���X�G���g���[�Ƃ������@�ɂȂ�A�{�^�������������ŃG���W���͂�����܂��B���̕��@���Ȃ��_�Ƌ@��ɍ̗p���Ȃ��̂��Ǝv���̂ł��B�_�Ɛl���̍��������A�����Ƃ��Ă����藧�ł͂Ȃ��ł����B
�@�ߓ��A�L�[���U�b�N�ɓ��ꂽ���Ƃ�Y�ꂽ�܂Ԃ̃g�����N���[���ɒu���A�ړI�n�̒��ԏ�ŁA����A����Ȃɗ��ꂽ�ꏊ�ɒu���Ă������A�ł��G���W���͂�����˂Ƌ����܂����B�����ŁA����҂Ɠd���g�̘b�����Ȃ���R�ɓo��������ł��B����d���g�Ɏ��͂܂�Ă��鎄�����ɉ��̉e�����Ȃ��킯�͂Ȃ��ƁB�I�E���^�����̎����Œm�炳�ꂽ�u�|�A�v�Ƃ������t���v���o���܂����B
�@�k���Ȃǂł͂������N���O����w�Z�Ŏq�ǂ��������g�p����p�\�R���͕������w�肵�Ă���ɗL���Ƃ���A���d���̎��͂P�T�O���̓y�n�͓d�͉�Ђ���������Ĉ�ʂ̎g�p�ɒ��Ȃ��A�Ɠd�̂h�g�������ɓI�ɂȂ��Ă���ȂǁA���낢��Ƒ���Ă��邻���ł��B
�@���{�ł����ł͓d���g�A�����M�[�Ƃ�����Ǐ������F�߂��A��w�E�ł͖���N������Ă���Ƃ��B���R�j������Đi�߂��郊�j�A�V�����B���R�����ł͂Ȃ����N�̖ʂŁA���ꂪ�d���Ƃ����斱�����喇�͂����ď���q���A���Ƃ��|���b�ł��B
���@��
��������
�@���̕ւ肪�͂�����A������ł͔~���炫�n�߂܂����B�A���̓V�C�\��Ŋe�n�̉Ԃ̗l�q�����������Ɠ`�����A���悢��V���炫�Ƃ�����������ŁA������̍��͂�����Q���c��݂����܂����B
�@�����������鏬��R�x��ł́A��N�Ɉ��������A�l�����̌����炵��ƂȂ��Ă���R�̏�̒�ō��N�����̓������s�������Ȃ��Ƃ�������A�ύ��̉����Â��܂����B
�@�����͓���ɂ������̊ۑ���l�����Ȃ�ׂĈ֎q�Ƃ��A���̒����Ƀv���X�`�b�N�̃R���e�i�̏�ɓK���Ȕ��ڂ����e�[�u��������ďo���オ��ł��B�[������V�C�������Ȃ�Ƃ����̂ɁA���Ԃ̓������̋������ƁB�R�̏�䂦������Ə��X�����݂������͍̂Ђ��ŁA����̈ʒu�ւƊۑ���]�����Ă͊��������A�P���܂��P���ƒE���n���ł����B
�@���͓V������炢���Ƃ����傫�ȃ^���N�̐����g���Ė��A��ʂ��̂�������v�ƁA�����͎R��A���C���h�ł��B���̃^���N�Ɂu�V�y���v�Ɩn�������z���f�����܂����B
�@���Ԍ����u�s���̂������̓��v�ł��̂ō��̓s���͊Ԃɍ��킸�A���䂩�����f���̂��Ȃ����̌i�F����˂���ƁA�Ԃ��c�q�ō���莭�����ƎR�ɖڂ������Ă��܂��͎̂R��̈����N�Z�ł��B�X�������z�����F�̉_�̒��ɑo����̎��������x������ɂ��A�܂�Łg�R�̂��Ȃ��̋��K�����ށh�̕��͋C�ɂ݂�ȂŌ��Ƃ�Ă���܂����B
�@���́A�₦���r�[����傫�ȃs�b�`���[�̃R�b�N���Ђ˂��ăW���b�L�ɒ����Ƃ����A���ꂪ�ڋʂŁA���Ƃ̓W���M�X�J���ł��B�z�����݁A�ቺ�ɒ���̓��肪�ڗ����ɂȂ�ƋC���͉����蕗���o�Ă��܂����B�ǂ����V�C�͉����ɂ��������̂ł��傤���B���x�̓_���}�X�g�[�u�Őd��R�₵�Ēg�����܂��B
�@��������������������ȕ��ƌ������J�̈�邪������ƁA�����͉��₩�ȓ��������~�肻�����A�������ɂ͍��͂R���炫�B���������̃s���N�Ő��܂�̂��A�����b�ǂ݂ł��B
���@��
��������
�@�R�ɓo����͂����m�̎��Ǝv���܂����A�O�_�x���Ƃ�����o��̊�{�Z�p������܂��B
�@����́A�葫�̂S�_������Ƃ炦����ԂŁA���̍s���ɂ͂��̂����̂P�_���������A��ɂR�̓_�Ɏ�|����⑫�|�������������Ɗm�ۂ����Ĉړ�����A�Ƃ������@�ł��B�������Ȃ��R�_������ŏo����O�p�`�̓����ɏd�S��u���悤�ɂ����Ԑ��������Ƃ����肷��`�A�Ƃ����킯�ł��B
�@�ŋ߁A�т̒�����L�c�c�L�̃h���~���O�̉�����������悤�ɂȂ�܂����B�t�ł��ˁB�ɐB���̃T�C���������ł��B����Ăđo�ዾ��ڂɓ��Ă��̂ł����A�����邱�Ƃ͏o���܂���ł����B���ɐ����ɂƂ܂�A�����������ׂŊ������L�c�c�L�B���̚{��ł��t���錃���������A�����ɓo�铮�����A����g��Ȃ��ނ炪�Q�{�̑������łǂ����Ďx���邱�Ƃ��o����̂��낤�ƁA�����ԕs�v�c�Ɏv���Ă��܂����B�m���ɑ��̒܂̓J�V���Ɗ���͂�ł���̂ł��傤���A���͐K�������͂ȂR�_�ڂƂ��đԐ����m�ۂ��Ă��邱�Ƃ�}�ӂŒm��܂����B
�@����A��ɉ��肽�z�z�W�����y�̏�̉������ꐶ�����ɂ���ł��܂����B�����Ă������̎�ł��傤���B���̂����A�̂�����Ƃ��点�āA������Ƌ�����グ�Ă���ł͂Ȃ��ł����B���̒��̋�͓��ʂɐ��A�����ʂ�悤�Ȍ�������Ă��܂����B�l�Ԃ��ق�ڂ�ƌ��グ�Ă�������ł������A�z�z�W���͉����v���Č��グ�Ă����̂ł��傤�B���̎��ɋC�Â����̂ł��B�z�z�W���͗����̗��̐�[��y�̏�ɓ˂��悤�ɂ��ė����Ă����̂ł��B����Ԃ邽�߂̃o�����X���A���̐���g���Ď���Ă���̂ł��B�]�ʐ�̏��A�z������p�ɁA�u�ւ��`�A���Ɨ��łS�_�m�ہI�v�ƁA���S�����炨���������B�����ɂ͌��ցA�����A�g�C���Ɏ萠���ݒu����Ă��܂��B�]�ׂΐQ������Ƌ�������ĕs���s���u�V�l��v�����ꂽ�̂ł����A���͎g������Ė��ӎ��ɎO�_�x���ōs���B���Ȃ��Ă��܂��B
���@��
��������
�@�ȑO����e���r�����Ȃ������������Ă��܂��B����ł��V���̃e���r���͌J��I��������ԂōŌ�ɖڂ�ʂ��܂��B
�@�s���_�t�Ƃ������������P���ɂQ�g����������A�C���^�r���[�������Ҕԑg�ƂȂ��đ����Ă����肷��̂ɋ����Ȃ���A�V�����h���}�s�J���e�b�g�t���ڂ������܂����B
�@�����Q�A�R�N���O�ɂȂ�ł��傤���A�_�Ƃ��B�����悤�ȕ����V�I�w���҂ɂ���Ċ�Ղ��N�����������ڂ�y�c�̉f�悪����A�܂����b�`���킯�̂킩��Ȃ����q�����̃u���X�o���h�́A����ɍŋ߂ł͎v�킹�Ԃ�ȁu�I�P�V�l�v�Ƃ����f����ł��܂����B�Â��͎��ƒ��̃g�����{�[���t�҂̖�������u�I�[�P�X�g���ߏ����v���n�߁A�C�M���X�̒Y�z�J���҂�����������y�c�́u�u���X�v�ȂǁA�n�����܂����A�������g�߂Ȑ����҂��������y��ʂ��Ċ�]��������Ƃ��������̉f��͂���������܂����B
�@���܁A�܂��Ȃ��H�Ǝv���̂ł��B�ǂ����s�J���e�b�g�t�́A���ꂼ�ꉹ�y�ɂ͎����킵���Ȃ��ړI���������S�l�����݂���M���Ȃ��܂ܑg�A�R�l�܂ł��f�l�Ƃ������y�l�d�t�c�̘b�̂悤�ł��B
�@���y�ɂ͏d�v�ȗv�f�Ƃ��ăe���|������܂��B�f�l�̃A���T���u���͂Ƃɂ����Ȃ̑S�̑���������܂ł͑�ςł����A�₪�Ċy���ɋL���ꂽ�e���|�ɓ�����đ��������悤�ɂȂ�܂��B�����Ă��̌��ʁA���������̂Ƃ̏o�������̂ł�����A���t�͊�т̂ق��̉����̂ł�����܂���B
�@���y�̉c�݂�������͂��m�F���邱�ƂɂȂ���ꂻ���Ɏ����҂͋�������̂ł��傤���B�������e���r������ǁA�ŁA�傰���̂悤�ł����l�Ԃ̗��j�ɉ��y���K�v�������Ƃ����Ӗ������߂čl����q���g�ɂȂ�܂����B
�@���y�̉c�݂�������͂��m�F���邱�ƂɂȂ���ꂻ���Ɏ����҂͋�������̂ł��傤���B�������e���r������ǁA�ŁA�傰���̂悤�ł����l�Ԃ̗��j�ɉ��y���K�v�������Ƃ����Ӗ������߂čl����q���g�ɂȂ�܂����B
�@����̂ɌR�C�̃e���|�̈Ӗ�������̂ɜɑR�Ƃ��A����̂ɁA�ꂵ������s���ēǂ߂Ȃ��ł���w�������e���̃o�C�I���j�X�g�x�Ƃ����{������܂��B�A�E�V���r�b�c�̎��e���ŁA���Ԃ�J���֑���o���y���ȃ}�[�`�����t�����o�C�˃����j�X�g�̉�z�^�ł��B
���@��
��������
�@���N�̌����͂��邤�b��}�����ĂP�N�̎��Ԃ��N���P�b���A�������������ł��B���̂P�b�a�ł��鎞�Ԃ������Ȃ����Ɗ�Ԃׂ����A���̎��Ԃ������Ȃ����Ɣ߂��ނׂ����A�N���ɂ���Ȑ��E����v�킴��܂���ł����B
�@�N�ł��A���ɁA�N�������܂鎞�ɂ͂��̂P�N���u���Ȃ��v�߂��������Ǝv���܂��B�����ɂ͂��̂悤�ȋC�������������ɂ����߂��Ă��邱�Ƃ͂����m�̒ʂ�ł��B
�@�P�������̐����ɂ��鏬�쑺�͋ߗׂ̑��X�ƂƂ��ɐ��R�n��ƌĂ�A���̐��Y�ɓK���Ă��邻���ł��B���ɑ哤�́u���R�哤�v�ƌ����A���������č���Ă��܂��B
�@�����ł����Ɛ��̍����i���哤�j���A���ߗ����ɉ����Ă��܂��B�����̓}���ɓ����A�}���ɕ�点��悤�ɂƂ����v�������߂��Ă��܂��B������̕����Ɂu�܂߂������v�Ƃ������t������܂��B����́u�܂߂ł���v�Ƃ����Ӗ��ł����A�N�̐��ɂ́u���N���܂߂������Ȃ��v�Ƃ��������A��������܂����B���N�����Ȃ��߂����ĂˁA�Ƃ������Ƃł��B
�@�Ƃ���ł��̐��N�A���̎��n�����ɉJ�̓��������悤�ɂȂ�܂����B������Ƃ��������߂��Ĕ��ɍs���Ă݂�A���͒��ɐH���Ė��c�Ȏp�ɂȂ��Ă��܂��B����ȓ��ł����n�E�E�������ĐH�ׂ�����̂�I�ʂ��܂��B�������َq���̂ӂ��Ɏ���Ă͓��Ƃɂ�߂��������Ȃ���_���}������菜���܂��B���ʓI�Ɏ̂Ă铤�̑������ƁB�哤�A�����A�����A���C���Q���A�ԓ��ƁA���ꂼ��̑S�̗ʂ͏��Ȃ��Ă��������ӖO����قǑ����܂����B
�@��N�͑��̐���ɂ�薳���Ŕz�z���ꂽ�i�J�Z���i���Ƃ����哤�������܂����B���̑哤�ō��N�͎��Ɛ��̂��ݖ�����낤�Ǝv���Ă��܂��B����������|����Ȃ��������Ԃ�v�����ƂƂȂ邱�Ƃ��\�z����A���͐������������Ŋ��ɂЂ��ł�����̂ł����B
�@�Ƃ����ꏉ����A�܂߂������s���������̂ł��B
���@��
��������
�@�u�X�͂����ɍs���Ă��܂����v�ƌ����ƁA�q�}�����ł����ƕ����ꂻ���ł��ˁB���͒��쌧�A������g�g���̎��̂悤�ȑo���Ƃ��猩���鎭�������x�Ō��������X�͂ł��B
�@�����ԁA���{�ɂ͕X�͂͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂������A�x�R�����R�J���f�����h�����قɂ�闧�R�A��̋ߔN�̕X�͊m�F�������s���A�Q�O�P�Q�N�ɂ͕x�R���̗��R�Ō�O��X�́A���x�ł͎O�m���X�͂Ə����X�͂������̕X�͂Ƃ��Ċm�F����܂����B
�@����Ɉ��N�́A���쌧�̎��������x�̃J�N�l����k�߂閜�N��̉��Ɍ������R�R���ȏ�Œ����͂V�O�O���ɋy�ԕX�̂����鎖��������܂����B�X�͂̓����ł���N���o�X���A�����������ރ��[�����Ƃ�����������܂��B�ł��̐S�ȗ����ϑ��͐ϐ���ђʂ��ĕX�̂ɒB���錊�������A�����ɂT���قǂ̃|�[���ߍ��݁A�����x�̂f�o�r�œ����̗L���𑪒�B�����ʂ͔N�ԂQ�D�T���Ɠ˂��~�߂܂����B���̑��A�ϔN�̒������ʂ��Ƃ炵���킹�āA���N�A���̕X�̑w�͌����̕X�͂ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�̂ł��B
�@���n�ܗ��X�L�[��̃S���h���ŃA���v�X���ɏ��A�ϐ�T�p�̓���n���̓��E��m�����E�j�m�����ցA����ɏ������R�܂łQ���ԕ����܂����B�����Ŏ��������x�̖k�����̖k�ǂ�������Ɍ������ނ��Ă���̂�ڂ̑O�Ɍ��Ȃ���u�`���܂����B�ڂ�����������ꂽ�̂́A�J�N�l����k�i�X�́j�w�p�Ǎ��c�̔ѓc������B���R�J���f�����h�����ق̊w�|�ے��ł��B
�@�u�J�N�l���̑��ɂ��X�͂����肻�����Ǝv����ꏊ�����̋߂��ɂ���̂ł����A�X�|���T�[��������Ȃ��̂Łc�v�ƁA����Ȃ�X�͔����̊��҂ƒ����̍�����|�c���B
�@�ѓc����A���{������u�R�w���������v�ɏ悹���Ȃ��ł��������ˁB���̋M�d�Ŋy�����̌��́A�k�A���v�X�R�x�K�C�h�����Ấy���������x�J�N�l���X�͒T�K�c�A�[�z�ɉ��債�ē������̂ł��B
���@��
��������
�@�������珬�쑺�Y�̐V�Ă�H�ׂĂ��܂��B�Ղ�Ղ肵�Ă��Ă��ŁA���������I�Ƃ����Ă��A�������Ă���킯�ł͂���܂���B���͂ق�̐����A���ƒE���̎���������`�������āA���Ă��Q�b�g���Ă��܂��B
�@���N�͈��𐂂ꂽ����Ɏ��X�Ƒ䕗������Ă��āA�{���ɂ悭�J���~��܂����B���������������̂Ɋ�����`�����X�������܂���B�҂��āA�҂��āA�ǂ����Q���قǐ��V�Ƃ����V�C�\��B�P���ڂ͈���������Q���ڂɈ�C�Ɋ���ƁA�c��ڂ̃I�[�i�[����d�b������܂����B
�@�����l�͎������v�w�̂ق��ɁA�W�O���Ă��邲�ߏ��̏����A�V�O�Α㔼�̃I�[�i�[�̋`��B����҂����ł��B�Ƃɂ������̂T�l�ŁA�x�ފԂ��ɂ���œ������鐡�O�܂Ŋ撣���Ċ���I���܂����B��������̓n�T�ɂ����Ď��R���������܂��B
�@�Ƃ��낪��������܂��e�͂Ȃ��J�B��͊����ǂ��납�G�ꂻ�ڂ��Ă��܂��B����ł����v�A���v�ƌ����������đ҂��A�܂��Q���قǂ̋M�d�Ȑ���\��B���x�͒E���ł��B
�@�c��ڂɎc��J�X�ɑ����Ƃ���ł������A�n�T�ɂ�������̂��ɒE���@���ړ������A��ۂ悭�E�������Ă䂫�܂����B���͎����I�ɑ܂ɓ���܂����A��t�ɂȂ�Ɛ��C����Ȃ��悤�ɓc��ڂɐςm���̃x�b�h�Ɂu�悢����v�Ɛl�͂Œu���܂��B�P�܂̏d���͖�R�O�`�R�S�L���B�^���Ԃł��������ɒu���ꂽ�܂��W�߂Čy�g���ɍڂ��A�I��i�[�̎���ɉ^��őq�ɂɎ��e���܂��B
�@�u�Ȃ�Ƃ��I����ėǂ������ˁv�ƁA�˂��炤���ɂ͓������Ă��܂����B
�@���ꂩ��܂������ƉJ�̔��������܂����B
�@�H�Ղ肪�I������Ƃ����̂ɁA�܂��n�T�ɂ�����ꂽ�܂܂̈��ڂɂ��܂��B
�@���N�A���{�S���ő䕗�ɂ��_�Y���̔�Q�͔��[�ł͂���܂���ł����B�H�����������l�����ɂs�o�o��y���}�����{�B�_�Ƃ𑼍��Ɉˑ����ėǂ��Ƃ���������B�Ԃƌ����������Ƃ������ƁH�@�ŁA�N���K���ɂȂ�́H
���@��
��������
�@�t�F�C�X�u�b�N�ɎQ�����Ă����A�A�����ꔭ�ŏI������ǂȁ`�A�ƌ����܂����B�t�F�C�X�u�b�N�ȂǁA�����ɂ͑S���K�v���Ȃ��̂ł����A���萔�����������Ă���̂ł���ΐ\����Ȃ�����ƁA�v�����čŐ�[�̐��E�֏�荞�����Ƃ����̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A�{�l�m�F�̂��߂Ɍg�ѓd�b�̔ԍ����K�v���Ƃ����ł͂���܂��B�g�ѓd�b�������Ă��Ȃ����Ƃ��ẮA���Ƃ���������Ȃ��Ŏ��ɐi�݂����̂ł����A�ǂ����Ă��_���Ȃ̂ł��B
�@�l�b�g������Ɠ����悤�Ȗ��Ŏ�������Ă���l�����\�����̂ł����A����ƌ�����������ɍs��������܂���B��`�߂��A�ƃp�\�R������܂����B�������Ȃ��ŕ���ƂQ�`�R����������`�Ղ͂Ȃ��Ȃ���̂Ǝv���Ă����̂ł����A�����p�\�R���𗧂Ă�Ɓu�A�J�E���g�̔F�����Ċ��������Ă��������v�Ƃ����t�F�C�X�u�b�N����̃��[��������܂����B�������A�������Ă��Ȃ��͂��Ȃ̂ɂR�l�̐l����u���F�����Ɂc�v�Ƃ������[���������Ă����̂ł��B
�@�����A�Ō�̍ԁI�ƁA�o�b���X�L���[�́u�������m�v�m������ɂr�n�r�B���������g���@�\���g����������������Ă��������܂����B�ł��A�s���Ȃ�ł���ˁA�Ƃ����p�\�R�������ꂱ��Ƒ��삷��̂��āB�����ŎႢ�l�̉����čēx�g���C���Ă݂��̂ł����c�����ɗ��Ă��ꂽ�ޏ����킭�u���̍����K�l�̃T�C�g�A�J�������Ȃ��ł��v�B
�@���ǁA�t�F�C�X�u�b�N�͎g��Ȃ����Ƃɂ��āA����l�̂��߂ɂ��萔���������肤���Ƃɂ��܂����B
�@����g�ѓd�b�i���͂�������Ȃ��H�j�������Ȃ��l�́u�����v�Ɏ�����Ȃ��Ƃ������Ƃ�������܂����B������g�K���p�S�X�h�ł��B
�@���̂��������̍Œ��ɖ�c�m�S����̖{��ǂ�ł����̂ł����A��������߂肷��悤�ȃJ�k�[�ł̐쉺��̌������āA�ƂĂ����͓I�ł�����ǂ˂��B
�i���@�j
��������

�@�Ȗ،��ߐ{���ɂ��鏬���ȉƂ��A�T�N�O�̓����{��k�ЂŎ��̂��N���������d�̕�����P���q�͔��d��������o���ꂽ���˔\�̃z�b�g�X�|�b�g�ƂȂ������Ƃ́A�ȑO�ɂ����̃R�����ŐG��܂����B������ł͊e���Ƀ��j�^�����O�|�X�g��ݒu���Ė��T�Z�V�E���̐��ʂ����\���A�������I���ĂQ�N���o���܂����B
�@���ʂ͖��N�ꌅ���炢�������葱���Ă��܂������A���̂Ƃ���0.09�}�C�N���V�[�x���g�ɂ܂ʼn��������̂ŁA������Ɨl�q�����ɏo�����Ă��܂����B������ƁA�ƌ����Ă���M�z�����։z�����k�֓��������k���Ə��p���ł̓����ł��B�֗��ƌ����Ε֗��ɂȂ������̂ł����c�B
�@���āA���n�ł͎Ԃܑ̕�����Ă��镔���Ɏ~�߂āA�p�����Ă��ǂ��d�����ɒ��ւ��Ē��C�𗚂��A�}�X�N�ƃS����܂ƁA�ꉞ�̐g�x�x�����āA�܂��ܑ͕����H�Ő��ʂ̌v���ł��B0.149�B
�@�������猚���܂łP�O���قǂ̖��ܑ��̓����A�ʂ镔�������G��������͂炢�Ȃ���ړ����ēr���̑��̏�Ōv���0.391�B���j�^�����O�|�X�g�̒l�Ƃ͈Ⴄ���낤�Ƃ͗\�z���Ă��܂������A����قǂƂ́I
�@����ɒl�͒�̓쑤��0.427�������A������0.412�B���ւ̓����͏�������̊��҂������đ������̂ł���0.204�B����ŏZ�ނ̂́c���Ƃ��G�߂̈ꎞ�I�ȑ؍݂ł��A���p���邱�Ƃ͍l�����܂���B
�@�����͖��p�ƈ����Ԃ��܂������A��N�ސE��ɟ������Ƃ�V�z���Ē�Z���ꂽ�Q���̂���͉J�˂��߂��Ē����s�݂̗l�q�ł������A���̓��A�ȗ��A���_�𑱂��Ă���ꂽ����̋��ɂɂ͋��̎p�͂���܂���ł����B�ʑ��n�Ɩ��ł��ĊJ������ĂS�O�N�A���ۂɉƂ����Ă��l�͏��Ȃ��A���ӂ͏��߂��瓊�@�ړ��ŕ��u���ꂽ�܂܂ł������A���H����n���قƂ�Nj����ʂĂ��X�Ƃ��������̍r�ݗl�ŁA�P���͔p�Ԏ̂ď�ƂȂ��Ă��܂����B
�@�������ƂȂ����������̒����̎��Ԃ��v���ƁA���W����C�����ł��B
�i���@�j
��������
�@�����ł͍���̑O�Ŏ�҂������{�[�h���������āu�푈�͂��Ȃ��I�v�Ɩ��T�A�s�������Ă���悤�ł����A�m�g�j�̃j���[�X�ł͂قƂ�Ǔ`����Ă��܂���B���̏����ȑ��ł͂Ȃ�����̂��ƁA���̒��ō������N�����Ă���̂��������ɂ����̂ł��B
�@�Ƃ���ŁA���̏��쑺�ł�������u�X�^���f�B���O�v�Ƃ����ӎv�\��������l����������̂ł��B���O����̓]���ҁA�܂�h�^�[���ƌ����鏗�����A�菑���̃{�[�h�������ĂP�O���Ԃ��������܂��傤�A�Ɖ��l���ɌĂт����āA�u���̉w�v�̒��ԏ�̌����ɉ��������ɗ����Ă��܂��B�ޏ��͊���Ȃ��_�Ƃ̍��ԂɎ菑���̃`���V�����A�����ŃR�s�[�����A�^�����Ă��ꂻ���Ȑl�Ɏ�n���Ȃ���ꏏ�ɗ����܂��Ɛ��������Ă��܂����B
p>�@�X�^���f�B���O�Ƃ����͖̂����ł������������ė����̂Ǝv������ł������A�Ȃ�ƂȂ��o�c�̈������������ĎQ�������Ă���܂���ł����B����A�u�����Ȃ��Ă������A���l�������āA�߂������c�v�Ƃ����ޏ��̌��t���Ă��܂��A����ς莄�������Ȃ���Ǝv���܂����B�����������ł��˂�ƁA�Ƃ����X�^�C���ɂ͒�R������A�����o���Ă������H�Ɗm���߂āA�{�[�h�ɕ����̑i���Ƃ����`�ɑウ�āA�t���[�g�ʼn��y�̑i���Ƃ����`�ɂ����Ă��炢�܂����B�����ăX�^���f�B���O�Ƀf�����[�B
�@����͕đ哝�̃I�o�}����̍L���K��A�Ƃ����j���[�X�ɍ��킹�āu�q���V�}�̂��鍑�Łv�Ƃ����Ȃ�I�т܂����B�����Ďc�莞�Ԃ̂��߂ɂ����P�ȁA�u���̉́v�B����ꔒ�n�����Ԍ����R�P�����s�������Ԃɂ������P�O���Ԃ̃X�^���f�B���O���ڂɗ��܂����ł��傤���B����ł����傤�Ǖ����Ēʂ肩���������̑��B��̃^�N�V�[��Ђ̉^�]�肳�A���f���������ė����Ă����l�ɘb�������ĉ������܂����B
�@�����́u���j�̎c�������̂́v��\�肵�Ă��܂��B�n�C�h����[�c�@���g�Ƃ͈Ⴄ���̂悤�Ȋy���A��ɓ����̂�������B
�i���@�j
��������
�@�́X�A����Ƃ���Ɂc�@����������ɒN�����������̂Ȃ��́A�S�n�ǂ����̂ł����B���́u�܂��{���Ȃ��v�̎s���x�q����̌��I�Ȍ����o���Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�����Ԃ�ƑO�ɂȂ�܂����A���u�[�����N�����܂����B
�@�e���r�▟��͕ʂƂ��āA�u���b�v�͂������̏o�ŎЂ���{���ɗǂ��G�{�ƂȂ��āA���ɂ�������o�ł���܂����B���͎q��Ă̎����ɁA�q�ǂ��ƈꏏ�ɂ��̖��b�̊G�{�Ɍ����������̂ł��B
�@���b�Ƃ����Ε������E�Ęb�E�o�łƂ������傫�Ȏd�������ꂽ���J�݂�q���v�������т܂����A�������w�̕���Ŋ����֓������̈�A�̖��b�����̂������A�؉�����̓��{���\����I�y���ƂȂ����u�[�߁v�Ȃǂ��v�������т܂��B
�@���̍�Ƃ������A���X�ƖS���Ȃ��Ă��܂��܂����B��N�̂Q���ɏ��J�݂�q������]��ŋC�Â��A���̕���Ō�ɑ����Ċ��Ă����Ƃ���i������܂���ł����B
�@�Ƃ���ŁA���́g�ǂ�K�ɍT���āh�����n�얯�b�E�̋����A���邢�͏d���Ƃ����A�u���̖��O��O��Ƃ���n�얯�b�ƑΛ����āA�����Ƃ��Ώ𗝂ɂ������铙�g��́v�G�l���M�b�V���Ȗ��O����`���Ă�����ƁA���˂Ƃ��E�����炳��������m�ł��傤���B
�@���͏���s�ɂ��Z�܂��ċ���ψ�������܂������A���̌㋷�R�s�ɓ]������܂����B���͌������ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B���N�a�����N���ɂ́u��N�A���J�݂�q�搶�������Ă���A�n�얯�b�E�������Ԃ�₵���Ȃ�܂����B���ʂƂ��Ď����A���J�[�}���ƂȂ��Ă��܂��܂������A����ɖ߂�܂�����A�n�얯�b�̏[���ɗ͂�s�����A���̐E�ӂ�S���������ƍl���Ă���܂��v�Ƃ���܂����B���̃A�m�J�[�}���A���˂Ƃ�����͍�N���̒�������A���̂R���ɖS���Ȃ��܂����B
�@�u�_�b�v�Ƃ������_�Łu���̘b�v����������Ƃ����́A�d���̓��������Ă��܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł�
�i���@�j
��������
�@�R���͂��낢��Ȃ��Ƃ��ς��G�߂ł��B�G�ؗтł́A���F�̃J�T�J�T�̊��̎v��ʂƂ���ŁA�L�т�^�C�~���O��҂��Ă��鏬���ȐV�����肪�ڂɂ��悤�ɂȂ�܂����B�l�Ԃ̎Љ�ł͈�ʓI�ɔN�x���ŁA������l���̌�オ����܂��B�����̔ԑg�����傫�Ȗ����܂݂Ȃ���A�e�Ђő����݂����낦�ď������Ȃ���Ă���悤�ł��B
�@�ߓ��A�w�m��̐V������c���̌��҈ꗗ�����Ă����v���u���A���䂾�B���䂪���邼�A�~�����Ȃ���v�Ƒ����ł���܂����B
�@�Ƃ��Ƃ��w�m��ɂ܂ŏ�荞��Łg���������f������w�҂̐��E�h�Ɉ��{�H����~�����Ƃ����̂ł��傤���B�������Ƀ��[���ɑ����������ŁA������q�g���[���ǂ��̂����Ȃ̂��ƋC���̈������ƁB
�@�u�����������o���낤�H�ӂ��`��A���̌o�ς��v�A�u�w�m��̐l�Ƃ����̂͋��{������̂ł���B�܂����ނɓ��[����l������Ƃ͎v���Ȃ�����ǁB�ȂA�ǎ��������ŐV�����ɂ��킹�����v�A�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ����v
�@���n���i����I�j�Ƃ������t������悤�ɁA�����̌����ȊO�̂��Ƃ͒m��K�v���Ȃ��Ǝv���Ă���w�Ґ搶������̂ł��傤���B
�@�u�ԍ����ԈႦ�Ȃ��悤�ɂˁv�u���̌��҂̙l�߂ɂȂ�����܂�������ȁv�ȂǂƏ�k�����킵�Ȃ���A�����{�[���y���Œ��J�Ɂ~��������܂����B
�@�Ƃ��낪�A���̌�Łu���I�v�Ɨ������t�����̂ł��B�Y������I����ȊO�̐l�Ɉ�������ꍇ�͖����ł��A�Ə�����Ă���ł͂Ȃ��ł����B���䎁�̔��f�͋�B��w���o���l�݂̂ɗ^����ꂽ�����������̂ł��B
�@�C���t�̏o�Ԃ��Ǝv������u�����A���̂܂܂ŁB�ӎv�\�����B���̌��҂Ł~�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��l�Ȑl���Ȃ�����������A�����ł��Ƃɂ�������ɂ́~�v�ƈꌏ�����B
�@�쎟�n�����ł͂���܂����A���ʂ�m�肽���Ǝv���܂��B
�i���@�j
��������
�@�Ⴊ�~��~�݁A�����̋C���������Ȃ�Ɖ����Ɏc���Ă����Ⴊ�����܂������ƂƂ��ɗ����āA�Ƃ̎���͐�Ŋ_�����ł����悤�ɂȂ�܂��B��ɂȂ���ᩁX�ƌ��������킽��ƋC���͂ƂĂ��Ⴍ�Ȃ�A��_���ɑj�܂�ċ�C�������Ȃ��̂��A�����͕ǂɑ�������t���Ă��܂��B
�@�u���̑����炵�����́A���E���������Ƃ��Ȃ��́v�Ƃ����̎�������܂����A�������H�̎��Ɏ����̐Ȃ��瓌�̐��E������̂ɂ͏����ȑ�����������ł��B���̑��ɔ���������₵�����̂��c�B���H�@����Ăăh�A���J���đ��̉���_�������̂ł������̌����ƂȂ���̂͂���܂���B�ł��A�������̂͌��ꂽ��������肵�Ă��܂��B�悭����ƕǂɂł����q�ɂ̉e�����z�̈ʒu���ؖ����邩�̂悤�Ɉړ����Ȃ���A���̓������������̑���n�����Ă���̂ł��B�������琅���C����������Ă��܂����B����͎��c�ՕF�́u���q�̓��v�ɊO�Ȃ�Ȃ��ƁA�G��ł��Ȃ���V���ĂȂ��w�Ԋy����������������ł��B
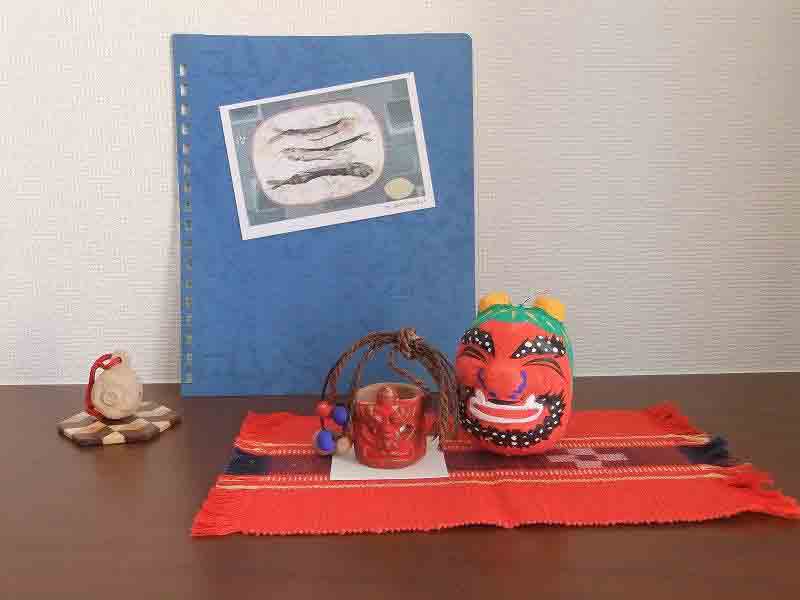
�@�Ƃ���łQ���ɓ���Ƃ����ɗ��t�B�����ė��t�Ƃ����{���̗D�����ᓶ�q�̂��b�A�u���匎�̎l���v���v���o���܂��B�䂪�Ƃł͂��̋G�߂ɁA�P��̋S��炢�̂�����Ƃ������̂����܂��B
�@����̃~���T�[�D��̐Ԃ������ȕ~���ɁA�O�t�̃f�R���~�Ō���������q�̐ԋS�̊�i����Ə������Ȃ�悤�ȁA�ꔲ���ɐl�̗ǂ��Ί�Ȃ̂ł��j�ƁA�ǂ��Ŏ�ɓ��ꂽ�̂��S���L�����Ȃ��̂ł����A����������������ԋS�̓y��B�����ɁA���q�̐��Ŏ�ɓ��ꂽ����̉Ԃ̕����o���f�p�ȓy����Y���܂��B���N�͓������q����̕z�G�́u�����v��w�i�ɒu���ĕ��͋C���o���܂����B���Ԉ�ʂōs����q�C���M�Ŏh�����u��̓��v���A�d�オ��͂����Ə�i�c�Ǝ��掩�^�B
�@�p�����u�z�G�v�͈ȑO�A��ō�����G�n�K�L�̒��̈ꖇ�ł��B����p�̕��͂������I
�i���@�j
��������
�@�P���S���̐[��A���ݓn�����k�̋特���Ȃ��A��̐����I���I���̑т̂�����ւƗ���ď����Ă䂫�܂����B�������s�[�N�ƌ����Ă����u���Ԃ��v�̗����������̂ł��傤�B�Ƃɂ����A���̂��ꂢ�ȑ��ł��B
�@�\���x��܂������A�P�O�N�߂��s�����藈����̐����𑱂��Ă������쌧�̏��쑺�ցA��N���ɓ]�����܂����B�Q�O�P�U�N�̐V�����N�́A���̐V�����y�n�Ō}�����̂ł��B
�@���̑��͕����̑升���ł͓Ɨ��h�̑�����I�сA����s�ւ̋z����ނ��āu���v���т��Ă��܂��B�u�ɂق�̗��P�O�O�I�v�ɂ��I��A�̂Ȃ���̗{�\�Ɖ��ƒI�c�̘A�Ȃ镗�i���c����Ă���A��������������c���ꂽ�n��ƌ���ꌓ�˂Ȃ����A��������܂���B
�@�l���͂R�O�O�O�l�������A���킸�����ȂŁA����҂͂������ʂɌ����Ŋ��Ă��܂��B�ǂ��֍s���̂������艺��Ƃ����R���ŁA��{�Y�Ƃ͔_�ƁB����s�̑P�����𒆐S�ɂ��Đ����ɂ���n��𐼎R�n��ƌ����A�哤���ǂ��̂��̂ŗL���ł����A���쑺���u���哤�i�����܂߁j�v�Ƃ����n��������قǂŁA�̂���哤�̎Y�n�ł��B�f�l�_�Ƃ̎��������r�[���̂��܂ݗp�̎}���₨�����p�̍����A�ԓ��A������ɏ����ƁA���͎��������Ŋy����ł��܂��B
�@���ł́A�Ⴂ�l�����̑��c�Z����̓�����Ȃ��т��n�Ƃ��Đ�������ȂǁA�O������̐l�̗U�v�ɗ]�O������܂���B
�@����ȏ����ȑ��ɂ��A�����Ȃ���A������x�v���i�����{�c�̕ۑ��������߂��j�̂��b�������A�����H���₳�u��͂��������܂Ȃ��v���R�Ƃ��āA�ጎ�搶�i�����v�����a�@���j�́u�ǂ�ȉ��f���f��Ȃ��v�Ƃ����ꌾ�ɁA����҂̑��ŋً}�̑Ή����ł���悤������d�˂Ă���Ƃ����A�����I��ʂ��_�Ԍ��邱�Ƃ��o���܂��B
�@�����������P�x�A�u���̉w�v�łP�O���ԁA�푈�@�͔F�߂܂���Ǝ���J�[�h���������ăX�^���f�B���N�ői����l���������܂��B
�i���@�j
��������
�@���܂���肾�������܂̒�ɁA�Ђ���т������Ȓ������Ɨ����Ă��܂����B������ɖڂ����ƁA���̎��܂�u���Ă����������̋��ɁA�����悤�ɂЂ���т������_�X�ƎU����Ă��܂��B���̌��o���̂��钎�͂ɂ����������]�E���V�ɈႢ����܂���B���܂̒��̏��������Ă������r�j�[�����ۑ��܂����鋰����o���Ă݂�ƁA���̏����ȏ����ɁA�Ђǂ����̂ł͓���O���̌����������A�����̊Ԃɂ͂܂������ē����Ă���̂��������œ����Ȃ����̂�A�Ƃɂ����A�����A������t�I
�@�u���킠�c�v�ڂɂ������̃V���b�N�͂��Ȃ苭��ł����B���������������������r�j�[���܂Ȃ̂ɁA���������ɂ͓��ɂ��������Ɠ����悤�ȉ~�`�̌����������A�Ă̏����ő��₦�₦�̘A�����A�V�N�ȋ�C���z�����߂ɂ���Ƃ̎v���Ő��蔲�����̂��Ǝv�킹�邠�肳�܂ł����B
�@���̃A�Y�L�]�E���V�͂ƂĂ��ɐB�͂������ŁA�ꗱ�̏����̒��Ő�����܂ł���Ƃ������Ƃł��B�ُ픭���Ǝ~�߂��̂͂�����̎����ŁA���ɂ��Ă݂��������ɐ����Ă����̂�������܂���B
�@����͉Ă̘b�B���܂��A�V���ɓ��ނ����n���鎞�������܂����B���ł������̎}���̔����������ƁB����������O�̍����ł��B�̂ꂽ�Ă̓��͒Z���Ԃʼn��ŏオ�邵�A�����̂��̂̂ӂ��悩�ȊÂ݂������āA�r�[���Ɍ������܂���B�ł��A�����ɂ������������ɂȂ��Ă��܂��̂ō���܂��B
�@�Ƃ���ŁA���_��Ŗ�����Ƃ������Ƃ͂��̂悤�Ȓ��̊Q�͂�����ꂸ�A���i�Ƃ��Ẵ��X�N��w�������ނ��ƂɂȂ�܂��B��������Ċ撣���Ă��鐶�Y�҂́A�_����U�z���锨��艽�{���̘J�͂�v���܂����A�������ނ�̐l����͂ǂ�������o�ł��܂���B���Y���̉��i���̂��̂��������v���ł��Ȃ��_�Ƃɂs�o�o�́c�ȂǂƁA���̒��ɂ͎G���Ȏv����������������������ɋ삯����܂��B
�i���@�j
��������
�@��M�z���𑖂�Ȃ���A�����̈����ȂłX�O�L���̃X�s�[�h���o�Ă���ɂ�������炸�A�E�֍��ւƉ߂�����i�F������낫���ƒ��߂Ċy����ł���܂����B
�@���m�c���ɓ���ƍ����Ɂu���܂�R�v�A���̉E�ׂɃ`���L�̓�{�̎w����˂������l�Ȋ�ڂɓ���܂��B���܂�R�Ƃ����͎̂�������ɖ��t���܂����B�ӂ�����Ƃ����Ⴂ�R�ŁA���傤�lj����猩�����܂�̂悤�ɍi��ꂽ�`�̎O�̃s�[�N���R�����`����Ă��邩��ł��B
�@�����Ă����ɐ^������ȍr�D�R�������Ă��܂��B�o�ˎR�Ƃ������������Ȃ�����������䃊�Ƃ�����f�R��ǂ̉��܂ł͖{���ɕ���ȍb�̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��B
�@�������߂���Ɠ��{�O���i�̈�A���`�R�̂��̓Ɠ��ȃM�U�M�U�̎R�B���̓��͂�����������������ĉs���͂���܂���B�₪�āA�E���ɐ�ԎR�B�������_���Ⴍ����ĎR�����A���̋������܂���B����ł��A�قƂ�ǐ^����ʉ߂���ꏊ����͎R�����F�Â��Ă��邱�Ƃ�������܂����B
�@����������N�̂��̎����A���傤�ǂ��̕ӂ�Ō�����ԎR�͌��t�ɂł��Ȃ��قǑf���炵�������݂��̍Œ��ł����B�_�Ԃ���~��z�̌��𗁂т��Ƃ���̐F�Ƃ�ǂ�̑N�₩�ȐF�ʂƁA�_�������������Ƃ���̂����F�ʂ̃R���g���X�g�͊G�̂悤�ł����B�ǂ����ɎԂ��~�߂Ďʐ^���B�肽���Ǝv�����̂ł����A�������H�ł͂�������Ȃ��܂���B
�@�Ƃ���ŁA���͂P�N�ɂP�x�A�R���n�敶���Ղň�ʕ�W�����邻�̎��ɂ��킹�Ĕo������܂��B�w��܂�Ȃ����錾�킸�����Ȃ̓��e�ł����A���N�̋G��Ɂu�����݂��v�Ƃ����̂�����܂����B�����ɓ��ɕ����̂́A���N�O�ɖk�A���v�X�̗��R����ܐF�����֍s���r���A��̉z�Ƃ��������z�����Ƃ��Ɋ�O�ɊJ�����i�F�ł����B
�s����z���Έꕝ�̊G�̑����݂��t
�i���@�j
��������
�@�u���A���B���t�����������ˁB���ꂾ�A���ɗ��������āv����Șb�ɑ�������܂����B
�@�b�Ƃ����̂͂����ł��B�ނ͂��̐��T�ԂƂ������́A�����������Ă��錋�\�ʓ|�Ȏd�����i�s�ŏ������Ȃ���Ȃ炸�A�����Ԃ�Ɛ؉H�l���ĉ߂����Ă��������ł��B���̓�������������ƒǂ��A����ł��u�ǂ����ړr�������A�ߌ�ɂ͂����I������v�Ǝv�����Ƃ��ɁA���̗���̐����Łu�����A���т͂ǂ�����v�Ɖ�����ɕ����������ł��B����Ɓu����A��������A�����͂������H�ׂ܂����v�Ƃ����Ԏ��B�����Ő��A�u���ɗ������I�v�ł��B
�@�ς܂����H���̎���Y���A�Ƃ������Ƃ͂�����{�P�̑����Ƃ��ėǂ��m���Ă��܂��B�Â����Ƃ͊o���Ă��Ă��V�������͖Y��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A�قƂ�ǂ̐l�͒m���Ƃ��Ď~�߂Ă��܂��B�����đ��l���̂����͏��Ă��̏ꂪ���܂�܂��B
�@���̘b����������A�Ȃ�Ǝ��͗F�l�Ƃ̑҂����킹�̓����ԈႦ���̂ł��B���߂�ꂽ���ԂɌ��߂�ꂽ�ꏊ�ŗF�l�̎Ԃ�҂��ƂP�T���B�g�ѓd�b�������Ȃ����͂��̂܂܂��������҂��܂����B�҂��Ȃ���ӂƁA����A�����͉���������������Ƌ^�╄�����̒��œ_�ł����̂ł��B�������������̓S�~�o�����C�ɂ��Ȃ��Ă��悢���A�c�Ƃ������Ƃ͐��j���B���j���ɂ͐����̂łƌ��߂������́A�c�����ؗj���ł����B�}���ʼnƂɖ߂�J�����_�[���m�F����Ɩ̑O���ł͂Ȃ��ł����B�����A���ɗ������I
�@�m���ɂ��낢��ȗp�����ڂ����ς��̖����̌��ԂɁA���}���g�ݍ��V���Ȗł͂���܂����B�����炻�̋C�ŊO�o�p�̕��𒅂āA�҂����킹�̏ꏊ�ɏo���������́g�Ă�����h�Ƃ����m�M�I�Ȏv�����݁B�������ĘV���̍����͉����Ȃ��߂Â��Ă���̂��Ȃ��B
�@�������A�Ɩڂ̑O�͈�u�Â��Ȃ�܂������A��w�Ǝv�����Ƃɂ��܂��傤�B
�i���@�j
��������

�@Bouchon�i�u�V�����j�Ƃ����̂̓R���N�ŏo���Ă��郏�C���̚ނ̐��̂��Ƃł��B
�@�u�͂Ȃ̂����ȋ��v�Ƃ����q�ǂ��̖{�������m�ł��傤���B�߂��ۂ��̊i�̗ǂ����́s�ӂ��邶�Ȃ�ǁt�͑̂Ɏ����킸�A�R���N�~�̖̉��ʼnԂ̍���������ł���̂��D���ȋ��ł����B���͂��̊G�̕ł��ƂĂ��D���ł��B�ł��A�����͊G�{�A���ۂɂ͂��̊G�̂悤�Ƀu�V�������̎}�ɗ�Ȃ�ɐ����Ă���킯�ł͂���܂���B
�@�Ƃ���ł��̃u�V�����ł����A�ЂƂЂƂɐ����ꏊ�≽�N�ɍ��ꂽ���Ƃ����������Ă��܂��B�Ⴆ�A�����MEDOC2008 Mis en Blle au Chateau VIGNOBRE POITEVIN�ł��傤���B����Mis en Bouteille dans nos Cave�A�܂��A�����͉��������ꂸ�ɂT�{�̖�̂��˂�ꂽ�Ƃ���ɑf�G�Ȃq�̃f�U�C�������������Ă�������A�Ԃǂ��̗t�Ǝ��Ɩ��̊G������������Ƃ����̂�����܂��ˁB
�@�g����܂��ˁh�ƌ������̂́A���A���Ă��邩��ł��B�R���N�V��������قNJ��l�����߂Ă����ł͂���܂��A������܂���ɓ�����̂Ȃ̂Ŏ̂Ă�悢�̂ɁA���̕��͋C�����Ƀo���[�h�Ȃ�ł���ˁB�s�������Ƃ��������Ƃ��Ȃ��Y�n�̂͂��݂F�̗[��ꎞ�A�W�����̒��̓c�����i�Ȃǂ����ɕ�����ł����肵�āc�B
�@�܂��A������ʂ�߂��鎞�ɂ́A���̚ނɓ\���Ă��郉�x���̃f�U�C�������ĕ����܂��B���C����E�B�X�L�[�Ɍ��炸���{���ł��Ē��ł��A�����͔@���ɂ����́u�l�i�v������Ă���Ǝv����̂ł��B
�@�ŋ߂̓u�V�����̑���ɋ������̊W�������Ă�����A���x�������Ɋȑf�ȃf�U�C���ɂȂ��Ă����肵�āA���C������̎艖�ɂ������d���̍��Ղ�����������ꂪ���ł��B���ݏI�������̂Ă��Ă��܂��悤�ȕ��ɗ͂𒍂��̂͌o�ϓI�����������ƁA���͂Ƃ������A�f���C�͖����Ƃ������Ƃł����B
�i���@�j
��������
�@�~�V���������O�c���ό��n�Ɏw�肵�����ƂŁA�܂�ŋ���̕��s�ғV���̂悤�ȍ����R�ł����A���̐l�o�������ĐÂ��ȓ�����������̂Ȃ�Ƃm�g�j���Љ���������́A���⒆���N�̓o�R�҂œ�����Ă��܂��B
�@�����R�i�T�X�X���^�����s�j�́A�Â�����C���̎R�Ƃ��Ă̗��j�������A���́g��N�̐X�h�ɂ͓Ɠ��ȐA����������������M�d�ȎR�ł��B���ӓ��H�̏a�؊ɘa��}�邽�߂ɁA���̎R�Ɍ�������ʂ����ƂŋN�����ꂽ�V��ٔ��ɂ͑S�������ڂ��܂����B
�@�ߓ��A�F�l�ɗU���āu�Â��ȁv�ƌ�����R�[�X�̗�����������Ă��܂����B���A��Ƃ������̒ʂ�A���˓�������悭�������铹�������A�����Ɩ؉k����̓������ǂ�܂����B��x�݂��������ɁA�ӂƑ����Ƃ̍����y�̏�ɑ��z�̗ւ��������`����Ă���̂��ڂɓ���܂����B�܂��邢�����X�e���h�O���X�̖͗l�̂悤�ɒu����Ă��܂��B���グ��A�u�₩�ȕ��ɗh���̗t�̊Ԃɐ��ݐ��������āc�B�����������B�����Ƃ��A���킩��藣����邽�߂ɂƁA�K���l���������������܂����B
�@�؉k����́A�n�ʂɏo������̌`�����z�Ɠ����ۂ��`�����Ă��܂��B�ǂ�Ȃɓ���g�}�Ǝ}�̊Ԃ����蔲���č~���Ă��Ă��A���̗t����錄�Ԃ̌`�ɂ͂Ȃ�܂���B�������H�̂Ƃ��ɂ͌��������z���̂܂܂̌`��������O�����̌`���n�ʂɉf���o����܂��B�Ȃ��s�v�c�ł��ˁB
�@���́u�؉k����v�Ƃ������t�ɂ́A�����Ō��Ă������Ă��A���S�n�̗ǂ��֎q�ɐ[�����܂����悤�ȐS�n�悳���o���܂��B�O���ꎫ�T�ł��̌��t���������L���������悤�ȋC�������̂ł����A�X�̑������{�̕����������t�Ȃ̂ł��傤���B
�@����Ȃ��Ƃ��C�ɂ����l�͑��ɂ����āA�l�b�g�ɂ͊O����ŊY������\���̈ꗗ���ڂ��Ă���v���O������܂����B�������ɐX�ь��̖k���ɂ͒P�ꂻ�̂��̂�����悤�ł��B
�i���@�j
��������
�@����l�̂�����ē����Ă����������߂ɁA�k��ɂ��Z�܂��̂j�����K�˂܂����B
�@�z�P�T�O�N�͒������Ǝv����{�\�_�Ƃ́g�T�����h�͂��܂��ɓy�Ԃ̂܂܂ŁA���͂ɂ͖��ō�����V���N�t�����[�A���H�̗r�A�^���Ԃȑ�̒܂��ɕ҂ݍ��������A�ǂ�̃g�g�����X�A�ǂ��Ƃ��Ă��ڂ��ӂ��i���Ƃ��닷���Ə����Ă��܂��B
�@���グ��قǍ������̉��̐���ǂɂ͏���G�Ȃǂ̊z���A����������Ƃ������Ă��܂��B���̒��̈�A���G�������ƌ��Ă�����u����A���m����̍����v�Ƃ������Ƃł����B
�@�������m����́A���̍��������Ȃ���푈�����̐�]�I�ȓ��X����U���̊�n�ʼn߂����ꂽ�Ƃ����A���ʂȎv���̂���R�������ł��B�~��t���́w�����x�ɕ`���ꂽ�s�풼�O�̎��̊o��Ɛ��ւ̎����A���Ԃm����������悤�Ȏv���Ő����Ă����̂ł��傤�B
�@�ł́A����ɁA�ƌ����ĕ\�ɏo��ƁA�Ȃ�Ɣ[���̒����炱��������Ă���n�������̂ł��B�S���ō��g�݂����āA���̂̕����͑S�Ĉ����҂�g�肵�Đ��I�ɍ��ꂽ���g��̔n�B��������Ɨ��p�́g�n�炵���h�͂��邱�ƂȂ���A�፷���͂��̂��������̂悤�ŁA���A���Ă��݂��ȂłĘb�������Ă��܂��܂����B�u�����Ɛ��@������č�����̂�A����Ă݂�H�v�c�O�Ȃ���A���̓��̓X�J�[�g���͂��Ă����̂ł��B
�@��������q���̈�������Ƃ����ׂ��⓹�����Ȃ���A����܂łT����������Ȃ������̊ԂɁA���̕ӂ�ɎR�̐_�R�G�C�J�����Ƃ��������������ĂƂ��A�肪��������o���Ƃ��A�͂Ă̓����J�[�Ŋ����^����̘b��g�U���U��ŁB�����j���̈ꑰ�̋�����n�Ƃ��������ɂ́A������ɉ��Ɖ�������ƐΈ͂��̌��Ԃ�������čs���܂����B�k���ɎՂ���̂͂Ȃ��A�y���ɏ�B�̎R�X�B��n����̒��߂͂ƂĂ��ґ�ł����B
�i���@�j
��������
�@�a�c�͂q�́w�ˈ�@�{������x�Ƃ����������A�����Ԃ�O�ɓǂB�u�~�r���ؐ}�v�Ƃ����͂ŁA�ǂ��ɂł�����悤�ȎG�����H�ׂ��邱�Ƃ�m�����B����ȗ��A�ڂɂ���G���ɋ����������Ă���B
�@�ŋ߁A���ЎR�̉���s���Ă���u�������V�s�ǖ{�v�Ƃ������q�������B����ɂ͖̌��\�ƂR�W�̗������Љ��Ă���B
�@���\�́A�y�N�Y�z�������i�E�����l�ቺ�A�y�^���̉�z�b���E�����l�ቺ�A�y�E�R�M�z�����l�ቺ�A�y�^���|�|�z���݁E�����A�y�m�r���z���s�A�y���i���~�z�������A�y�C�m�R�Y�`�z���t�E�����E�}�`�E�ߒɁE���A�A�y���u�J���]�E�z���A�E��A�y�x�j�o�i�{���M�N�z�ݒ��̓����𑣐i�A���X�B
�@�����́A�ȒP�����Ŏ��̂܂݂ɍD�]�Ƃ����̂��^���|�|�̃x�[�R�����B�^���|�|�̗t���ςQ���قǂ��A�X���C�X�����x�[�R���ɂ��邮��Ɗ����ėk�}�Ŏ~�߁A���̃t���C�p���ŏĂ��A���E�R�V���E�Ŗ�����B�C�m�R�Y�`�̓V�Ղ�Ƃ����̂��ȒP�������B����Đ��C��U�藎�����t�ɔ��͕��𔖂��܂Ԃ��ėg����B�݂����ɂ������̃n�R�x�����蔫�ł����ăy�[�X�g��ɂ��A���������A�d�q�����W�Ő��������ēV�����������āg�n�R�x���h������Ă����A�����U�肩���ĐH�ׂ�����������̈�i�ƌ����悤���B�i�Y�i�̂��Z���͂����ƊȒP�ŁA���ꂱ���������Ċ��߂ɂ��ݖ��A���������B
�@�Ƃ���ŁA�^���|�|�̗t�͒N�ɂł���������Ǝv�����A�C�m�R�Y�`�͌䑶�����낤���B�H�ɂȂ�ƕ��ɕt�����t�j�̂Ƃ����Y�{���⑳�ɂ������ĂȂ��Ȃ����Ȃ��A����ł���B�i�Y�i�͂�B
�@��������t��̗t�𗘗p����̂ł��ꂩ�炪�����̃V�[�Y���B��킭�͔r�C�K�X�𗁂тĂ��Ȃ��t��E�݂������̂��B
�i2015.2.3�@���@�j
��������
�@�R�[�q�[�u���C�N�A�ڂ̏��߂ɁA���ɔ����Ă�������o�C�I�����ɂ��ď������B���ǁA���̂��̂Ƃ�����蕃���y���ނ��߂̊y��ɂȂ����̂����A����A��������Ȃ�o���Ă���A��͂莄���a����̂��������낤�Ə���Ɏ����ė����B���̌���k�ł���B
�@�����A�����o�C�I�����͂��̂܂܉�������̉��ɂ��܂�ꂽ�B�ӂƎv�������ăP�[�X�����o���Ă݂��Ƃ��ɂ́A���Ԃ��K�т��ĊW���J����̂Ɉ��J����قǂ������B�|�����o������A�Ƃ���Ƀo�T�b�ƈ�C�ɖт��������B�|�͖т�ւ��Ďg���Ƃ������Ƃ���m��Ȃ������̂ŁA�P�[�X���|���u�j�ӃS�~�v�ɏo���Ă��܂����B
�@�o�C�I������e���F�l������B���̎�𗣂�Ă���Q�O�N�߂����̃o�C�I�������A���Ȃ����ƂȂ特�̏o��y��ɖ߂������Ƙb��������A�H�[���Љ�ꂽ�B
�@�H�[�͍��c�n��B�C�Ƃ�ςC�^���A�ɂ͍��ł����N�o�����Ęr���Ă���}�G�X�g���́A�������Y����Ƃ����B�܂��͋|��˂Ȃ�Ȃ��B�u���̔N��ł���Ƃ��āv�̔��e�Ȃ炱�̒��x�̋|�ŏ\���ƁA�U�O�O�O�~�̋|���S�O�O�O�~�ɂ��Ă��ꂽ�B���ꂩ��o�C�I���������߂����߂��č�Ƃɓ������B���̋�́c�A���̃j�X�́c�A���̒����l�W�́c�A���̌��́c�ƁA�{���̃o�C�I�����̐�������Ԃ��ǂ��������̂ł��邩��������Ă���Ȃ���A�Ō�Ɂu���̐l�����ւ��ĕs�v�ƂȂ������̂ł����v�Ɗ{���Ă����t���Ă��ꂽ�B���ꂩ��}�G�X�g���͊��ꂽ����ŐV�����|�ɏ�����h���Ē����������̂����A�e�����܂ꂽ�y��̂悤�ɗǂ������������B
�@�}�G�X�g���̖��@�̎�ł�݂��������o�C�I�����A2���Ԃɋy�ԃ����e�i���X�Ȃ̂ɁA�V�����|�Ə����̑�������������߂��Ȃ������B
�i2015.1.17�@M�EO�j
��������

�@���N�̏��߁A�v���Ԃ�ɉ�����F�l����f���h���r�E���̏����Ȕ��������������B�G���W�F���E�x�C�r�[�s�O���[���E���t�Ƃ������O��t����ꂽ�Ԃ͂R�Z���`���炢�̏������ŁA�ӂƉԂ̒������̗ΐF���ԑS�̂����������ΐF�̏����������ɂ݂��āA���^�ł���B�ʂ�߂������Ȃǂɂӂƍ���̂��A���������ȊÂ�����ōD�������B
�@�A���̊Ǘ��͋�肾���A�ꉞ���Ԃ̓J�[�e���z���ɁA��͗₦�߂��Ȃ������̒I�̏�ɒu���Ă݂��B���ꂪ����t�����̂����Ƃ��Ɛ������������̂��A���ɓ��ɉԂ̐��������Ĕ��͉Ԃɖ����ꂽ�B
�@�₪�ĉԂ̎������I������B�\�Ɋy���̂ɁA�����ŗ~���o���B����Ȃɂ�������Ԃ�����̂����犔���������Ĕ��̐��𑝂₵����ƁA�̂Ȃ��̗~����ꂳ���낵���A�m�g�j�́u��̉��|�v�Ƃ����Â��G���𗊂�ɂS�̔��ɕ����Ă݂��B�ď�̏����Ɗ����̑�͂���ł����Ƃ��ł������ȂƎv�������A�}�ȉ��x�̕ω��ɂ͔Y�܂��ꂽ�B
�@���A���̒��ɗ���Ȃ��ɔ[�܂����f���h���r�E���́A��������A�Ԃ��炩���Ă���Ă���B�ǂ���犔���c���āA�܂������Ă͂����Ȃ������悤���B���Ƃ����b�����čs�����肾���A���N�̏t�͍炢�Ă���邾�낤���B
�iM�EO�j
��������
�@����s�̌����قł͖��N�H�ɕ����ՂƂ����s��������B���N�A�܂�������P�N���o�Ȃ��p�\�R���w�K�T�[�N���̈���Ƃ��ĎQ�������B�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��Ƃ����A�p�\�R������g���ă����o�[���ꂼ�ꂪ�I���W�i���̃J�����_�[������ēW������Ƃ������̂��B�C���^�[�l�b�g�Ŗ����\�t�g���������A�C�ɓ��������̂��_�E�����[�h���Ď����̍l�����`�ɉ��H���č�蒼���Ƃ����p�\�R���p�ł���B
�@�u�t�̓p�\�R�����g���Ύ��ɊȒP�ƌ����Ă������A�p�\�R�����u��g�v����Ƃ������ɂ́u��g�v�Ɠ��Ă����Ȃ��Ƃ������B��ʂ����߂Ȃ���ǂ����ǂ�����Ή����ǂ��Ȃ�̂��Ɣ����Ȓ������������A�ڂ��r����ꂽ����Ɏv�����ʂ͓���ꂸ�A�C�͂��ނ��Ă��܂��B���s���J��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ƃ��P�Q�������I����̂ɂQ�������v�����B
�@�_�E�����[�h�Ƃ����̌������邱�ƂɈӖ�������ƍl���Ď��݂����A�ǂ������l�̍�������f����q���č����A�͂��߂��玩���̎v���ʂ�ɍ�����ق����ȒP�ł͂Ȃ����ƁA�Q��ڂ�����Ă݂��B������̓G�N�Z���łP�N���̓��ɂ���\�ɂ��邽�߂Ƀp�\�R���𗘗p�������A���Ƃ͍H��Ƃł����������A�v���o�̎R�s�̎ʐ^�������o���Đ�����\�����肵�āy�R�ɗV���X�z�Ƃ������J�����_�[���o���オ�����B�P�O�O�~�V���b�v�Ō������ؐ��̂�������̃C�[�[�����w�����č�i���ڂ��Ă݂�ƁA����A�s����s����B
�@�����Ղł́u��̉ԁv�u����̕��i�v�u�r�̃C���X�g�v�Ƃ������ʐ^��C���X�g�����C���Ƃ������́A�R�������P���Ō���Ƒ��X�P�W���[���E�J�����_�[�A�Q�������Ƃ̃n�K�L��̑��J�����_�[���A�����o�[�̗͍삪�o��������B �g�����R�ɂ��������������h�Ƃ����Ђƌ����Ƃ̞x�^�u�쒹�v�̃J�����_�[�́A�����Ƃ����Ԃɕi��ƂȂ����B
�iM�EO�j
��������
�@�b����K�[�f���v���C�X�ɓ����s�ʐ^���p�ق�����B�W����ꂾ���ł͂Ȃ��}������n�쎺������A��K�z�[���ł͏�f��i�������Ƃ����A�ʐ^����Ƃ�����p�ق��B���C�̂���2016�N�H�܂ŕ��Ƃ��������O�A���̂ڂ肳���낵���b����w���瓮�������ɏ���čs�����B�ړI�͂R�K�́sall about life and death�@�����邱�Ǝ��ʂ��Ƃ̂��ׂāt�Ƒ肷��ʐ^�Ɓu�������F�v�̎ʐ^�W�ł���B
�@�[�[�łɃ��F�g�R�������̏P�����������g�C�r���̐w�n����͂܂����������ׁX�Əオ���Ă��܂��B���S�ɏĂ��ꂽ�w�n�̏Ă��Ղɂ́A�T�O�̂قǂ̍��ł��̎��̂����ׂ��A�܂��A�o���o���ɂȂ�������肪�@��o����Ă��܂��B���͂R�O�{�قǂ̃J���[�t�B�������u���ԂɎB�e���Ă��܂��܂����B��������ăJ�����̏�ɂ������藎���܂��B�^���̎��A��l�̘V���m���A���̘r�������āA���ł�⥂ɕ�܂�Ă��鏬���Ȏ��̂̑O�ɘA��Ă䂫�܂����B�ނ�⥂ɂ�����ꂽ���̔F���[�̉D���w�����Ȃ���A�u�킽���̎q�ǂ�������ł��܂����B�`���[���C�I�@����ł��܂�����B�ǂ����ʐ^�Ɏʂ��Ă�����I�v�ƁA�b���悤�Ɍ����܂����B�i�����j�^���̌�A���p�C���b�g�̂f��тɎ��͉�܂����B�ނ͎��̎ʐ^����W�����w���C�t�x���́u�X�����F�g�i���푈�v�̃y�[�W���߂���Ȃ���u���̓�̔߂��݂́A�푈�ɗՂޓ샔�F�g�i�����{�R���m�̏h���Ȃ̂��B�悭������B���Ă��ꂽ�v�Ƃ����āA���̎�����������肵�߂Ă��ꂽ�̂ł����B�샔�F�g�i���ł́A��]�I�Ȑ퓬�������������A���y�����ׂĐ��ɂȂ��Ă��܂��B���m�����́A�Ȏq��A��ĖC�̉������܂���Ă���̂ł��B�[�[�i�w�샔�F�g�i���푈�]�R�L�x���Ƃ������j
�@�A���O���͐^���ʁA���i�������l������������܂Ȃ��B����Ȃ̂ɁA�l�ԂƂ��Ď��ނ̖ڂ́A�t�@�C���_�[�Ɏ��߂������ɑ�������点��B�u��x�ƕ�������܂��Ƃ��߂��v�ނ̗B��̕���A�����ȃJ�������A���E���Ɂu�푈�v��m�点���̂͂S�O�N�ȏ���O�������̂ɁA���A���{���t�́I�I�@
�iM�EO�j
��������
�@�Ă����ɂ�����Ǝ��˂����B��̓��|����A�Ƃ����������X�^���X�ł͂Ȃ��B�Ȃo���邩������Ȃ��A�Ƃ������A�E�g�T�C�_�[�I�Ȃ���ł������B�}���c�[�}���w���ł͂��邪�A�搶�́u�o�����ĕ����������Ƃ͋������邯��nj�͖{�����āv�Ƃ��Ă��������w�{�������������B�搶�̂��ƂŐ��`�܂ł͂��邪�A�Ă��̂��ւ�������̂����̏o���ɂ���q���ɂ��C���ł���B
�@�ӂ��A�R�[�q�[�J�b�v����肽���Ƃ��A����A���邢�͂��M�A�Ǝ��p�I�ȖڕW�����炵�����A�ŏ��ɍ�����̂͏�铔���v���[�g�ł���B�P�T�Z���`�~�Q�O�Z���`�قǂ̓��ɉ߂��Ȃ��B�˖_�ŏ�������L���v�̂ŋϓ��ȂT�~���قǂ̔�����A�������ɂ��ꂾ���ł͍쓩�Ƃ����Ȃ����낤�ƁA�I���I�����̂V�̐��������ǂ������������Ă����t������g���������肵�Ă݂��B
�@����s�˂Ă���ƁA�Ȃ��ׂ����Ƃ͏��������f�ł���悤�ɂȂ��Ă�����̂��B�����Ȋ�𐔓_������̂��z��������Ă݂��B����Ȃ��̂����l�͂߂����ɂȂ��B�Ⴊ�Ȃ��̂Ŏ��݂ƂȂ�B�܂�o���オ���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ƃ��c�ł���B���ʁA���͏Ă��Ă��邤���ɐ�����䂪�ނ�A����ɂ��C���̊G�t���͎��̈Ӑ}�Ƃ͑S���Ⴂ�A�S���܂Ƃ߂ăK�b�V���[���A�ƒ@���t�������C���������B
�@�Q�����ȁA�Ƙr�g�݂����Ă����Ɗz�߂Ă��邤���ɁA���������Ă��́g�G�t���h�Ȃ���܂邩�A�Ƃ������Ȋ�]���������B��Ƃ̊G�Ƃ����̂͂ǂ�Ȋ��ɂ����J�������炷�͂�����Ƃ������Ƃ��낤���B�V���K�[���̔ʼn���Q�_�A�c�����O�̃��g�O���t���P�_�A�����ĂȂ��ł�����͂܂��������ȁA�Ǝv����ŏ�̊z�ɂ͕��̊G�̎ʐ^����ꂽ�B
�@�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA�ł���B
�iM�EO�j
��������
�@�T�C�h�{�[�h�̏�Ɏ��v���O����B������������Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�@�^�ɂ���̂͒��a���P�T�`�U�Z���`�̖Џ@�|���ɂ������̂ŁA�a����p���ăI���W�i���̂�������S�ʓI�Ɍ����Ă������̎��v�B����͏���s�̖�V�V�������X�u�܂������v�ɏo���肵�Ă������̍��ꂽ���̂ŁA������Ƃ����W�������Ē��������̂��B
�@�E���̉��ɂ́A�����T�~���قǂ̓����ŁA�c���P�W�Z���`���炢�̎l�p�����v������B��앗�����������邪�A���ɓo�^���W���낤���A�ւ�����M�yMARUI�ƈ�����ꂽ�����ȃV�[�����\���Ă���B ����͐V����̃��T�C�N���X�ŃV���v���ȃf�U�C���Ɉ�ڂڂꂵ�Ĕ������߂����̂��B
�@���̑O�ɂ���̂́A�N�}�̂ʂ�����݃R���N�^�[�̉Ɛl���A�N�}�̃C���X�g�������Ƃ����ċ��߂������̖ڊo�܂����v�ŁA�b�j�����Ă��܂����̂ɂ����Ɠ����Ă���B
�@���̎O�͓��ɈӖ����Ȃ������ɂ���B���X�ڂ����ƎO���O�A�����悤�Ȃ��̍����j���p�x�ɂ��Ă���B������O�Ȃ̂ŋC�ɂ����߂Ȃ��������A�����p�x�������O�̎��v�̐j����������Ă��邤���Ɂu�ǂ����Ō����c�v�u�Ȃɂ���i������i���������悤�ȁc�v�A����ȋC�����Ă����B
�@�������A�~�܂������v���B�L���ŁA���������̂W�F�P�T���������܂~�܂������v�B����ŁA�P�P�F�O�Q���������Ď~�܂������v�B�{�錧���|�㒆�w�Z�ɂ́A�R�N�O�̓����{��k�ЂŒÔg���������Q�F�S�U�����܂~�܂������v���c����Ă���B
�@������Ȃ�C�ɂ��Ȃ�Ȃ��������̎��̎����Ȃ̂ɁA�������ĎO���ԂƑi���Ă��鉽���̂����������B�P�X�S�T�N�W���P�T���A�����Ǝ��̓V�c�̎��Ԃ͂��̓��Ɏ~�܂����ɈႢ�Ȃ��B���ꂩ��V�O�N�߂��A���a�Ȏ��Ԃ��������ė����͎̂������Ȃ̂��B
�iM�EO�j
��������
�@�����鍑�̗v�l�Ƃ�����l�����̌����ŁA�܂����Ă��}�X�R�~�͓�������B�̂��牉���Ƀ��W�͂����̂��������A���̎��I�ȍ��͎��ɂȂ����킵���B�l�I�Ȑl�i�̌��@�����邱�ƂȂ���A�ނ�̑����͓��{����悭�m��Ȃ��̂��낤�Ƃ��v���B���t�́A���j��Љ���Ȃǂ�w�����Ĕ����ȈႢ���܂݂��G�ɔ��W���Ă����B�����������Ƃɖ��ڒ��Ȕނ�͂��������A���s�̃c�C�b�^�[�̌����p���ėp�͍ςނƍl���Ă���̂��낤�B
�@�ߓ��A�u�ԒZ�ҏW�v��ǂB��ƁA�����ւ́u���{�l�ɐ��܂�Ȃ���A���邢�͓��{��������Ȃ���A���Ԃ̍�i��ǂ܂Ȃ��̂́A���������̓��{�l���������������Ă���悤�Ȃ��̂��v�Ƃ����Ă���B�ނ́u�R���L�v���琄�@���āA���������Ԃɋ����邱�Ƃ͂��Ȃ�����B����A�J�ł́A���Ԃ̍앗�͌��z�I�łǂ����ٗl�Ȃ��̂����Ƃ���ɕ`���Ă���Ɖ��߂���Ă��Ȃ����낤���B�Ƃ��낪�A�����ł͂Ȃ��̂��B
�@���Ԃ̖ڂ͎��ɏڂ����A�����炩�Ȃ�Ȋw�I�ɁA��������������ĕ������ώ@���Ă���B�w��A�O�H�[�[�\��A�O�H�x�Ƃ�����i�́A��̕~�̂�����Łu���傱���傱�Ƃ������͂ӂ�ӂ�Ɓv�����Ă����܂���ׂȂ��q�����A�꒹�ɗ�܂���Ă��̊Ԃɂ����Ō����Ȃ��Ȃ�܂ł��A�u�^�Ȃ����ɐ��߂��悤�ȁA���̗����A�������₩�ɔ�Ԃ̂ɓ��邩�B�������A�������͖O�����Ɏ��߂��B�v�ƁA����͂��悻1�����́g�����Ǝq��ċL�^�h�Ƃł������ׂ����̂��B�������A���̍�i�̌㔼�ł͖��ȁu���̂��h�v�֕��ꍞ�ނ̂����c�B
�@�u���{��������Ȃ���v�Ƃ����w�E�ŒɊ�����̂́A�������t�c�Ō��߂Ă��܂����Ƃ��鐭�{�̂��������Ȃ��y���̎コ���B�����ɁA���͂̎g���u�Ì��v���R���Ȃ������f���ȓ��{�l�̑������B
�iM�EO�j
��������
�@�����̐����̕Lj�ʂ����I�ŁA���̏��I�ɂ͖{�������ƕ��ׂ��Ă���B�u�܂�Ő}���فI�v�Ɩڂ����������Y����Ȃ����i������B����͏��w�Z�U�N���̂Ƃ��Ɋ_�Ԍ����A���ē�̒��j�̕����Ȃ̂��B����ł����{�͈��|�I�Ɋ�g���N�������ɂŁA���ɂ������o�ł���Ă������N�����̖{�͂��ׂđ������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̕n�������������Ă��������ɁA���͎��ɕ��ɖ{���ċA�邱�Ƃ��������B�{�̉e���͂͑傫�������B��g�̗c�N���Ɂu�A���v�X�̂��傤�����v�́A�����R�D���Ɍ����킹�������Ǝv���Ă���B�����������瑵���Ă�����������̖{���A�������������̂����ł͗��R���肩�ł͂Ȃ��̂����A���Z���̎��ɐV���̓��������o�đS���̗~�����Ƃ����l�ɑ������B���̌o�����u�{��������Ƃ������ƁI�v�����Ɋw�����B
�@�ߓ��A���ЂƂ���ɓ��ꂽ���{���������B���ɔłł���Ȃ���A���i�͂Ȃ�ƂQ�O�O�O�~ɁB�Y���ɐ����̕��䂩���э~�肽�B����́w������̃L���M���X�x�Ƃ����R������̖{�ł���B
�@�����͂P�D�T�Z���`���炢�ŁA�P�U�U�ł̎�̂Ђ�ɏ��T�C�Y�B��E���E�����̂��ׂĂ����{�l����|���A�V���W���T���H�[�Ƃ����A������̏Z������݂Ă��Ԃ���ł͂Ȃ����Ǝv���H�[�Ő��삳�ꂽ�A����Q�O�O���̂����̈�����T�C������œ͂����B
�@�m��l���m��R�����́A���ݏȋΖ����o�Č��݂̓V���W���T���i���\����^�̃��}�}����ɂȂ�j�H�[����ɂ��鑢�{�Ƃł���B�G�b�Z�[�ɓY������쒹��ԁA����R�̊G�̓W���K�C���ɂ���łŁA���̂��炩���F���ƃV���v���ȍ\�}�ɂ��l�����\��Ă���B�M�d�i�Ƃ��ď����鍋�ؖ{�Ƃ͉��������̖{�A�����Ď�����Ȃ������̏��ƂȂ����B
�iM�EO�j
��������
�@���łǂ��Ȃ鎖���ƐS�z���Ă����ւ��^���ԂȉԂ���������炩������A�����玟�ւƒ������Ԃ��炯�ɂȂ����B�Â�����ɕӂ�����ƁA����˂̉ԁB�����ɗ����Ă���Ԃ��瓪��ɍ����}���Ă���̂���h�ł��邱�Ƃ��m�����B
�@�_�X�Ǝc����Ă���s�X�n�̔��̉��ɐ����Ă���G�����A���������Ƃ��Č����ƌ��������قǂ̉Ԃ����Ă���B���Ƃ��C�̓łȖ��O�������u�W���~���A�����Q�̐�ɂ킸���g�F�������n�߂Ă����B���₪�ď����Ȕ����ԂƂȂ�B�тɕ����Ă���̂Ń��u�W���~�i�M���l�j�ƌ����������Ȃ邪�A�Q���Ԃ����ǂ��Ȃ��Ĉ��炵���B
�@�悭�G���ɂ̓C�k���^�k�L���J���X�Ƃ��������O���t�����邪�A�����炭���Ă͂�����̂̐H���Ƃ��Ă͖��ɗ����Ȃ��Ƃ������Ӗ������̂��낤�B���̒��Ԃ̃J���X�m�G���h�E�̉Ԃ����ꂢ���B
�@�J���X�m�G���h�E�ƂƂ��Ɏ��グ����̂��X�Y���m�G���h�E�ł���B�Ƃ��낪������A���傤�ǂ��̒��Ԃ̑傫���łƂĂ����Ă���Ԃ��������B����Ɍ�z����Ă���ȉԂ��炩�����̂��Ǝv�������A�R����ׂĂ݂�Ƃ��ꂼ��͂�����Ƃ����Ⴂ������B�}�ӂׂĂ݂�ƁA����̓J�X�}�O�T�Ƃ���������Ƃ������O�������Ă����B�J���X�ƃX�Y���̒��Ԃ̑傫���Ȃ̂Łu�J�v�Ɓu�X�v�̊ԂŁu�J�X�}�O�T�v�Ƃ����B�Ȃ����������A�Ƃ����C�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�@�J���X�m�G���h�E�͂T�`�V�~���قǂ̍g���F�̉Ԃ��Q�A�R����B�X�Y���m�G���h�E�͂Q�`�R�~���قǂ̒W���F�̉Ԃ��T�A�U�ŁA�J�X�}�O�T�͂R�`�T�~���̐��F�̉Ԃ��Q�A�ɂȂ��č炭�B
�@�������G������ǎG���ŁA���ׂĂ݂�Ɩ��O�̕t������n���̕��@�Ȃǂ��ʔ����B���Ė쌴���щ���Ă����炵���j�ǂ����A���ꂢ�Ȏʐ^��C���X�g����̎G���}�ӂ���������o���Ă���B
�iM�EO�j
��������
�@�����t���A�Ƃ���ɍÂ����̈ē����ʂ��͂����B
�@�������߂ăs�A�m�ɐG��Ă����w���Ƃ܂ł����Ƃ����b�ɂȂ����搶�̃T�����R���T�[�g�B��w�ŕt���Đn�̂����b�ɂȂ������y�̐搶��������O���[�v�ɂ��A�I�y���̃K���R���T�[�g�B�n�ӏ��S������Ƃ����A���Ƃ͎R�{���p�̉�̏��D����̘N�ǂ̉�B�R�̊G�`������Ƃ��Ēm��l���m�钆���D��������̌W�B�������N���O�ɂȂ邪�w��ɐ����钹�����x�Ƃ����ʐ^�W���o��������s�̐E������́A���̗F�l�́g�M�������[�i���I���u���h�J�X�̂��j���ʐ^�W�B���Ԃ����ݏZ�̏\��E���X���v�Ȃ�����ԃA���b�g�ł̃O���[�v�W�BAKIHIKO�̉��͉ĂɍÂ���鉪�����F�ʐ^�W�B�o�ϊw�̐搶����͎v�������Ȃ������g�̎ʐ^�W�̂��m�点���B����ɁA�n���̒j���R�[���X�̃����o�[����O���[�v�����P�O���N�̃\���ƃf���I�̉��t��A�����Ƒ����Ă���Ԃɍ���҂������Ȃ��Ă��܂����Ə����������c������B
�@���ꂼ��ɁA�����̐ςݏグ�Ă������̂����J����@�������A�����̐l�֓�����������ꂽ���Ԃ���ĉ�����B�v���ł͂����Ă��������C�g�̓����镑���ɂ���킯�ł͂Ȃ��A���R�Ȍ��𗁂тĂ̍Â����̂���ɂ��Ă���l�������B���ŏo��ΐe������b���e�݁A�����b�Ȃǂ��������Ƃ��ł��邵�A�Ȃ�Ƃ����Ă��C�y���{���ɐG��邱�Ƃ��ł���̂͂��肪�����B
�@�����̈ē���͖{���ɍׁX�Ƒ����Ă��鉹�M�̎����ŁA�����Y�ꂸ�ɂ��Ă��ꂽ�̂��ƁA�|�X�g������o�����Ƃ��ɂق���ƍK����������B
�@�Ƃ���ŁA����1�N��1�x�̃t���[�g�\�����������B�ł��A�ƂĂ��l�l�ֈē�����o���E�C�͂Ȃ������B
�iM�EO�j
��������
�@��N���ɓߐ{�����ꂩ��~�n�̏����ɂ��ĘA�����������B
�@���d�̕�����P�������̓����A�����ߐ{�����ʂɗ���Ă������߁A�ʑ��n�Ƃ��Ĕ���ꂽ�R�тɂ͑я�Ƀz�b�g�X�|�b�g�����ꂽ�B�אڒn�ɂ͐��A�J��_�ƂƂ��ē��A�������_�Ƃ��Z��ł���B
�@�N�������Č��n�ŋƎ҂Ƃ̑ł����킹�����邱�ƂɂȂ����B���k�����~��Ĕ��͕��ʂɑ���ɏ]���A�Ԃ̒��̐��ʂ������ɏオ���Ă����B�܂��͒�����ɍs���ď����̐��������B����͎����^���قǂ��e���ŁA���˔\����菜���Ƃ������Ƃ͕s�\�A���ɂ��p�t�H�[�}���X�ɉ߂��Ȃ��A�Ƃ����ɔ��f�����B
�@�������ł͐��ʂ��O�D�Q�Rµ�V�[�x���g�^���ȏ�ŕ~�n�̑S�̂�ΏۂƂ��鏜����Ƃ��A���͎s����ԂłP�T���قǂ̂����ł́A�Ȗ،��Ƃ����������Ő��ʂ������ł������̓��e���Ⴄ�B���ɐ��ʂ̍��������͌��ɉ����č��E�T�O�Z���`���ɂP�O�`�R�O�Z���`�̓y������ւ���B�~�n�͗����t�������Ώۂő܂ɋl�߂ĕ~�n���ɖ��݂���A�Ƃ������̂��B���̖��ݏꏊ�����߂�̂������̋Ǝ҂Ƃ̑ł����킹�������B
�@���������ԉ����Ƃ���ɂ������ƒN�����v�����A�����͖������ďd�@�������Ȃ��A���������ł͑S���̑܂߂���Ȃ��ƁA��]�O�]���ċƎ҂ɏ������B�ނ炾���āA�D��ł���d���ł͂Ȃ��͂����B
�@���̌��Ƃ͂ǂ��Ȃ����̂��A���ꂩ��I�������Ƃ����A���͂Ȃ��B
�@���Ȃ݂ɐ������𑪂������ʂ́A�����̒n��O���i�n�ʁj�łR�D�R�`�T�D�Xµ�V�[�x���g�^���A�낪�O�D�T�X�`�P�D�Q�Rµ�V�[�x���g�A���H�����R���̐������܂�ꏊ�ł͂T�D�W�X�Pµ�V�[�x���g�������ꏊ���������B
�@�R�N�̊ԖK��Ă��Ȃ��������A�~�͂�̂���������Ƃ͂����A��т͂��������ꂽ������ۂ߂Ȃ������B
�iM�EO�j
��������
�@���N�̂��Ƃ����A���Ƃ������ɓ͂��Ă��炦����܂łɓ������Ȃ���ƁA���������l�܂����M���M���̎��_�ŔN���������n�߂�B�������Ƃ͂����ؔł��č���̂ŁA���������O�̂ЂƎd��������B�P�Q���ɓ���������ɂ͏o���オ��\�z�}�������ł��Ȃ������ł��Ȃ��ƂЂ˂��Ă݂�̂����A����͂R�N��܂ł��V���[�Y������Ƃ����A�f�U�C���̃G�R����}�����B
�@�o�����̃G�R���Ƃ�������A�����V���ɂ��蔲���Ƃ����Ă��܂�����܂ł����c�@�����邪�A����Ă݂�ƔN���ƂɘV���̘b�肪�����Ă���̂��������B
�@�u�o������n�߂ĂP���Ԃ��炢�A�}�ɍ����瑫�ɂ��тꂪ����S���͂�����Ȃ��Ȃ蔇�������̑̂ʼn��R�����v�Ƃ��A�u�[���œ|��A�����d��������Ɛf�f����Ēf���v�Ƃ��A�u��Ғʂ�����̂̐����v�Ƃ��A�u����Ƃ���Ƒ̗͂��W�O���߂��Ă����v���X�B
�@���ꂪ�N���Ƃ������Ƃł�����B�ߋ���m�点�����A���݂��l���Ƌ���Ď��o�𑣂��B����ł�����͕K���V�������Ƃւ̎Q���Ɗ��҂Ō���Ă���̂��������B
�@�N�̏��߂ɐ����̔��i������e�͏��Ȃ����A�u���Ƃ��O�����悤�v�Ƃ��A�u�`�a�d�̖\�����~�߂�͂͗L���v�Ƃ��A�u����Ă���̂͌��@�ɋ��������I��̂̌`���ł��v���X�A���ӂ𑣂����̂�����B
�@�Ƃ���ł��̔N���A�o��������ʼnƑ��̕����܂߂ĂP�O�O���قǂ��w�������̂����A�A��铹���ŏo��ɒu���Ă��Ă��܂������Ƃ��v���o���n���B���߂Ĕ����������B����ɂ��܂��ĔN�������đ�ʂɎ��ւ���p���������B���̎�Ԃ̖ʓ|�������B
�@�������肵���ƌ����Ȃ���A���͖{���̃{�P�ֈڍs���Ƃ������Ƃ��ƐS�����₩�ł͂Ȃ��B
�iM�EO�j
��������
�@�P�T�V�O�R�P�c�c�Ƃ��Ƃ��P�T���L�������B���s�������ł���B
�@���̊ԃ��J�ɂ͉��̖����Ȃ��A�C����v�����̂͏��������̂ł̓��C�p�[�u���C�h�A�傫���Ă��^�]�Ȃ̑��K���X�̃��[�^�[���炢���낤���B�ȑO�A�o�悩�獂��w�l�𑗂������ɁA�ǂ����H�����̉w�O�œB���E�����悤���������A�Ƃ܂ł̍����������̖����Ȃ�����A�p���N�ɋC�Â����̂͂R���ゾ�����Ƃ������炢�^�t�������B
�@�җ��ڑO�ɂ������A���Ƃǂꂭ�炢�Ԃɏ���̂��낤�A����Ԃ͎Ԃœo�R���܂ōs���������̂��ƁA�Ԍ����@�ɂ���܂ŏ���Ă����s�X�n�����̏�p�Ԃ���SW�c�ɏ�芷�����B
�@�������܂Ŗk�A���v�X�̐���A�㍂�n�̑�n�B�����x�̔��Z�ˌ���ω����B��A���v�X�̖鍳�_���ցA�����A���v�X�̐��̑�ւƁA���ɋC�y���^��ł���������̂��B
�@�������ɂP�T���L������ƊO�ς̐����������Ă���B�h�A�m�u�̃p�b�L���O���{���{���ɂȂ��Ă���B�{���l�b�g�ɂ̓s���z�[����ɓh���̔���������B���N�̂R���ɂ͎Ԍ������A�V�Ԃ��l����^�C�~���O��������Ȃ����A���ꂱ���A���Ɖ��N�����Ƃ��ł���̂��B�N����炵�̐g�ɂ͖��N�̕ی����ێ���͂��Ȃ芬����B
�@�����ōl�����̂��y�����ԁB������A���[�X�ŁB
�@�F�l�̎ԉ�����ɑ��k���ăp���t�����Ȃ��猟�������B���������ƂɃG�R�J�[�Ή��ŏd�ʐł��擾�ł��ƐŁA���̕��̔����i�͂���ƈ�����������B�s�����Ɏ����Ԃ̔���グ���L�т����R�͂����������Ƃ������̂��B�G�R�𐄐i����Ƃ�������Ŋ�Ƃ͗D���[�u������̂��B�����A���̐�ɑ҂��Ă���͍̂������H�̒l�グ�Ɖ������Ȃ��K�\�����ŁA�����Ă���ς�y�̎����Ԑł��グ�悤�Ƃ����ژ_�����B
�iM�EO�j
��������
�@�R���������ΓV�C�͕ς����̂Ǝv���Ă����B�P�T�Ԃ��ς����̂ɂ��܂łR�O�x�ȏ�̓��������̂��ƁA���̉Ă��ւƂւƂɂȂ����B��C�ɋC���������������̑̂̓����̃X���[�Y�Ȃ��Ƃƌ�������B�������������Ő��_�I�ɂ����̓I�ɂ���������_���ɂȂ��Ă������Ƃɋ������B
�@���a�U�Q�N�i�P�X�W�V�j�ɏo�ł����w���s�@���V�C�Ύ��L�x�Ƃ����{��ǂݕԂ�����u���߂Ɂv�Ƃ����Ƃ���Łg�������\�N�A�܂荡���I�����ς��́A���{�̕��ϋC���͂������Ə㏸���A�n��ɂ��A�ɒ[�ȓV����邱�Ƃ��\�z����A�N�X�̓V��͕ϓ����傫���A�ُ�C�ۂ��������₷���h�Ɓu�ُ�C�ۃ��|�[�g�W�S�v�i�C�ے��j���q�ׂĂ���Ə����Ă���B����ɁA�Љ�̓V��ɑ���Ǝ㐫�͑��傷��Ƃ����̂����O�̋C����Ƃ̑���̌����ł��A�ƕM�҂������Ă����B
�@���s���ꂽ�N���猩��ƍ����I�Ƃ����̂͂Q�O�O�O�N�܂ŁA���N�͂Q�O�P�R�N�łQ�U�N�ڂƂȂ邪�A�{���ɂ��̒ʂ�ɂȂ��Ă���B����̈ɓ��哇�̓y������Ɂw�ΎR�D�n�x���v���N�������B�ߋ��ɂ�������ЊQ�̗l�q�͋L�^�⏬���≉���ɂ����Ȃ��čJ�Ԃɓ`�����Ă���̂ɁA���{�͎����̋C�ے������\���郌�|�[�g�ɖڂ�ʂ��đł���l���Ă����Ȃ��̂��낤���B����Ƃ��A���������ЊQ�͐푈�Ɠ������炢�o�ϕ����̎�i�ƂȂ�Ǝ�����܂˂��Ă���̂��낤���B
�@��J�ŗ����ꂽ���A�n�k�ŕ��ꂽ�ƁX�A�Ôg�Ɉ��܂ꂽ���A�����ɔ���ꂽ�����A�Ȃ�Ƃ����Ă������̎��������������Ȃ������B�R���Ɏ~�߂悤���Ȃ��\�Z�𒍂����ޗ]�T���ǂ��ɂ���Ƃ����̂��낤�B
�@�����Ȃ�g�t�O����ǂ��ڂ̑O�ɁA�閧�ی�@���o���B�������u���{�����͍����̍ō����茠�����匠�҂ł���v���Ƃ����߂Ď��o���A�푈�֓����J�����Ƃ��鐨�͂ɑR���ĔR���オ�鎞�Ȃ̂��B
�iM�EO�j
��������
�@�c�Ɉ炿�ŁA�p�c�ŁA���������̖L���Ȋ����͔ޏ��̑��݂�j�݂ɋC�Â�����ɂ͂��܂肠��}�`���_�ƁA���ƂȂ��c�ɖ��̃T�N�Z�X�E�X�g�[���[�̂悤�ȕ\�肾���A���₢��A����̓W���K�C���̘b�B
�@���Ⴓ��Ƃ����B�ꋼ����������B�{�E�͑�H�����A��������Ď���ɗאڂ���X���\���Ă��܂����B
�@�����͐M�B���̓�E���B�ł����ẴR�V�͂Ȃ��Ȃ��ŁA���ꂾ���Ŗ�������̂����A�����ĂȂ������ƂȂ�Ƃ܂��͘Z�̑O�����ԁB���厩�炪�A����͂��сA����͂����݁A���ꂪ�����Ԃ��ȂǂƁA���̂��ė������̂ǂ��ɍs���Ό������邾�́A���̐����͎��Ɋ����������B�Ȃ��ł���Ԃ̓��ӂ͕��������̌{�̗L�����̌��Ă��������B���ɏo�����̂͋������̏`���B������G�߂ɂ���ĈႤ�����ŁA�H�Ƃ��Ȃ���o�̒��͑��ł����ς����B
�@�u���̂Ƃ���~�葱�����J���~��o�邾�낤�Ǝv���āA���傤�Ǎ���̂�ɍs�����̂�B�����͂��傤���Ŏd���ĂĂ݂����ǁA�ǂ��H�v�ƁA������܂������������B���ꂩ��V�Ղ炪�o��B����������Ɛ��̖��R�ŁA�܂苼�����͂��߂��ׂĐH�ނ͎��O�Ƃ������Ƃ��B�����ɋ������o�����̂����A���ւ�͎��R�A�����ꖇ�ǂ��H�Ɗ��߂��Ă������͂������Ȃ��ɂ͓���܂���A�ƂȂ�B�f�U�[�g�͌I�̏a��ςƋ����̊��V�[���[�B���Ă���v�ɂ��āi����ň�l�O�P�T�O�O�~�j�A�낤�Ƃ�����A�����炲�������ƂȂɂ��������Ă����B
�@�u�}�`���_�A����H�ׂĂ݂āB�����Ɏς��邩��֗�����B�ł��j�݂��D���Ȑl�̌��ɂ͂ǂ����ȁA�|�e�g�`�b�v�ɂ͂����B�A������������������B���A�ȂɁA�j�݂��D���Ȃ̂��A�_�������v
�@�}�`���_�͒W���ŁA�W���K�C���A�Ƃ������̖������Ȃ������B
�iM�EO�j
��������
�@�u�G��v�Ƒ肷��c�P�P�Z���`�A���P�S�Z���`�قǂ̔ʼn����ɓ��ꂽ�B�G�`������̃A�g���G�Ō�������A�G��̃`���[�u�≽��炪�G���ɓ]�����Ă���P�J�b�g�ł���B��҂͏\��̊삳��B�����m�̕��������Ǝv���B
�@���N�O�ɁA���̌W�ł��̔ʼn���ς��Ƃ��A�ӂƕ��̕����̖��G�̋�̂ɂ������v���o�����B�������܂�̕��͎������̂ł͂Ȃ��������G��`���Ă��āA�u��x�ł�������A���܂��悤�ȊG��`�������Ȃ��v�ƌ����ď��Ă����B
�@�ӂ����قǑO�ɂȂ邪�A���Z�ōÂ��ꂽ�\�ꂳ��̌W�ł��̍�i�ɍĉ���B�~�����Ǝv�����B���A�ǂ����ʼn�̎��ɉ��V�~������C�ɂȂ�B���{�l�Ɂu���̔ł͂�����ɂ���܂����v�Ȃǂƕs�^�Ȏ�������āA���߂č���Ȃ��������̂��w�����邱�Ƃɂ����B
�@�o���オ�����Ƃ����̂ł��������ɏo�����ƁA���͑O�̔ł������Ă݂��Ƃ���A�o�W���Ă�����i�Ƃ͈���Ă����Ƃ����B�Ȃ����ł̈ꕔ������������炵���A����オ�����G�̂��̕����͋������������B�����ł�����x�V�����ł����Ȃ��������̂́A���x�͒����������ׂ������B����ł͂Ȃ��Ƃ���ɂ�����x�A�ʂ̐n�Œ������̂����̍�i���ƁA���ꂼ��O�̔ł܂ł������[�������Ă����������B
�@�Ƃ���ʼnߓ��A���̏��I�̌Â��{�����Ă�����A�{�̊Ԃɋ��܂ꂽ�t�����������B�t���ɂ͂e����̎��Łu�B���v�Ƃ���A�g�n���i���̂��Ɓj�́u�l�ʂ�v���̖�ƂȂ�A�Q���~�͂e����̍ρB��]���ꂽ���͋ߏ��̐l�Ƃ̂��ƂŁA�F���^�����Ă��������h�Ƃ������B�P�X�V�W�N�̏H�A����U���ڂ́u���p�T�����͂܂̂�v�ōÂ��ꂽ��P�U�����S����W�̈ē��͂����������B
�iM�EO�j
��������
�@�v���Ԃ�ɏ���ɖ߂��Ă������쌧�ݏZ�̗F�l�ƐH�����̘b�������B
�@�ނ̂��鑺�͐l���R�O�O�O�l�ŁA�������ɂ��ꂸ�A�قƂ�ǂ�����҂��Ƃ����B���̏t�A���́u�����̂��Ղ�v�̃O���[�v�ɏ�������אl����A�M���������̂ō̂��ė�����⡂������������������B⡂͑����Ă����a���T�Z���`�قǂ̃n�`�N�i�W�|�j�Ƃ����|�ł���B
�@���N�u�����̂��Ղ�v���s���A�w�肳�ꂽ���ɂ͒|�M�ɓ����č̂邱�Ƃ��ł���B�I�c�ŕč������鑺�Ȃ̂Œ|�M���}�ΖʂȂ̂ɁA�����ō̂�̂��y�����Ə�A����̎Ԃ��}�����炦�̒��ԏ�ɕ��ԂƂ����B
�@������ԂłR�O���قǑ���A����s��咬�s�̑�^�X�[�p�[�Ŕ������͂ł���̂����A�Ȃɂ��u����̓Z�J���h�ȏ�ɓ���đ��������Ƃ��Ȃ��v�Ȃ�Ă�������҂��Ԃ��^�]���Ă���B�H�ו��͑����ɔ����ɍs���̂ł͂Ȃ��A���ō����̈ȊO�ɂ��t�̎R�A�H�̑��ȂǁA���O��������O�Ƃ��������������Ƒ����Ă��āA�{�𖡂������͕ۑ��H�Ƃ��Ē�������B�ƌ����Ă������͌���A�ۑ��ɂ͊F����Ⓚ�ɂ����p���Ă���Ƃ����B
�@���ɂ́g�n���̓��h���܂����邵�A�l���W�܂�@��͏��Ȃ��Ȃ��B�W�܂���y�����o��B���X�h���������Ȃ�悤�ȔZ���ݖ��F�������ϕ��̒��ɋG�ߊO��̃^�P�m�R���o�Ă�����A���ł��R�I�̂����킪�ӂ�܂�ꂽ��A����Ēu���́i�Ƃ������A�c���Ă����Ƃ����̂��j�������ޗ����g�����H�ו������ɕ��ׂ���B
�@���ł��ނ��������̂͂���p���̓V�Ղ�B�ނ̂��Ƃ����牓���Ȃ��傫�Ȑ��Ō������������B�u�Ȃ��ɂ����[��[�I�v�B�悭����Ƃ���p�������ł͂Ȃ��A�����߂̂ǂ�Ă��̓V�Ղ��H�p���̓V�Ղ�܂ł�����B�u���̂�����ł͂��������v�ƌ����āA�ނ͂����H�́u�����v�Ƃ����̂��낤���Ɠ���������������B
�iM�EO�j
��������
�@�����Ԃ�O�ɂȂ邪�A��l�ŏ��߂Ĕ��n�ɃX�L�[�ɍs�����B�R�������Ĕ��n�ܗ��̃X�L�[������܂Ȃ��A����A��ǂ����Ă��h���������Ԃ��炯�̋}�ΖʁA�G�L�X�p�[�g�R�[�X�������Ă̘b�����A�������B
�@�h����͐V���̍L���������Ă������s�b�N�A�b�v���Ă���l�b�g�Ō������A�u��l�ł����}�v�Ƃ������_��̃y���V���������ƂɌ��߂��B���Ȃ܂�̂���I�[�i�[�͎��Ɠ����N�ŁA�E�T�������ăy���V�������I�[�v�������Ƃ����B�ȗ��A���N�̂悤�ɂ����b�ɂȂ��Ă������̃y���V�������A�T���Q�T���ɂQ�T���N���}�����B
�@���̏t�h�����ꂽ�j����ƃI�[�i�[���A��l�Ƃ����m�s�s�Ζ��Ƃ������Ƃ�������A�j����͓����Ζ��ŃI�[�i�[�͑��Ζ��ƁA�����͈Ⴄ���̂̓�����l�ŁA���������A���a�i�x�g�i���푈�E���ہj�A��Ђ��p�g�����炲���J�Ȃ鈵���H�H�������ƁA�Ȃǂ����ʂ���Ə��������������B����������͂Q�T�N�A����Ȃ�L�O�p�[�e�B�[���ƁA�j����̐l���ŐV�h�Ƃ����т̃��M����𒆐S�Ƃ���o�O�̐��i���ł��j���̌𗬉��悳�ꂽ�B
�@�����̓}���V�����̑���̂��߂ɋ삯���邱�Ƃ��o�����A�j�d��ł����ł����������C�������������A������烁�[���ł��̓��̗l�q��m�点�Ă��ꂽ�B
�@�Q���҉��ׂP�P�O���A�h���҉��ׂX�U���B�������I�[�i�[�͒n��̃y���V�����Ƃ̂Ȃ����厖�ɂ��Ă���̂ŁA�ߗׂɏh�����˗����A�E�G�ɂ͋v���Ԃ�ɓ��₩�Ȃ��q�̐������������Ƃ��낤�B�ӊO�ɂ�����R�̂��������O���[�v�A�Q�P�����Q�������������B������ɍs���Ă�����m���Ă����ɏo������A�Ǝc�O���B
�@���̉�ł��A���n���ӂ̊ό���n�C�L���O�Ȃǂ���悵�A�y���V���������Ƃɏh���ł���Ƃ����Ȃ��E�E�E�B
�iM�EO�j
��������
�@�u���ۂɐ��̒��ŋN�����Ă��邱�ƂƁA���@�ɏ����Ă��邱�Ƃɍ����o�Ă��Ă���B���@�͏��F�G���炲�Ƃ��A�ƂȂ��Ă���ق����A��قǕs�������v??�@���ꂪ���@�����`�����ۂ���ꂽ��b�̌��t���I�@�U���Q���̂m�g�j���j���_�ł̐Δj�Ύ����}�������̔������B�܂������䖝�Ȃ�Ȃ��B���������A����͌��@�ɑ��镎�J�ł��薼�_�ʑ��ł���A���{�����͂��Ƃ�萢�E�̐l�X�ւ̔w���ł���A�e�N���ׂ��\���ɂ��������̂ł͂Ȃ����낤���A�ƁA����͎̂�����ł͂Ȃ��Ǝv���B
�@�����̓s�c�I�̌��ʂɂ��Đ��c�J�Ŋ撣�����o�ɓd�b����ꂽ�B�ł��邩����̂��Ƃ����Ċ撣�����Ƃ������Ƃ����A�ǂ��撣�����̂��B
�@�������������A�݂�ȍ���҂ƂȂ��Ċ撣��悤����������̂́A�����h�̐l�������{���ɑ_���Ă���̂͂ǂ��������ƂȂ̂��A����������Ă��܂����Ƃ��ǂ����������������炷�̂��A�Ƃ������Ƃ���������Ƒi����r����吨�ʼn�����w���ŎT������A�e�˂̃|�X�g�֓��ꂽ�肵���Ƃ����B�u�^�������`������̂�����B���̓����ł�?�A���������������ˁv�ƌ����Ă����B
�@���@�͏��F�G���炲�Ƃ��A�ȂǂƐl�X�̌��ɏス�����Δj���̂����ӂ̗U���q��ɏ�炸�A���ꂱ�������ɑ��邻�̕s�������ɂ́A������Ǝ��炾�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̗��s�Ƃ����悤�Ȍy���ŏ��Ă��ނ��̂ł͂Ȃ��B�����������ɁA�����̈Ӗ�����Ƃ����^���ɖ₢�Ȃ����Ă䂭���Ƃ͑厖���Ǝv���B
�@�s���Ƃ��Đ��_�����鎄�����͖ق��Ă��Ă͂����Ȃ��B���E�I�Ȍo�ς̗������݂��ЊQ����̕������A�������铹�͌����Đ푈�ւ̓��ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ���˒[��c�ł��b��ɂ��āA���_�����߂Ȃ���B
�iM�EO�j
��������
�@���N�S���̑�P�y�j���͂��Ԍ��ƌ��߂āA����l�͋��܂��ƃI�[�v���E�n�E�X�̂P����݂��Ă���F�l������B���Ԃ̓�ʂ͖^�������̍L���~�n�ō��̉����B���łɉԂ͏I���r�V����ꂽ���̓��A�d�Ԃ����p���ŏo�������B
�@���{�l�����{�l�����ɏW�܂�l�͕����l���n�ߔo�D��|�\�W�҂������B�Ζ��炳��̌��Ɏ�������ďΊ�������鎞�}����̃X�i�b�v�ʐ^�����āu���A�S���Ȃ����́B�N�������Ă���Ȃ������I�v�Ƃy���B����ȉ�b�����ʂȂ̂��B���A���̂悤�ɏ��Ζʂ̎҂ł��b���ɉ����镵�͋C�́A�������ɐ������ꂽ�ނ�ł���B
�@�����h���Ō����������t�J�f�B�I�E�n�[���̎ŋ�������̎ŋ��̘b�ɂȂ����B���̎ŋ����������l�̘b����A�o��̘b�ֈڂ����B��N���}����ɓ������āA���Ă��������o��̐��E�ɐg��u�����Ƃɂ����Ƃ����u�ӂ��������I�v�Ȃǂ̌��f�B���N�^�[�`���A�o�D�̂y���A���̎O�l�B��i�������̎M�������Ȃ��Ȃ肾���ԃA���R�[��������Ă���B
�@�����ɟ��́u俒��ȏ��������̂ɐ��܂ꂽ���v���o�Ă����B�`�����킭�A����͎q�K���u�ӂ邳�Ƃɏ�����係˂Â�����v�Ɵ��̋A���ɍۂ��ĉr���̂̕Ԃ����A�ƁB�E�\���A�Ǝ��͌���Ȃ������B�q�K�͟��̋A����҂����ɖS���Ȃ��Ă���B
�@����������g�́w���E�q�K�������ȏW�x���I���̂ق�����ǂ�ł݂����A�q�K����̎莆�́u�l�n���[�_���j�i�b�e�V�}�b�^�v�ŗL���Ȃ��ꂪ�Ō�ŁA�����R�T�N�P�P���B�����ɋ�Ȃǂ͖����B���́u係قǂȁv�͖����R�O�N�Q���A�F�{���瑗��ꂽ�S�O��̒��ɂ���B�f�B���N�^�[���A�ǂ�������������Ă����̂��A�o�����m�肽���Ȃ��B
�@����ɂ��Ă��A���Ǝq�K�̏��Ȃ͖ʔ����B���̂悢����̂悤���B
�iM�EO�j
��������
�@�Z�{�̍����V���p�قő�U�U����{�A���f�p���_���W�����Ă����B�P�K�̂S�������g���āA�P�P�O�O�_����i���Q�W�̃R�[�i�[�ɕ�����ď����Ă���B�r���ō��|���邱�Ƃ��Ȃ��A�ЂƂƂ��茩�I����̂ɂR���Ԉȏォ�������̂ł͂Ȃ����낤���B��ꂽ�B���A�\���Ɋy���܂��Ă�������B
�@�A���f�p���_���W�́A�P�W�W�S�N�Ƀt�����X�̃p���Œa�������W����ł���B�h�����������������������͉p��̃C���f�y���f���g�i�Ɨ�����?�j�̈Ӗ��ŁA���̎�|�͖��R������܁E���R�o�i�B���̌��́A��d���h�Ȃǂ̐F�ዾ�Ȃǂɍ��E���ꂸ�A�����̕\�����������̂������̗��V�Ő��삵�Ď������ށA�Ƃ����`���B
�@���{�ł͂P�X�S�V�N�ɁA�t�����X�ł̐��_���p���ő�P����J�Â��A���������Ēa���������{�����@�̗��O����̊�{�ɐ����āA�����܂ő������Ă���B���R�A�u�\���̎��R�v�͉\�Ȃ�����u�W���v�����̂ŁA�Ƃ��ɂ́u�H�v�ƌ����������Ƃɂ��Ȃ�A���鑤�͂����ō�ƂƖ����̂��Ƃ������B���̂����i�A�����Ă����i������B
�@�Ȃ�ƕ\���̕��́A���邢�͉��s���̍L���[�����Ƃ��B���������������琳�������߂���̂̌��������Ă��邱�ƂɋC�Â����ꂽ��A�^���͂������Ƃ�����邱�ƂƂ͌���Ȃ��ƒm�炳�ꂽ�肷��B�ǂ̃R�[�i�[�ł������ꂼ��ɐ���҂̑��݊����������B
�@���N���W������Ă����^�����Ń{���{���̓S��p������i�Q�A�e�������킦�������ɑ��̎w���������u�������镺�m�v�Ȃǂ̑O�ł́A�푈�̃��A�����ɑ����̂ݑ����~�܂�B����ŋ��F�̒����A���ǂ��Ȃ������ƃu�i�̐X�ɒ����V�ԁu��������̂悤�Ɂv�i����������i�������j�̍�i�j�̑O�ł́A�ق��Ƒ����͂��đ����~�߂��B
�iM�EO�j
��������
�@���l�̑�V���z�[��������ɂ́A���ꂼ��y����������V��j�������ւ̗������Ă����B�o���h���ԂƁA�F�����ƁA���邢�͐e�q�ŁA�N��̊_������艺��̊_�����Ȃ��u���X�̃C�x���g�ł���B�₽�����ɋ݂��������ĂĎ�t��҂N�̊�ɂ��A�����̂Ȃ��݂����ӂ�Ă����B
�@�x�܂��Ȃ���g�����y�b�g�𐁂��n�߂������A���̊_���̂Ȃ�������ɂ��̌����������ƗU���Ă��ꂽ�̂ŁA�u�����ɂ��v���̌��ɋy�B
�@��t���ς܂��A�����̊y��̃p�[�g�����W�߂�B�Ȃ�ƂW�Ȃ�����B���Ɋo���̂���Ȃ̓��f�b�L�[�s�i�ȁA�n���[�h���[�A���グ�Ă�����̐����A�̂R�Ȃ������B�P�Q��������S���܂ŁA�Q��̋x�e������Ń��n�[�T�����������B
�@�܂��̓��f�b�L�[�s�i�Ȃ���n�߂�B�]����Ƃ������a��̂��钘���Ȏ��w���҂��^�N�g�����낷�ƁA�`���̃^�^�^�A�^�^�^�A�^�b�^�b�^�^�[���A�^���^���^���^���^�̃����f�B�[�����������Ŏn�܂����B���₠�A��������o�Ȃ��I�@������������͒N�������Ă���Ȃ��B�u��������Ȃ��̐��E�v�A�u���X�E�o���h���͑̈��n�Ƃ����鏊�Ȃ��B
�@���w�Z�̐��t�y���Œ�ԂƂ�����T���o�u�v�A�e���r�ł�����́u�x���{�����v����u��@�ꔯ�v�A�����{��k�Ђ��琶�܂ꂽ�u�Ԃ͍炭�v�ȂǂƁA�W���[�N���������M�d�ȃR�����g�����炢�Ȃ�����K�������B�U�O�O�l�̊NJy��ƑŊy��̉��̔��͂́A�����A�Ȃ�ƌ��������B���n�[�T�������Ŕ�ꂫ���Ă��܂����B
�@���̌�ł����Ɩ{�Ԃ��������B���ʂƂ��āA�S�̂̂P��������Ƃ͏�ꂽ���낤���B�����̖ڗ������N�̒j���������A�y�������Ă��������Ɖ��t���Ă���p�͍D�����������B�F����A���ɏ�肢�B
�@�����푈�̂Ȃ������V�O�N�߂��̎���������ƈʒu�Â���̂͑��v��������Ȃ����A���y�����Ȃ��Ɋy���߂���A�܂蕽�a���A�����������Ƃ������Ǝv��������������B
�iM�EO�j
��������
�g�b�v�y�[�W��