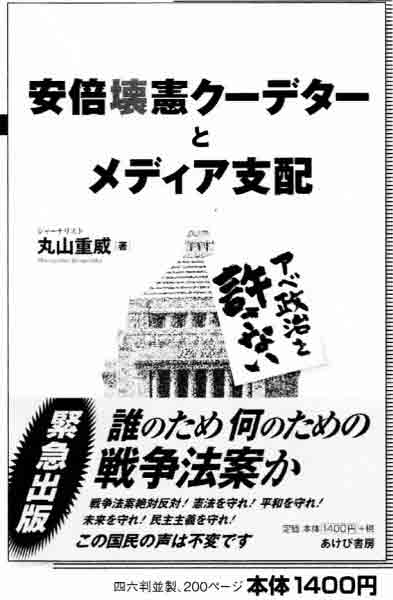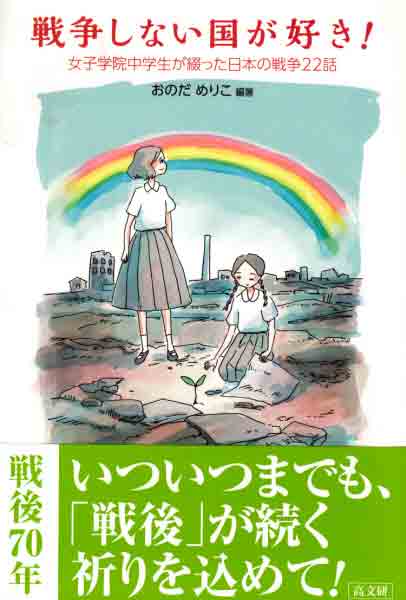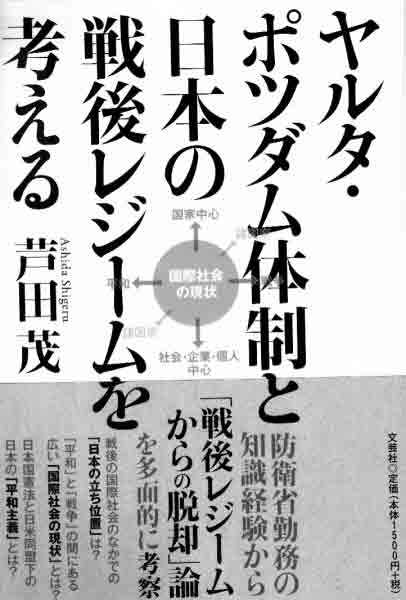機関紙114号 (2015年9月28日発行)
ジャーナリズムの自殺行為 12万人大集会がたった35行
梅田正己(書籍編集者)
2015年8月30日の安保法案に反対する大民衆行動を、朝日と毎日は、1面の左半分と社会面のあらかたを便って報道した。東京新聞は、1、2、3面と社会面、最終面の全部を使って報道した。3紙の1面の見出しはいずれも当日の行動が画期的だったことを伝えていた。「安保法案反対最大デモ----国会前に集結 全国各地でも」(朝日)「安保法案反対の波----全国300カ所で集会・デモ」(毎日)「届かぬ民意危機感結集----8・30安保法案反対、全国300カ所で」(東京)
では、読売はどうだったか。1面にも2、3面にも、社会面にも記事はなかった。やっと第二社会面に記事を見つけた。写真2枚と35行の記事だった。しかも見出しは上の3紙とは質的に違っていた。「安保法案『反対』『賛成』デモ---土日の国会周辺や新宿」そして写真も、30日の国会前の集会の写真の下に、29日の新宿での「安保賛成」デモの2枚が掲載されていたのだった。記事もまた、反対デモに参加した女性の声のあとに、土曜の新宿の賛成派のデモに参加した女性の話---「法案の中身を正しく知らないで反対している人が多い。今のままでは国を十分に守れない」というのが活字にされていた。
記事は、国会周辺のデモ参加者は、「主催者発表で12万人」と伝え、一方、新宿区内のデモは「主催者発表で500人」と伝えている。12万人と500人。240対1を、読売記事はほぼ対等にあつかっているのである。これを「公平の原則」というのだろうか。
日経もまた、社会面の左端、中ほどに、写真と32行の記事ですましていた。さすがに「賛成」派の記事は載せていなかった。
報道の社会的役割と責任の第一は、事件・事態の生起した事実そのものを伝えることである。それをどう伝えるかが第二の仕事となるが、とにかく事実が起こったことを伝えないことには何も始まらない。したがって、目の前で重大な事態が生じていることが分かっているのに、それを報じないということは、報道機関としての任務と責任を放棄したことにほかならない。
大行動の翌31日のテレビ朝日・報道ステーションは、ドイツの公共放送もイギリスのBBCも30日の大民衆行動を大きく報じたことを伝えた。続くTBSのニュース23は、韓国の全国紙各紙がやはり大きく報道したことを伝えた。アメリカの通信社も伝えていた。
今回の読売と日経の記事のあつかいは、事態そのものの重大さから見て、ほとんど「黙殺」したに等しい。
読売の読者には伝えない
読売は国内随一の購読部数を誇る。購読している世帯のほとんどは読売−紙だけしか購読していないはずである。したがって、読売だけからニュースを得ている人のほとんどは、国内の各紙はもとより、海外のメディアさえこれほど大きく報道した事実を知らぬまま終わったのではないか。
国内各紙と海外メディアが、今回の大民衆行動を画期的な事態として報道したのは、それが日本の民主主義と平和主義の民衆的基盤が幅広く存在することを証明して見せたからにほかならない。つまり、日本の民主主義が健在であることを、目の当たりに示したからにほかならない。
しかし、読売は(また日経も)この歴史的ともいえる事実をほとんど「黙殺」した。とくに一般紙である読売は、いまや日本の民衆行動に敵対するメディアであることを、公然と示したと言わざるを得ない。つまり、民主主義に敵対する新聞ということである。
(2015年9月1日記)
もくじへ
まだ最高裁がある、法律家の良心に期待
林 茂雄(名古屋外語大名誉教授)
集団的自衛権の行使容認を中核とする安全保障関連法が9月19日未明に成立した。
全国に沸き起こる『反対』の声を無視した安倍政権の暴挙だが、第九条に象徴される『平和憲法』が最終的に崩壊したわけではない。違憲立法審査権を持つ最高裁判所の15人の最高裁判事の判断に委ねるのが法治国家の在り方だろう。
問題は米国の最高裁が持つ法案成立時の違憲審査権が日本の最高裁にないことだ。何か具体的な告訴案件が上告されて初めて審査を開始するからだ。
今回、1959年の『砂川判決』(米軍駐留は合憲)が『安保関連法は合憲』の論拠に持ち出されたのも最高裁の安保法令審査の少なさが一原因ではないか。
今までの自衛隊の海外派遣に伴う特別措置法(特措法)にも違憲性の強い法律があるが、最高裁が審査したとは聞いていない。
私は法律の専門家ではないので、どうすれば今回成立した「安保関連法」を出来る限り速やかに最高裁に審査させる方策は思い至らない。多分、近い将来に同法が違憲立法かどうかを求める提訴が法曹界からあると思う。
そうなれば『安保関連法は違憲』の判決を勝ちとる可能性は高い。あれほど多くの憲法学者、元最高裁判事、弁護士、政治家が『違憲』と断じた法案だ。衆院の公聴会で自民党推薦の参考人まで『違憲』とした。15人の最高裁判事が『違憲・同法律は無効』の判決をくだす可能性は大きい。最高裁判事の法律家としての良心と職業倫理に期待したい。
日本国憲法第九条の『不戦条項』は1945年の連合国軍総司令部(GHQ)による占領時に、軍司令官マッカサー元帥の「新憲法三原則」(天皇象徴・主権在民、戦争放棄と戦力不保持、封建制度の破棄)に基づいて規定された。
私は1995年にGHQの日本国新憲法起草委員長のチャールス・ケーディス陸軍大佐(当時・民生局次長=故人)から直接聞いたのだが、草案を読んだ元帥は「第九条を第一条にせよ」と言い出して起草班を困惑させたと言う。
「それくらい元帥は戦争放棄に拘った。平和を希求する時代の雰囲気でもありました。生涯を戦争に生きた元帥は、戦争の愚劣さに嫌気を覚えていたのでしよう。」
結局、大佐は法律家(徴兵前は弁護士)の立場から、「新憲法は形式的には明治憲法の改定であり、どの国でも憲法は国家の体制から始まる」と説得、元帥の思いは憲法前文に書き込んだと言う。大佐は続けた。
「起草班全員がこの新憲法は日本占領が終わった時には、日本側で即時に改訂されると考えていた。それが今も残っているのは、この憲法に時代を先取りした普遍性があったのでしょう。私は理想の憲法の起草に関わったことを誇りに思います」。
現憲法は形の上では確かに占領軍による押し付け憲法である。しかし、内容は世界に誇れる民主的な立憲主義の平和憲法である。夢想を承知で言えば、世界全部の国が九条のような不戦条項を自国の憲法に明記して順守すれば、確実に平和は維持されるはずである。
卑劣極まる“禁じ手”
こうした制定当時のいきさつを知った上で憲法を読めば、安保関連法の集団的自衛権が憲法違反であることは容易に読みとれるだろう。それにしても、閣内で立法の違憲性を審査する内閣法制局長宮を抱き込んでの『解釈改憲』は卑劣極まる。政治家の“禁じ手”だ。「無理が通れば道理引っ込む」とはこのことだ。かつての自民党議員には戦争の愚かさと空しさを知る良識派が存在した。
平和憲法が決して越えてはいけない則を知っていた。「自由と民主」を党名に冠した政党が、国家公務員の憲法順守義務(九九条)を自ら破る首相を無投票で総裁に再選するとは残念でならない。
(元東京新聞ワシントン総局長)
もくじへ
丸山重威(元共同通信編集局デスク)
「私」が見当たらない
「賛成議員は落選させよう!」「安倍は辞めろ」---。安保法案(戦争法案)が強行可決された国会前で開かれていた「シールズ」の集会では、雨の中でこんなコールが繰り返された。むかし風の「シュプレヒコール!」「オー」「安倍内閣は、退陣せよー」というリズムとは違って、「賛成議員は、落選させよう!」「賛成議員は、落選させよう!」と繰り返す。「裸の王様、誰だ?」に「アベだ!」、「民主主義って何だ?」に「これだ!」と答える新しいリズム。「シールズ」とは「自由と民主主義のための学生緊急行動「Students Emergency Action for liberal Democracy’s」は5月に誕生した若者の組織だ。
賛成議員の落選運動も
だまし討ちに近く、「強行」とも言えない、ほとんど無効の委員会採決、野党の表現の自由を奪う発言時間制限を決めた中での本会議採決を経て成立した戦争法に、反対運動を進めてきた側からは、「戦争法制を発動させずに廃止に追い込む」という声明が相次いで出されている中で、「賛成議員を落選させよう!」は、重要な提起だ。
問題はこれからどうするか。来年の参院選を当面のターケットにした共同の継続が語られ、違憲訴訟の可能性も追求されているが、どれも現状では「決め手」に欠けるだけに、これからの運動と政党の動きにかかっている。
廃止に向け多様な模索
「戦争法」廃止については、一致する勢力が国会で多数を占めることが必須の条件。しかし、国政選挙で政党がまとまることは容易ではない。しかし、安保法反対の「一点共闘」がここまで広がったことは、今までにないことで、いろんな可能性が模索されている。
「生活の党」の小沢一郎氏は、6月に民主、維新などに「共産党を除く複数の政党で政治団体を設立し、比例統一候補を擁立する」と提案したが、共産党は19日の中央委員会総会で「戦争法廃止、立憲主義を取り戻す」の一点での選挙協力と「国民連合政府」の結成を呼び掛けた。
これについて民主党の岡田克也代表は20日、「思い切った提案でかなり注目している」と述べている。政党間で具体的な協議が始まれば、「どうしたらいいか」と悩む運動が勇気づけられることは確実。「賛成議員は落選させよう」の具体的な声と政党の統一の努力が、いまから大衆的に議論され、参院選まで続いて、国民連合政府が実現すれば、本当に平和国家・日本への新しい展望を開くことが出来るだろう。そしてそのためには、もういちど、草の根からの「戦争法反対」を広げていかなければならないのではないだろうか。
運動側の位置づけと態勢
違憲訴訟については、少なくともいまの裁判では、「被害」の事実、実態があり、その中で裁判所が救済の必要性を認めなければ勝てない。海外への派遺命令を受けた自衛隊員が、赴任を拒否して処分を受けるなど、具体的な事件がない限り、訴訟を起こしても裁判所に「却下」される可能性が高い。イラク訴訟のように、請求を棄却しながら、傍論で違憲を認めるという判決まで持って行ける可能性は極めて小さく、違憲訴訟が「主役」になるには、運動側の位置づけと態勢がどうしても必要になる。選挙も訴訟も、いずれも「決め手」に欠ける。そこでは結局、世論がどこまで持続的に声を上げていくかが勝負になる。「反対だ」「違憲だ」と言い続ける。安倍政権の反民主主義、反立憲主義、反知性主義の姿勢を一層明らかする報道が続く。そこで、政権打倒と統一政府への共同の声が広がる。それできるかが「闘いの焦点」だ。(メディア研究家)
もくじへ

もくじへ
フランスのアニメ映画
鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)
渋谷のシアター・イメージフォーラムで上映されたフランス製作のアニメ映画「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」を見た。くまのおじさんとねずみの女の子の交流が、心を豊かにさせてくれる傑作。美しい水彩画の背景とともに描かれた愉快な冒険の物語は親と子どもがともに楽しめる。「戦争法」など無用である。
ベルギーの絵本作家ガブリエル・ヴァンサンの代表作「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」シリーズの待望の映画化。
映画は地下にあるねずみの国の教えからはじまる。子ねずみのセレスティーヌは地上にあこがれていて、ひとりで反発する。一方、地上のくまの国に住む音楽家のアーネストは腹をすかしている。ずんぐりむっくりなくまとかわいいねずみの女の子、会うことのなかった二人が出合ったことから、奇妙な交流がはじまる。
腹いっぱいにケーキを盗み食いをするアーネスト、歯医者から歯を盗むセレスティーヌ、それぞれに助け合って、危機一髪、難を逃れる。
ねずみ社会の機械操作などは幾何学的な構造だ。ねずみ警察の大群がおそってくるシーンや山の上から車が逆走していくシーンなどは迫力満点であった。
日本語の吹き替えはアーネスト・玉野井直樹、セレスティーヌ・宇山玲加。ともに適役、味わいのある表現を感じさせた。監督はバンジヤマン.レサールほか。第86回アカデミー賞長編アニメ候補作。80分。今後も単館上映の予定あり。
もくじへ
原田みき子

9月14日は、翁長沖縄県知事が前知事の埋立て承認を取り消す意向を表明した歴史的な日である。この日も国の工事車両がゲートに入ることが予想された。前夜の泊り込み組も加え200人が集まった。この写真は知事の記者会見の3時間前、午前7時頃の光景である。国から何度も裏切られ続けているため、知事の承認取り消し表明の日でも工事車両が入るだろうと予測し、多くの市民が駆けつけた。マスコミも普段の3倍以上いた。その数に思いとどまったのか、「知事表明の日はさすがにまずい。県民感情を逆撫でする」と考えたのか、とうとうこの日工事車両の進入はなかった。
しかし、外からは見えない基地内の浜辺では浮桟橋の設置作業が進められたし、知事の「埋立て承認取り消し」の表明に、安倍首相も菅官房長官も「知事の発表は長い間の負担軽減・危険性除去という県民の願いを無視するもので残念」とコメントした。県民の願いは「普天間の即時撤去」であり「新基地建設断念」であることを知りながら盗人猛々しい言葉である。県民が全基地撤去に向けて心を固めつつあるこどを知らせねばならない。
写真右端の帽子をかぶっているのが筆者で、左側と一番奥には大学生の列が見える。最近、全国から大学生を中心に多くの若者が来てくれるようになった。国会前の運動と連動しているように感じられる。集会では県外からの来訪者にはスピーチをお願いしているが、若者たちの検証と考察に感心させられる。彼らが異口同音に述べるのは「平和」の意味の違いである。県外では「平和」は与えられるものだが、沖縄の「平和」は勝ち取っていくもの、そして平和憲法も県外にはあるけれど沖縄に来てみたら無いということに気づき、「来てみなければ分からない」という言葉で締めくくる若者が多い。
彼らにとって「戦争法案」が現実的となった今、辺野古は見過ごせなくなったようだ。10年前の海上闘争のときにもいたが、辺野古ぶるー(カヌーメンバー)やスタッフになって残ってくれる若者が増えた。心強いことに2月頃にはマスコミに内定を取った大学生が自己研修で活躍した。今や辺野古は若者たちの「平和学習」「ジャーナリズム学習」の場にもなっている。私をはじめ、60代から80代後半までの高齢者が多い辺野古総合大学だが、意欲的な若者たちの参加を得て希望にあふれる日々である。
「夜明け」が近いと感ずる。(沖縄県本部町在住)
もくじへ
「試練」との認識に立つ読売経営
「政治経済がうまくいくか、今年は向こう10年の日本の運命を決める大事な年になります。ひと言で言うと、大衆迎合的なポピュリズムを排除しなければならない。(中略)ポピュリズムを排除するのかしないのかという方向に政治と国民、経済界も含めて誘導していくのが新聞の使命であり、特に最も健全な体質を持った読売新聞の大きな使命と考えています」。ことし年頭の賀詞交換金での渡邉恒雄読売新聞グループ本社会長・主筆の発言だ。ナベツネが見立てた「情勢分析」どおり、「向こう10年の日本の運命」を左右する重大な事態が進行しているが、そこで読売新聞が「政治と国民、経済界も含めて誘導していくのが、大きな使命」とまで言い切っている。読売の本質、役割をあからさまに語った。
●経験ない事態が
しかし、社の現状は生易しいものではないようだ。ナベツネの嘆きが聞こえてくる。
「読売は1年間(2014年)で66万部減少、広告収入も、ピーク時に1700億円あったものが、800億円までほぼ半減し、去年(14年)も800億円をこすことがありません」。
6月の株主総会直後に開いた「読売東京七日会総会」(販売店主など約1000人出席)ではさらに踏み込んだ発言をしている。「部数が過去−年間で数十万部減り、広告収入も153億円減少し、総売り上げも前年度比186億円減少している。これは、私の社長就任以来二十数年の経験でも一度もなかったこと」と吐露した。
朝日新聞の一連の問題を「チャンス」ととらえ、大量の物量作戦で読者獲得に臨んだが、増紙に転じるどころか、多くの読者を失っているのが現状なのだ。
●深刻さ増す販売店経営
読売経営陣の危機感は相当なものだ。減収を招いた「最大の原因」を折り込み広告減と人件費にしているが、実は押し紙問題が販売店にとって大きな負担になっていることは明確である。
読売販売店に限らず、新聞販売店は発行本社から読者数以上の部数を日々、押し付けられている。販売店にとって部数とは読者数とプラスアルファー部分が合まれている。部数と読者数とには、かい離があるのが現状である。販売店は、折り込み広告収入を読者のいない分まで手数料として広告主から得て、押し紙分の購読料金の一部を賄ってきた。しかし、経済不況で折り込み広告が激減、販売店の体力を急速に衰えさせている。読売販売店も、そのことを顕在化させてきている。
●軽減税率へ死に物狂い
消費税10%増税時に「軽減税率適用を勝ち取るべく、死に物狂いで戦う」。経営幹部の発言はヒートアップしている。消費税増税の旗振り役の読売が、今度は「軽減税率適用」に血道をあげているが、どれだけの説得力を持つものなのか、大きな疑問があると言わざるをえない。
七日会総会でナベツネは「苦戦」の要因を消費税率の引き上げと長年の不況で、企業の宣伝費支出の激減をあげているが、増税不況の責任の一端はまぎれもなく読売社論にある。消費冷え込みを作り出した要因には、まったく触れようとはしない。そればかりか、企業内では「危機」を煽りたてリストラを推進、販売店には「物流カ」を生かせとまで迫っている。
リストラ推進は業績の悪い関連企業・子会社に向けられている。その一つ、読売グループで関連子会社の報知新聞では今年はじめ、50人もの希望退職を、その前には報知の印刷部門子会社でも同様の人員削減を断行した。
「2015年は読売新聞にとって試練の年」(同社の中期計画)と位置づけているが、果たして? 販売店いじめとリストラ頼みの経営は、もはや限界である。【元新聞関係労組勤務員・大手町K】
もくじへ
任期満了に伴う所沢市長選の投開票が、10月18日(日)と迫るなか、現・所沢地区労働組合協議会議長の元教員、市川治彦氏(62歳=東狭山ヶ丘在住)が、市長選への出馬を正式に表明した。
市川氏は地元三ヶ島小・三ヶ島中、県立川越高校、横浜市立大学文理学部を卒業。市内中学校(美原・富岡・上山口・小手指の4校)で35年間の教員生活を送るなか、所沢市教職員組合委員長など歴任した。
また、今年2月に小中学校へのエアコン設置を巡って、執行された住民投票での「住民投票を成功させる会代表」、「所沢市基地対策協議会委員」、「守ろう憲法・オール所沢連絡会」の共同代表など務めてきた。
住民投票で65%がエアコン設置を是としたほか、育休退園問題でも保護者の家庭の事情を無視し、突然に退園を迫るという事態が起きた」と、指摘した上で、「市長の政治手法は多数の意見に耳を傾けず、一方的に強引に進めるスタイル。市民感覚からズレている」と厳しく指弾した。「市民の声を聴き市民とともに歩む市長として頑張りたい」と決意表明をした。
狭山ヶ丘地区4学童クラブ連合会会長、狭山ヶ丘土地区画整理問題を考える会代表世話人、所沢市教職員組合委員長等を歴任した。
もくじへ
《ついに来たか!》
原 緑
「俺、絶句。言葉が無かったね。これだ、ついに来たかって」そんな話に大笑いをしました。
話というのはこうです。彼はこの数週間というもの、いくつか抱えている結構面倒な仕事を同時進行で処理しなければならず、ずいぶんと切羽詰って過ごしていたそうです。その日も朝からばたばたと追われ、それでも「どうやら目途がついた、午後にはもう終えられる」と思ったときに、その流れの勢いで「おい、昼飯はどうする」と奥さんに聞いたそうです。すると「あら、お父さん、お昼はさっき食べました」という返事。そこで絶句、「ついに来たか!」です。
済ませた食事の事を忘れる、ということはいわゆるボケの第一歩として良く知られています。古いことは覚えていても新しい情報は忘れてしまうということも、ほとんどの人は知識として受け止めています。そして他人事のうちは笑ってその場が収まります。
その話を聞いた数日後、なんと私は友人との待ち合わせの日を間違えたのです。決められた時間に決められた場所で友人の車を待つこと15分。携帯電話を持たない私はそのままもう少し待ちました。待ちながらふと、あれ、今日は何日だったかしらと疑問符が頭の中で点滅したのです。そういえば今日はゴミ出しを気にしなくてもよい日、…ということは水曜日。金曜日には先約があるのでと決めた日程は、…そう木曜日でした。急いで家に戻りカレンダーを確認すると約束の前日ではないですか。ああ、ついに来たか!
確かにいろいろな用件が目いっぱいの毎日の隙間に、取り急ぎ組み込んだ新たな約束ではありました。朝からその気で外出用の服を着て、待ち合わせの場所に出向いたその“てっきり”という確信的な思い込み。こうして老いの混乱は音もなく近づいてくるのかなあ。
私もか、と目の前は一瞬暗くなりましたが、一つ学んだと思うことにしましょう。
もくじへ
鑓田英三(駿河台大学教授)
(1)「戦争依存症」の国アメリカ
「戦争法案」で強調されているアメリカとの「同盟」は、日本を奈落の道におとしいれるものである。それは、アメリカは重度の「戦争依存症」に罹っていて、そんな国に「従属」しようとする今回の法案によって、日本は再び戦争の泥沼に入り込んでいくのが必定だからである。
20世紀に入ってアメリカは「戦争依存症」に罹っていく。第一次世界大戦で直接戦場にならなかったアメリカは、連合国に武器や工業製品や農産物、原材料、資金などを輸出する戦争特需で大儲けしていった。さらに、第二次世界大戦でも戦時ブームで潤い、1929年からの世界恐慌から立ち直っただけではなく、大戦後の繁栄の基礎を築いていったのである。その過程で戦争に寄生していこうとする企業体質が根付いていく。基幹産業の大企業が、軍需など巨大な国家需要へ依存していく「軍産複合体」が形成されていった。
(2)「軍産複合体」の発達
第二次世界大戦後、政治・軍事力・経済力で圧倒的な優位に立ったアメリカは、「パックス・アメリカーナ」(アメリカによる平和)を追求し、朝鮮戦争やベトナム戦争などで「戦争依存症」の症状はひどくなる一方であった。膨張し続ける軍事費は、「軍産複合体」を肥大化させた。1961年、軍人上がりのアイゼンハウワー大統領さえ、退任にあたり、「平和を維持するための軍事の必要性が、『大規模な軍事組織と巨大な軍需産業の結合』をもたらした」と警告するほどであった。
「軍産複合体」は、単に巨大企業による軍需の受注にとどまるものではなかった。武器の開発が、科学技術を押し上げていったのである。兵器の予算は青天井であり、国防総省の研究開発費は、全体の約半分を占めていた。その軍事用に開発された科学改術が民間の企業にも転用された。半導体技術は、小型軽量ミサイル開発の産物で、インターネット、コンピュータ、LSIなどすべて軍事用に開発されたものであり、軍事開発がなければ現在のアメリカの産業発展はありえなかったのである。
しかし、60年代後半から70年代にかけて、ベトナムでの敗北はアメリカの威信を大きく低下させただけでなく、76兆円にも上るベトナム戦費など軍事費の増大はインフレをもたらし、西ヨーロッパや日本の急速な経済復興や石油危機も加わって、アメリカ経済の弱体化を招いた。
(3)レーガンからの軍備拡張
そこで、軍事的にも経済的にも「強いアメリカ」を取り戻すべく1981年に登場したのが、レーガン大統領である。しかし、彼が採った政策は「戦争依存症」を一層進行させるものでしかなかった。彼は、軍事的威信を回復するためにソ連に対し「新冷戦」を仕掛け、「レーガン軍拡」を推し進めた。その後も「戦争依存症」は進行し、今世紀に入り極限にまで達している。ブッシュ前大統領は、2001年の9・11テロのあとの「対テロ戦争」で軍事予算をさらに巨大化させ、2000年の3700億ドルから2011年の6700億ドルと倍近くに膨れ上がっていった。
また、経済的に強いアメリカの復活のためにとられた政策(レーガノミックス)以降、アメリカ経済政策は社会保障や賃金の充実を重視するケインズ主義から、政府による規制の緩和・撤廃や企業減税によって大企業の強化を目的とした新自由主義に転換した。規制緩和によって寡占化した大企業は、低賃金を求めて途上国に生産拠点を移す「グローバル化」を進めていった。「生産の空洞化」と同時にアメリカ経済の主役に躍り出たのが、「マネー資本主義」FIRE(金融、保険、不動産、リース)であり、ウォール街の金融資本がアメリカ経済を牛耳っていく。1995年から2008年にかけて1京円のマネーがアメリカに集中していったのである。
また、軍事技術の転用によって、世界をリードするIT産業の発達がもたらされ、それが企業のグローバル化や「マネー資本主義」の原動力になり、三位一体で進行していった。
巨大な軍需が、日欧中の台頭で競争力を弱めていた基幹産業(軍需産業)を底支えしていただけではない。民需中心の「平和産業」でも軍需の割合が高まっている。飛行機のロッキード社は軍需生産の割合は、92%を占め、電機メーカーGEでも26%に達している(2008年度統計)。そして、最近アップル社などのIT産業も軍事生産に積極的に取り組み始めているように、アメリカ経済全体が「軍産複合体」になっているのである。
(4)1%に奉仕する99%
グローバル企業の海外生産の進展によって、国内での製造業従事者は、1980年の2000万人から2010年には1200万人に減少していき、失業するか、求人が多いものの低賃金のサービス業などに働き口を移さざるを得なかった。その結果顕著になったのが、中間層の没落であり、貧困人口は2000年の3100万人から2010年には4620万人に膨れ上がった。
とくに対イラク・アフガン戦争の94兆円に膨れ上がった軍事費は、大幅な財政赤字をもたらし、累積債務は、2001年の580兆円から2011年の1500兆円に達した。このツケが国民に転嫁された。本来の国家の役割である教育、医療、福祉が放棄され、資本の手に委ねられ儲けの対象になっていき(民営化)、貧困化を一層促進することになった。2010年には、国民の三分の一が医療費を払えないほど高額の治療費が原因の破産が半分を占めている。
他方、グローバル企業やウォール街金融資本の「スーパー経営者」が高額の所得を獲得していた。彼らの所得は平均労働者の1980年の127年分から2006年には1723年分に跳ね上がった。「戦争依存症」のもとで、「99%の人間に負担を押し付けて異常な利益を手にする1%の富裕層」という構図がつくられていった。
(5)これからのアメリカの戦争戦略
この構図は、「チェンジ」をうたい文句にしたオバマ政権になっても基本的には変わらなかった。公的か民間のどちらかの保険に入らなければならない「オバマケア」(2014年実施)でも、政府が薬価交渉権を放棄するなど製薬・保険業界の利益は温存され、国民の負担はかえって増している。
そして、国民の疲弊化で民需が停滞するのに逆比例して軍需への比重が高まった結果、経済界は大量のロビイストを送り込んで政府との癒着を強める「コーポラテイズム」に走り、「資本独裁国家」になっている。そして、「99%」の反発を抑えるために、愛国者法など政府に都合の悪い情報の拡散を防ぎ、国民への監視を強める「警察国家」体制を強化する一方で、「対テロ戦争」のように統一した敵を作っで危機感を煽り「強い・一つのアメリカ」というスローガンで国民を駆り立てている。そのためにも、軍備の拡張、戦争の継続が正当化されているのである。
しかしながら、莫大な軍事費のツケによる国民生活の破壊やホームレス350万人のうち50万人がイラク帰還兵で、2014年には800O人の帰還兵が自殺しているという。身近に戦争被害が広がる中で、オバマ大統領が採ったのが、本国から操縦する無人飛行機(ドローン)によるイラク攻撃や民間企業に後方支援や戦闘を委託する「戦争の民営化」である。ハリバートン社がイラクに派遣している4万8000人のうち、35%がネパールなど開発途上国からの出稼ぎ労働者であり、アメリカ人の人身御供になっている。
また、徴兵制にかわって若者をリクルートする方法として問題になっているのが、貧困からの脱出を求めて途上国や国内から志願する「経済的徴兵制度」である。「戦争依存症」による弱者切り捨て政策のなか、不法滞在者には市民権を与えるとか、学費ローン返済免除プログラムなどいろいろなエサが蒔かれ、若者を戦争に駆り立てているのである。
そして軍需生産のおいしい部分以外を他国(日本)に肩代わりさせようとしているのである。「集団的自衛権」を行使する今回の戦争法案によって、自衛隊は米軍の指揮下に入り「米衛隊」になる。そしてそれは日本人も途上国の人々同様、アメリカの1%であるグローバル企業、ウォール街金融資本の捨て駒として尊い命を差し出すものでしかない。
もくじへ
私のなかに確実に広がった未来と希望
宮内聡子(専修大学文学部4年)
胸が震えた…
私が初めて路上に出て抗議活動に参加したのは、昨年12月だった。友人に「特定秘密保護法について学生が主体の抗議行動があるから、興味があれば参加して」と声をかけられた。「デモって効果あるの? 他の人に変な目で見られるのでは?」と疑問や不安もあったが、同世代の人たちが主催で活動していることが気になり参加した。政治に多少関心はあっても、今まで考えもしなかったデモという選択肢が、突然現実の選択となった。
寒空の下、集まった学生たちが、交通整理をしたりパンフレットを配ったりしながらラップ調のシュプレヒコールを挙げる様子は力強く逞しく見えた。また、思いを同じくする参加者が世代を超えてコールで一つになることを体感したときは胸が震えた。行動することで、人と出会い、人との出会いがさらに思考を促し、次の行動につながるというサイクルを感じられた。
「どうせ可決」の声も
今年、9月18日。夏休糺も終わり、授業が再開されたばかりの大学ではこんな声が聞こえてきた。「今、国会やはい感じだよね。でもさ、どうせ可決されるでしょ」なんだか他人事のようにそう言った。その後、19日未明に安保法案が可決・成立した。たしかにこの学生が言うとおりだった。
日本が戦後70年に渡って不戦の誓いを立て守ってきた平和主義のあり方が、憲法違反の疑いが強い法案を数の力で押し通すという、民主主義・立憲主義をないがしろにした行為による転換だった。
悲惨な加害と被害を背負った国として揺らぐことはないと思っていた平和国家としての方針が、国際情勢の変化という言葉によっていともたやすく舵を切るにいたるとは驚きであり、恐怖である。しかし「一国の政治は国民を映し出す鏡」とも言われる。だからこそ、政治が今後もっと良くなるかあるいは悪くなるかは、私たち一人ひとり次第なのだと今強く思う。
まだ壁がある政治の話
私は6月から国会前に足を運び抗議活動に参加してきた。あの日、国会前や全国各地では「戦争法案絶対反対!」と最後まで声の限り訴える人たちがいた。あるいは、公共放送であるNHKが行わなかった国会中継を、ネットで観ながら野党に応援メッセージを送ったり、SNSで中継の様子を拡散させようと努力する人たちがいた。
「どうせ」と投げやりになったり、無関心であったりすることは楽かもしれないが、自分の頭τ思考し行動する力は、私たちのなかに、私自身のなかに、確実に広がっていると実感して、とても希望を感じた。
また、SNSで友達に向けて安保法案に関する情報の発信やデモの呼びかけをしていたなかでも希望は見えた。政治の話題には、グルメや遊びの話題と同じようには良い反応が返ってこない。むしろ友人と実際に顔を合わせたときに「日本の政治は駄目だから。私は諦めている」と言われて落ち込み、悩んだこともあった。しかし、徐々に友人から賛同する声や、反対派の意見への疑問が投げかけられるようになった。顔の見える関係であるからこそ、異なる意見でも冷静に対話ができるのではと思う。安保法案の反対デモが大きくなったことで、若い世代で政治はタブーではなくなったという声も聞くが、まだ壁はある。これからも誰もが意見を交わせる雰囲気を作る不断の努力をしていきたい。
なぜ急いで普通の国に
また、戦争体験者が少なくなり戦争を知る人が語れなくなる時代が来るなか、「平和観」は世代によっても様々である。平和のためには国際的に協力しなければ国を守れない、抑止力が必要だと言う人もいる。しかし私は、同じ過ちは犯さないから大丈夫だと傲慢にならず、注意深く他者と対話する姿勢で信頼を得ることが不可欠だと思う。急いで「普通の国」にすることが本当に平和に資するのか、問い直すべきだと思う。
もくじへ
米軍横田基地にオスプレイが配備されることが公表されました。所沢市の西部地域上空も危険なオスプレイが飛行することになります。県内で戦争の準備のようなことが進められていることに注視したいと思います。
入間基地に自衛隊病院
昨年9月防衛省は入間基地に隣接する東町側留保地に「災害対処拠点施設と自衛隊病院整備計画」の協議を入間市に提出しました。この留保地は入間基地の航空機騒音と住宅地を分離させる緩衝地帯で、貴重な緑地帯(自然林)です。利用権のある入間市は、「近隣住民の生活環境を守り、市民に健康・医療・スポーツの機能を持つ公園として活用する」とする申請を国に提出しています。突然、防衛省はこの留保地を自衛隊が使いたいと協議を強要しています。
「災害」と謳っていますが、目的はあくまで自衛隊の訓練・演習場が目的であり、入間基地の拡張にあります。市民からは「病院があってもよいのでは」との声もあるようですが、防衛省側は入間市民の診療は行わず、外傷など軽い2次救急医療に限って「自衛隊医療業務に支障のない範囲」で認めるとしています。これはまさに野戦病院そのもの。市民から基地強化反対の声が挙がっています。
C2入間基地配備を公表
いま入間基地に配備されているC1輸送機よりはるかに大きいC2新型輸送機(平成29年度末から技術・実用試験を実施)が電波情報収集機YS1−11の後継機として、機上電波測定装置を搭載(機外に5カ所の各種アンテナを収納するためのアンテナドームを設置)した機種を2028年初頭から入間基地で試験評価(試験飛行)することが、北関東防衛局から入間市に伝えられました。配備に伴い、電波隊局舎、整備格納庫、電子整備場の建設が行われます。
C2の入間基地配備については、滑走路の短さ、市街地の基地であることから、配備は危険であるとし、平和委員会などが反対してきました。
防衛医科大学校で1種感染症対策
防衛省の平成28年度概算要求の概要によると、防衛医科大学校の概算要求に防衛医学に関する教育・研究拠点としての機能の強化の診療体制の充実強化の項目に、防衛医科大学校病院における1種感染症治療対応及び医療安全・感染対策強化のための増員が要求されている。感染症を専門とする人材の育成(2百万円)、防衛医科大学校病院及び自衛隊中央病院における1種感染症患者診療態勢のための施設機材の整備(2千万円)と記載されています。
1種感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱およびラッサ熱のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病が指定されている。感染症例には第−種(ないし特定)感染症指定医療機関への入院が知事より勧告されうるが、緊急時などやむを得ない場合にはその他の医療機関への入院が勧告される場合もあります。所沢で研究する目的は、海外に派遣され感染症にかかった自衛隊員の治療の研究が目的です。武蔵村山市にある国立感染症研究所の周辺では住民による反対運動も起きています。
もくじへ
丸山重威(元共同通信)氏が『安倍壊憲クーデターとメディア支配』を緊急出版
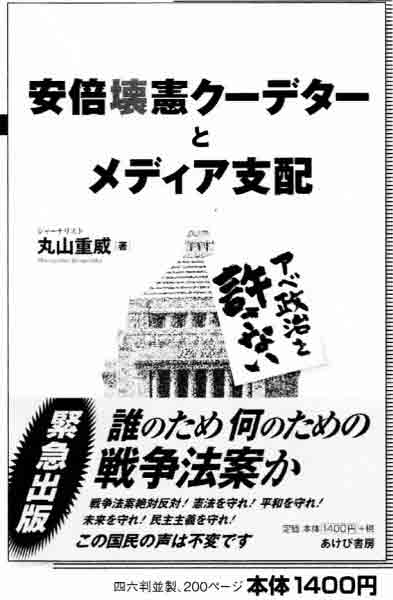
機関紙への寄稿の協力を頂いている一人、丸山重威(元共同通信編集局デスク、元関東学院大教授)氏が、このほど、『安倍壊憲クーデターとメディア支配』を緊急出版した。
丸山氏は「猛暑や台風や、国立競技場問題、『8・6』『8・9』、川内原発再稼働、70年談話など、めまぐるしく動く中で、参院での審議が行われていますが、首相は相変わらず、論理の破綻をものともせず、質問にはまともに答えず、とにかく意味不明の言葉の繰り返して、『白紙委任』を求めるような時間像ぎの答弁に終始しています。同時に、衆院での『維新の党』に続いて、参院では『次世代の党』などが修正案提出で合意し、自民・公明の強行路線を覆い隠そうとするなどの世論工作も始まっています。
安倍政権の政治手法は、世論操作を意識し、メディア支配を狙って行われていることに大きな特徴があるとも思います。
一方、国民のなかからの反対の声は、学者(法曹、女性、大学生、高校生、ママさん、ミドルズなどへと広がり、さまざまな工夫を凝らした運動が広がっています。30日には東京で10万人、、全国で100万人という運動も成功しました。
私も60年安保大学一年生世代ですが、『組織頼み』だった当時とは全く違って、全く新しい状況が生まれて来ているのかな、とも思います。要するに、この広がりは、『戦争は嫌だ。戦争法案反対』の一点による共闘が、国民の心からの平和への願いから起きていることを示しています。そんな運動を見ながら、『安倍政権とその後を闘い続けるために』と考えつつ、安倍政権の『本音』と狙いは何か、とにかくわかっていることを記録しようと、あけび書房から『安倍改憲クーデターとメディア支配ーアベ政治を許さない』をまとめ、緊急出版しました」と語る。
本屋さんでお買い求め下さい。
15歳が祖父母の戦争体験聞き書き
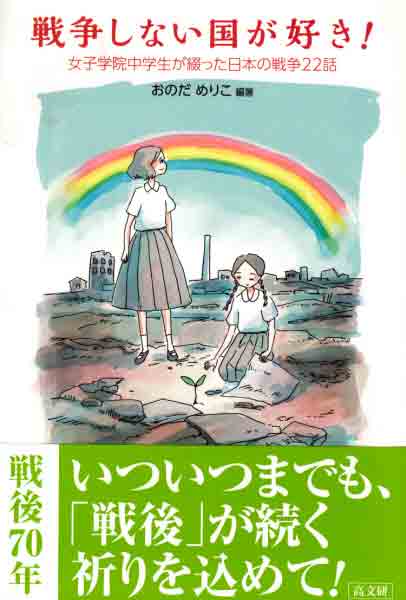
「戦争法案」を阻止し、日本を再び“戦争をする国”にしないため、戦争体験者の話を後世に語り継ごうと、女子学院(千代田区)の中学3年生が祖父母らから聞き取った22篇をまとめた『戦争しない国が好き!』が出版された。
編集を担当した女子学院中・高校国語科元教員の小野田明理子さんによると、同校は1980年度から、戦争体験の聞き書き学習を実施し、「35年間で作文を書いた生徒は約8000人。現在も聞き書きは続いている」という。
小野田明理子さんは「22人の“15歳”は、聞き書きを通じて戦争を追体験した。各編は『二度と戦争を許すまじ』という揺るがない決意に結びついている」と話している。
作家の早乙女勝元氏が、「いつまでも『戦後』のままに」と題して、エールの小論を寄せている。
高文研刊・本体1400+税。
『ヤルタ・ポツダム体制と日本の戦後レジームを考える』
山口・椿峰在住、芦田氏が出版
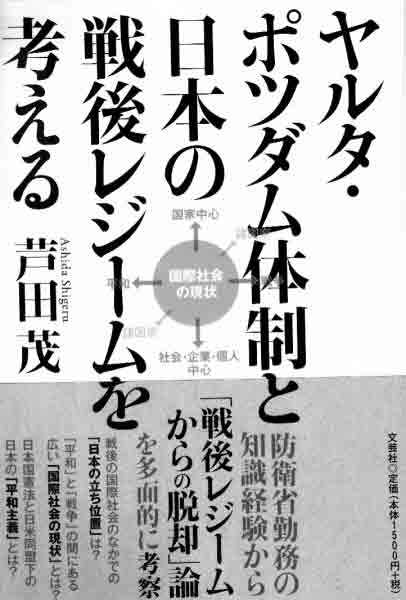
椿峰在住の芦田茂さんが、戦後政治史の資料として貴重な本を出版した。「ポツダム宣言」についてあいまいな態度をとり続け「戦後レジームからの脱却」を公言する安倍首相に読んで貰いたい本である。
この本は、戦後史の事実をたどりながら、「積極的平和主義」の危うさを静かに語りかける。
筆者は「ヤルタ・ポツダム体制は、『戦争ありき』『恒久平和ありき』の世界観から、戦争防止の国家努力必至とする世界観への大きな転換」と捉える。確かに今日の日米体制を真っ向から否定する論陣を張っているわけではない。「改革ではなく現状維持」を基調とする論理が、「解説」という言葉で、語られているところに注目したい。
そして何よりも、歴史的事実の記述と図表化された膨大なデータである。南沙諸島、尖閣諸島の領有権にも触れる記述もある。戦後の国際社会は、戦争防止のための努力を積み重ねてきた現実を明示する。この歴史的現実は、現在の日本の「有事法制」の議論に大きな警告になっていると語る言葉には説得力がある。筆者は元防衛省職員。(門目)
文芸出版。定価1500円
『朝日新聞』はどこまで卑屈になるのか 新聞透かし読み
14年6月〜12月 「週刊金曜日」の有料メルマガにコラムを掲載心ている同誌発行人の北村肇氏が、このほど、キンドル本で刊行した。
安倍政権の支持率はなぜ落ちないのか。答えは一つ。「新聞やテレビが真実を伝えないから」新聞をこよなく愛する筆者が、新聞、特に全国紙の実態を、日々の記事をもとに浮き彫りにする。メディア関係者や志望者必読の書。
ネットでご購入下さい。300円とお手頃の価格です。
もくじへ
バラライカ バリトン ギター 3人のソリストが紡きだす“ロシアの心”
ヴェルトクラードトリオ所沢公演

日 時:10月24日(土)18:30開場 19:00開演
会 場:所沢市民文化センターミューズ
チケット: ー般2500円、学生2200円、シニア(60歳以上2200円)。
お問い合せ・お申し込み090−8504−8186中山 04−2939−7630坪井
主 催:日本ユーラシア協会所沢支部
後 援:所沢市教育委員会ほか
もくじへ
トップページへ