羅漢像
浅川光一(北秋津在住)
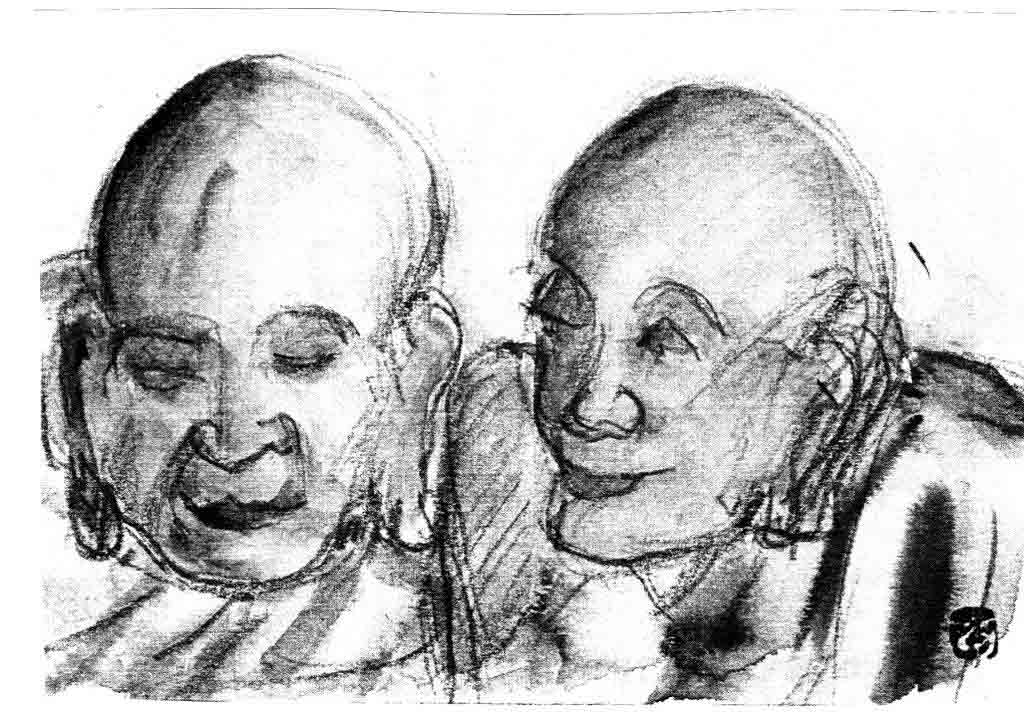
機関紙135号 (2017年9月2日発行)
桂 敬一(元東大教授)
森友・加計問題、南スーダン派遣自衛隊の「日報隠し」などで批判を浴び、安倍内閣の支持率は急速に落ち、不支持が支持を大幅に上回る結果となった。それらの影響もあり、自民党は都議選で大敗、安倍首相や側近も危機感を募らせ、面目一新とばかりに内閣改造に踏み切った。しかし、その魂胆が疑惑隠し、みせかけだけの刷新工作だということがバレバレで、支持率回復は思うようにいかず、首相が念願の改憲を、オリンピックの年=2020年施行で実現、と大見得を切った方針もぐらつき、もはやつぎの政権はだれがどうつくり、実権を握るかが取り沙汰される事態となっている。
8月になって北朝鮮のミサイル実験が実戦規模の様相を呈し、米軍基地のあるグアム島の周辺海域に同時に4発を着弾させる、と同政府が大見得を切ると、それに応じてトランプ米大統領も、やるならやってみろ、お前の国を今までみたこともない状態にしてやる、と威嚇した。これに対してメルケル独首相や英仏政府は、あくまでも話し合いで問題の解決を図れと両国に提言、とくにアメリカには、戦争に帰着する恐れのある対応は避けよ、と提言した。これに比べ、安倍首相はアメリカ一辺倒だし、ワシントンの日米外務・防衛担当閣僚安保委員会(2プラス2)に出かけた改造内閣の新閣僚、小野寺防衛大臣・河野外務大臣の二人も、北朝鮮に対するアメリカの方針に同調、日米防衛協力の強化、自衛隊と米軍の一体化推進に賛同するだけだったのだから、がっかりだ。
1950年の朝鮮戦争は、53年に休戦となったが、戦った中国・北朝鮮と米国・韓国、それにアメリカの後方基地の役を担った日本の5か国のうち、中米韓日の4国はすべて相互に国交正常化を実現、戦争を完全に終結したが、ひとり北朝鮮だけが未だに米韓日との国交正常化を実現しておらず、極東アジアの孤児のような存在になっている。冷戦時代はソ連や中国が面倒みてくれたが、現在のロシアは、もうそうしたパトロンではないし、中国も自国の大国化路線追求のほうが忙しい。だから北朝鮮は、独りで突っ張るよりほかなく、必要以上に強がってみせるのではないか。
少年時代だったが、朝鮮戦争当時のことはよく覚えている。この戦争の軍需で工場の稼働が盛んになり、にわかに日本に好景気が到来したのだ。工場の排出する非鉄金属の屑が高値で売れ、大儲けするものもおり、「カネヘん景気」だと、これをもてはやした。日本経済はこの戦争で復活のきっかけを掴んだのだ。他国の不幸をもっけの幸いとして復興へと転じた日本は、そもそも1910年(明治43年)、韓国併合で半島全域を植民地として支配、今日に至る朝鮮の不幸の遠因をつくった張本人でもある。南北に分割された朝鮮、そこに孤立する今の北のありようを眺めるとき、この地とそこに住む人びとが不幸に陥る状況の到来に、日本は二度と手を貸してはならない、という思いを強くする。
だが安倍政権は、アメリカが強硬策で臨み、日本政府がハイハイとこれに協力すれば、米政府も歓迎、この政権に対する支持・応援を明確にしてくれ、日本のメディアもそのことを否定しきれず、国民も内閣支持に転じるしかないだろう、と踏んでいるフシがある。
民進党が解体、その大きい部分が自公連合に合流しそうだ。小池都知事の「都民ファースト」が国政版の「日本ファースト」を押し出したが、これも弱体の安倍政権に恩を売り、「与党共闘」で一役買おうとしている。
だが、もうこんな魑魅魍魎にでかいツラさせているヒマはない。市民連合の総がかり行動で筋の通った野党共闘を強め、広げ、安倍政権の付け入る隙のない新しい政府を実現する時がきている。トランプに反対するアメリカの市民とも、極東アジアでの戦火を二度と許さない国境を越えた市民たちとも手を携え、新しい市民運動を展開していく時代が日本にも訪れつつあるのではないか。(メディア研究家)
丸山重威(ジャーナリスト)
「憲法9条1、2項はそのままにして、自衛隊の存在を書き加えることは、理解が得られやすい」。5月3日、憲法記念日に読売新聞インタビューと改憲集会へのビデオメッセージでこう表明した安倍晋三首相。都議選敗北(7月2日)と内閣改造(8月3日)で、支持率急落、「低姿勢路線」に転換して、改憲もぺースダウンしたかに見られているが、実はこれこそ安倍流改憲戦略。改憲反対の声を広げよう。
低姿勢路線を見せている首相の陰で、自民党の憲法改正推進本部では、戦争法などで公明党との協議を成功させた高村正彦副総裁と、官邸から党に移して権限を持った首相側近の萩生田光一幹事長代行が積極的発言を続けている。BSフジに出演した萩生田氏は7日「改憲の旗を掲げて歩みは止めない。自民党案を正式に出せる準備をする」と発言、高村氏は15日の時事通信インタビューに「改憲スケジュールは変えない」と表明した。
改憲推進本部には、側近の下村博文幹事長代行を本部長補佐、西村康稔総裁特別補佐を事務局長補佐に据え、副総裁の高村氏らに顧問を委嘱したほか、これまでは総裁の特別組織で事務局員も兼任だったのを8月1日から事務局も党の部署とするなど体制を強化した。新たに、事務総長に根本匠副本部長、事務局長に岡田直樹副本部長が就任した。
首相は自らの「代弁者」としての高村、下村、西村氏のほか、萩生田両氏を使って、自身の姿を隠しながら、改憲路線を進めていく戦略だ。もともと、麻生太郎副総理は2013年には、「憲法の話は、私どもは狂騒の中、わーっとなったときの中でやってほしくない。ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていた。だれも気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうか」と述べている。
そんな中で、見逃せないのは、改憲派の大衆運動での展開だ。既に神社での「改憲署名運動」や日本会議の女性対象の「憲法おしゃべりカフェ」など行われているが、日本会議の集会では、改憲賛同の1000万人ネットワーク作りを掲げる全国キャラバン隊のメンバーが「ありがとう自衛隊」キャンペーンを進める決意を表明した。(赤旗8月19日付)安倍首相と自民党が描く改憲への工程は、①自民党案の作成、議論をまとめ、17年秋の臨時国会の憲法審査会に提出 ②改憲派を結集し、現衆院議員の任期は18年12月までなので、3分の2の多数がある間に、つまり18年1月召集の通常国会か、秋の臨時国会で国会発議 ③発議から国民投票には、60日-180日の期間が必要なので、場合によっては総選挙と同時の国民投票 ④18年は明治150年。19年の天皇の交代、代替わりもあるので、2020年を「新しい時代」にするためのムードを盛り上げ、この中で「自衛隊合憲化」を図る ⑤19年中に国民投票で承認されれば、20年実施が完成する--というものだ。相当タイトだが、突っ走るには時間をかける必要はない、という発想だ。
首相の「自衛隊加憲」論は、自衛隊が災害出動で国民に容認されていることを理由にしたものだが、自衛隊はいま、米軍との一体化が進み、装備や武器では世界有数の存在だ。「陸海空軍その他の戦力」を持たないと決め、「交戦権」を認めない9条2項はそのままにされても、「前項の規定にかかわらず、自衛隊を置くことができる」などの条文を新設すれば、そちらが優先されるから、1項、2項は空文化される。つまり、戦争法で世界の裏側でも行動が可能になった自衛隊は、法律で軍事法規を次々と作ることも可能になる。
「国民投票になれば反対が多いだろう」という見方もあるが、カネや情実を使った改憲派の運動、宣伝は予測もつかない。「提案させない」.「発議させない」運動が、帰趨を決める。憲法を守るには当面、安倍改憲政権を倒すことがどうしても必要だ。(元共同通信)
浅川光一(北秋津在住)
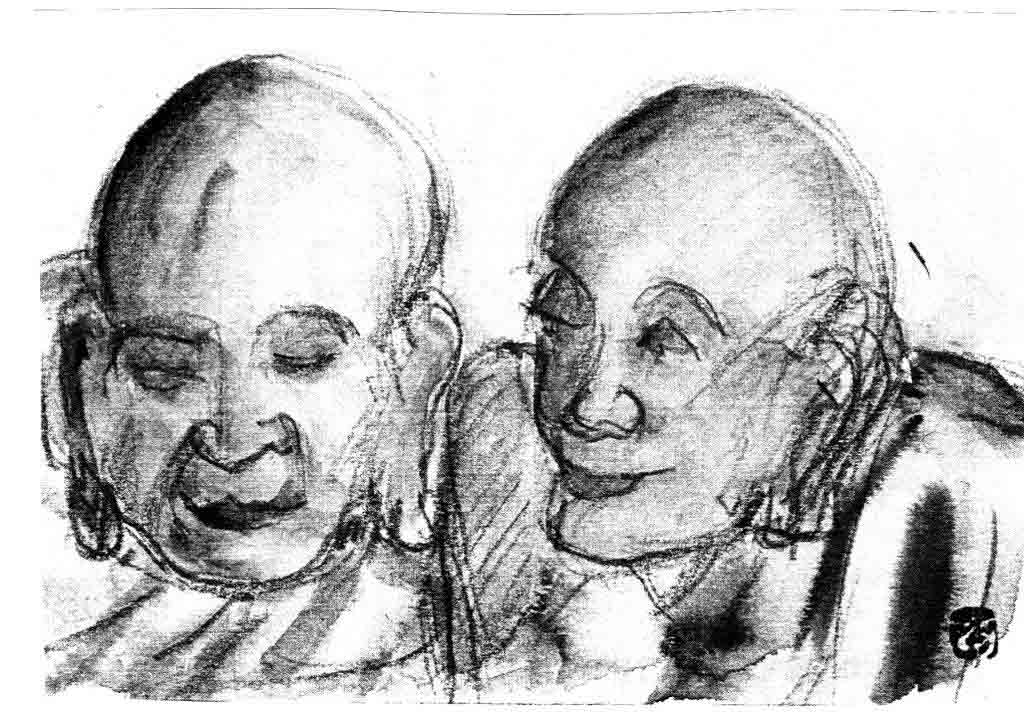

原田みき子(沖縄県本部町在住)
8月4日、日本環境法律家連盟と沖縄ジュゴン訴訟弁護団が、辺野古で座り込む市民を対象に行った「人権調査」の速報結果を発表した。5日間の集計によれば、207人のうち149人が「機動隊の暴力」を上げた。私自身数々の暴力を受け、何度も公安委員会に訴えてきたが、やっと全国的な連盟(440人)が動き出してくれた。
「腕をひねられて泣くほど痛かった。肩から上に腕が上がらなくなった」(70代女性)、「鉄柵の中に下ろされるときに腰を痛め整形外科に行った」(70代女性)、など、70人が「腕をひねる、ねじる、強くつかむ」の行為を上げ、他に「殴る」「蹴る」が5人ずつ、「胸ぐらをつかむ、押し倒す」が2人ずついた。わずか5日間の調査でこれほど上がった。他に私の記憶では、ろっ骨を折られた人が2人、脳を痛め嗅覚を失った人、股関節に被害を受けた人もいる。今回の数字は一部分でしかない。暴力を振るうことに慣れた機動隊員たちは、私たちが「痛い!」と叫べば、うすら笑いさえ浮がべ、数倍のお返しをくれる。だから誰も叫ばなくなった。黙って座り込みの列から引き抜かれ鉄柵の中に運ばれていく。
かつて中隊長が私たちを「犯罪者!」と呼んだが、どっちが犯罪者かと訊きたい。安倍晋三首相のお墨付きをもらっているのか、やりたい放題である。私たちが閉じ込められる鉄柵の中は日陰がなく、しかも囲みをつくっている数台の警察車両が出す排気ガスで気持ちが悪くなる。友人が置いた温度計は52℃を指していた。1時間近くも閉じ込められトイレも許されない。これではまるでアウシュビッツじやないか。私たちはガス室に放り込まれているようなものだ。調査した弁護団は「深刻な人権侵害がある」とし、米国の人権・環境団体などと連携し「国際問題化する」とした。10月には追加調査もするそうだ。今後、世界的な人権問題として取り上げられることを願う。座り込む市民は女性や高齢者が多い。みんな子や孫に基地を残したくない。さらに戦争の加害者になりたくないと頑張っている。私たちの声が世界中に届き、国際世論が安倍政権の非道を断罪してくれる日が待ち遠しい。
8月21日の沖縄タイムス紙1面に、ワシントンに本部を置くアジア・太平洋系アメリカ人労働連合(66万人)が年次総会で辺野古新基地建設反対の決議をしたことが載った。昨年に続き2度目で、同様に退役軍人らでつくる平和団体「VEP」も12日に2度目の決議をしている。沖縄の蒔いた平和の種が芽を出し始めてきた。
8月13日、山口のホームギャラリー藤原にて荒幡在住の山中茉莉さんによる「被爆体験を語る」集いが開催された。山中さんは広島の被爆実態を世間に知らせた「アサヒグラフ」を持参し、被爆以降の彼女の生きざまが語られた。
彼女は広島で、母と兄とともに被爆した。当時2歳で、父は戦地にあった。生前母は、自分たちが生き延びるのに精いっぱいで、周囲の人に手を差し伸べられなかったことを悔やんでいた。そして、自分たち兄妹に常々「人には良くしなさい」と話していたことなど母の思い、また、彼女の足首に残った傷跡を「天使の足輪(キッポ)」と言って心に傷を負わせないようにした父の思いが語られた。
並べられた遺体、皮膚がぶらさがった人、広島名物の牡蠣の殻が体中刺さって痛がる人、川では多くの死体が浮かんでいたこと。汚い身なりで田舎に行くと家々が戸を閉ざしたこと等。幼時から被爆当時のことを昔話のように祖母から聞いて育った。おばあさんの話を繰り返し聞いていたので、直接の記憶はなくても、被爆体験談は自分の身に染み付いている。それゆえ退職後、しらさぎ会(埼玉県原爆被害者協議会)の語り部に誘われたときに、原爆被害を後世に伝えていこうと思ったと決意が示された。
山中さんは、「名もなき被爆者の記」を雑誌「女性のひろば」に連載中です。
大手町太郎
「新聞業界の未来が描けない」---全国紙の新聞社幹部の“つぶやき”だ。新聞社・通信社の労組連合体組織、新聞労連が7月に開いた定期大会では、「毎年、中規模単組(労組)が、ひとつずつ消滅しているような状況」と組合員の減少を報告、組織拡大・組織強化が最優先の課題であることを明らかにしている。では、新聞界はどのように変わりつつあるのか、本当に「未来が描けない」衰退状況なのか、実相に迫ってみたい。
日本新聞協会の調査結果(2016年の発行部数、普及度/17年2月発表)によると16年10月現在の発行部数は4328万部(朝夕刊セットを1部とカウント)で、前年比98万部(2・2%)の減少となっている。協会関係者などは15年度の112万部減、14年度の164万部減に比べると、“落ち着きを取り戻しつつある”と見ている。10年間の変化では、07年の部数を100とした場合、16年は83・2、朝夕刊セットで1部のカウントでは78・5。夕刊発行部数減が大きく影響している。
広告収入はどうか。電通が2月に発表した「2016年日本の広告費」では、全媒体による総広告費は6兆2880億円で前年比1・9%増、5年連続のプラス成長だ。牽引はインターネットで、ついに1兆円を超す勢いとなった。一方、新聞広告費は5431億円、4・4%のマイナス。雑誌とともに紙媒体の広告離れは激しい。
部数も広告も不振となれば、新聞経営は相当に影響が出ているのでは、と考えがちだが、純資産は前年比2・7%増、初めて1兆2000億円を超した。これは新聞協会が調査している新聞社固定サンプル40社(15年度調査、16年11月発表)で明らかになった。大きな借入をした社もあり、資産全体が膨らんだとはいえ、自己資本率は50%を超えている。多くの社が設備投資を見送り、内部留保に回した結果が、このような「健全経営」を維持しているといえる。
部数も広告も減り続けているのになぜ、依然として収益を確保しているのか。設投、経費抑制とともに、主要因は人件費の削減。削減の大きなテコとなっているのが別会社化で、印刷、制作部門から編集、出版、事業部門へと一気に広がっている。ここに雇われている従業員の年収レベルは、新聞発行本社員の6割程度、中には半分程度というところも現れた。
ここ数年、新聞各社が追求してきたことは「読者が存在しない部数を抱えながらも収益を確実に確保できる企業への脱皮」だ。新聞社の公称部数(印刷部数)が読者数ではないことは、もう誰もが認めるものとなっている。いわゆる「押し紙」(「サービス紙」)の存在だ。バブル崩壊後もしばらくは広告収入を販売店へ補助金(援助金)としてつぎ込むことを続けてきたが、もはやそれも限界に近づいている。発行部数の変化を見るうえでおおいに参考となるのは、「日本一の(発行)部数」を維持している読売新聞だが、16年度の平均発行部数(朝刊のみの公称部数)は894万部(前年度比16万4000部減)としている。「1000万部は絶対維持し続ける」と豪語してきたが、それをあっさり捨て去ってしまった。新聞界全体が公称部数で競うことをやめる大きなきっかけとなった。900万部となっているが、これも依然、「押し紙」を抱えながらの部数であることに変わりはない。
ある全国紙では、16年度末に「20万部の押し紙解消」を予定していたが「諸般の事情」で先送りされた。今年度中には確実に公称部数20万部減となる。どこの社も一気には減らせない事情がある。大きな要因は全国に展開してしまった印刷工場の存在。「押し紙」解消には印刷工場の閉鎖・統合・再編が避けられない。「読者のいない部数を抱えながら確実に収益確保」から「印刷部門」の統廃合へ、次の経営戦略展開が始まっている。どこの社も輪転機更新の大型設備投資を控える事情がここにある。
その一例になるだろうか。朝日新聞は北海道での新聞印刷・発行の一部を来年4月から北海道新聞に委託開始、おそらく1、2年で全面委託に切り換えるであろう。他の全国紙も追随する気配だ。戦後間もなくはじまった全国紙の北海道進出は、大きな転換点に差し掛かっている。
読売グループ(基幹6社)の16年度決算を見てみる。減益決算だが、6年連続で100億円を超える当期純利益を確保した。「押し紙」を抱えながらも確実に利益確保その“秘密”は、徹底した別会社化にある。印刷部門では九州、北海道の自社工場を一般印刷企業へ経営譲渡。制作部門の別会社化も業界の先陣を切った。
新聞労連の組合員減の話に戻りたい。新聞産業に携わる労働者は、果たしてどれだけ減ったのだろうか? 新聞発行本社員は急激に減少しており、本社員だけで組織されている組合員も同様だ。しかし、業界に関係している新たな労働者は増え続けていることを忘れてはいけない。
鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)
東京芸術座「父を騙す--72年目の遺言」は、人間魚雷「回天」特攻隊の体験をした世代から現代に伝えるという意味で貴重な舞台であった。「回天」とは超大型魚雷を転用し、特攻兵器にしたもので、一人で乗り、脱出装置はなく一度出撃すれば攻撃の成否にかかわらず乗員の命はなかった。原案=安保健、作・演出=北原章彦。
横田家の三世代、六人家族の物語。祖父の認知症が進み、祖母が転倒して入院する。家族での介護は行き詰まる。父と母は、祖父母を騙してグループホームヘ入所させようとする。そんな時、祖父が孫に日記を託す。そこには、「回天」特攻機で突撃死した戦友と生き残ってしまった自身の壮絶な戦争体験が記されていた。
主人公は孫の優(藤原千晶)。冒頭、優のタブレットから、「ゴジラ」のテーマにのって亡霊たちが海軍体操を始める。鮮烈なイメージを与える快調なスタート。後半の「回天」出撃シーンでもこの亡霊たちは暗躍する。
前半は家族の認知症を巡る対応だが、優が祖父から日記を受け取ってからの後半は「回天」の出撃基地に変化する。祖父・影の旧姓は平田で、親友が横田一郎だった。「回天」の出撃で一郎は戦死、影は機械の故障で出撃できなかった。そして、一郎の妹・五月と結婚し、養子になっていたのである。藤原千晶は孫と若き日の一郎の二役で奮闘していたが、力が入り過ぎたようでやや難点が感じられたのが惜しい。ベテランの北村耕太郎、芝田陽子、柳瀬龍洋などが実力を発揮していた。(一部Wキャスト)戦中の軍歌を女性コーラスで聞かせた意図には疑問を感じた。簡潔な舞台セット(幡野寛)と、音楽(洪栄龍)、照明(関定己)などとのコラボが効果を醸成していた。
=新宿・紀伊國屋ホール、8月16日所見=
韓国の朴槿恵大統領が弾劾裁判に追い込まれました。追い込んだ力が、どこから来ているのか、当初、分かりませんでした。13に及ぶ容疑があるようですが、その一つが知人の「裏口入学」関与です。それなら「裏口入学」を取り消せばいいのではないかと、素人としては思っていました。財閥と組んで、いろいろな財団を作った、これもよくないことではあるがざらにあることです。それにたいして、韓国の人たちは230万人も広場に集まって反対しました。ハンギョレ新聞の記者の話を聞いて、その理由が分かりました。
韓国は日本が戦争に負けて、植民地から解放されました。しかし、冷戦のあおりを受けて、朝鮮は南北に分断されました。その後、韓国は軍人の独裁国家になっていきました。全斗煥の時代、軍事政権のクーデタに反対し民主化を求める学生デモが全国に広がりました。20万人が参加した光州事件では、全政権の弾圧で約200名の学生が死亡し、多数の負傷者がでました。本当にひどい仕打ちを受けて、死んだわけです。全斗煥の軍事独裁の社会に国民が反旗をひるがえし、金大中さんが大統領になり民主主義国家をつくりました。
少し寄り道をしましたが、韓国人にとって、本当の誇りだといいます。東西の冷戦のあおりを受け干渉が強いなか、ともかく軍事政権を民主的な政権にした、たくさんの犠牲を払ったが自分たちの力でやりとげた、それが韓国人の誇りだったのです。その誇りを、朴政権が踏みにじり、元の独裁国家にしようとしている、法治国家でなく権力者が自由勝手に動かそうとしする、これに対する怒りでした。多くの犠牲を払って民主国家にした、もう独裁国家に戻したくない、その怒りでした。
ハンギョレ新聞の記者が日本人に「あなたがたの誇りはなんですか」と聞くと、百人中百人が、「戦後70年、軍隊は日本人を殺したこともなく、外国人を殺したこともない、これが日本の誇りです」と、保守も革新も言う。民衆が作った国を壊すことに韓国人はこれほど怒っているのに、平和憲法が破壊されようとしているいま日本人は何をしているのだ、と記者は言っていました。
共謀罪、加計学園問題で揺れているのに、安倍内閣の支持率は45%(6月)です。
教育の現場はどうなっているか。教育基本法が改悪され、教師への締め付けが強まっています。ある研究会で高校の教師が、「18歳の生徒に選挙権が与えられたが、教師は常に中立でなくてはならない。選挙に行けば、どこかの政党に投票することになり、中立ではなくなる。だから選挙に行くな、と言われているようだ。選挙に行ってもいいのでしょうか」と正直に言いました。それを聞いて私は、そこまで日本人の意識がおかしくなっていると、思いました。選挙権を行使することは国民の最高の権利です。最高の権利であるなら、なぜ、学校で、いろんな政党の考え方を語り、正直に、こういうことがある、ああいうことがあると、言ってはいけないのでしょうか。
私が『対話する社会へ』(岩波新書)を書いたのは、こうした社会への危機感からです。家の周り、お隣さんとの付き合いでも、みんな自己防衛でいっぱいです。みんなばらばら、個人主義の社会で自己責任をいわれ、自分の生活を守ることだけで精一杯です。子どもを持つ親は、子どもが競争社会の中で落ちこぼれると、非正規労働しかできない。だから、子どもをどうやって勝ち組に入れるかで精一杯です。それから、忙しくて「過労死」しそうな状態です。そういうことが周りにいっぱいあります。政治に関心を持つことができない、そこまで追い込まれています。
よく集会で、老人ばかりだ、との声があがりますが、老人こそ時間があるのだから、集まればいいのです。若い人は、保育園に迎えにいき、食事を作り、宿題を見て、時間がなく、集会への参加は無理です。老人こそ集まるべきです。とにかく、世の中は逆転しています。逆転しているのは、「あなたの意識が変だ」ということではなくて、逆転せざる得ないところに追い込まれているのです。
そういう社会の中で、憲法をまもるということは国際社会でも通用する普遍的な価値をもっています。護憲派の人たちは、世界に、誇りを持ってやっている、と言える人です。その逆に9条をなくそうと考えているひとたちは、国連や米国からも心配されています。人間としてまともな考えではない。自分を守るためには無関心が一番いいと思っている人たちが多い。また、「日本会議」のように、力によって、札束で顔をひっばたいて原発を作り、そういうことがいいと思っている人たちがいる。民主的な討論をやっていたら、いつまでも話がまとまらない、権力者がいっぺんに進めてしまうほうがいいと思っている。辺野古の弾圧で分かるように、国が決めたら、つべこべ言うな、というのが「日本会議」の流れの中にいる人たちです。そこで、護憲でも改憲でもない人たちに、護憲の私たちの考えを少しでも理解をしてもらう、そのために必要なのが「対話」です。
(文責・編集部)(次号に続きます)
戦後50年を迎えようとしていた頃、平和な50年の歴史達成をカウントダウンする気運が高まっていました。半世紀もの間、戦争という人類のもっとも恥ずべき行為をしないで人々は暮らすことが出来たのだ、という思いをかみしめて、もう世の中から〝戦〟は無くなるのだろうと思ったものでした。
当時、地人会の朗読劇『この子たちの夏』がいろいろな場所で演じられていました。あの戦争が子どもたちに何をもたらせたのか、観る者聞く者に「もう二度とこんな思いは!」と心に刻みつける舞台です。
実は、山口で文庫活動をしている学校つながりのお母さんたちが公民館の舞台に上り、『この子たちの夏』を朗読したことがありました。台本を手に取って練習を始めてみると、とにかく涙、涙で大騒ぎ。知らなかった惨事の苦しみの細部までが見えてくるのです。
しかし、地人会が地道に繰り広げてきたことの本意には今ごろ改めて、深く思い至った次第です。あの舞台は、心ある人々が苦しみながら呑み込まれていった戦争が、金輪際行われないのだと確認するための機会ではありませんでした。戦争のない50年を数える水面下で、折あらばと頭を持ち上げつつあった改憲派の並々ならない力を見抜いての非戦への訴えだったのでしょう。
すぐにイラク戦争が起こり、自衛隊が参加する事態となりました。今度は非戦を選ぶ演劇人の会が『ピースリーディング』の展開を始めました。日々報道される現地の状況にリアルタイムでスポットライトを当てた構成で、戦地の今を知らされました。
舞台の力は新聞の見出しの大きな活字やテレビで流れるキャスターたちの時に感情的に走りかねない伝え方とは違い、聞いた者はいったん内側で事の次第を受け止め、その後に自分との対話を経て「そうなのだ」と自己決定を促します。その思いは深くゆるぎないものになることを体験しました。
が、残念なことに、舞台を観る人はなんとも少ないですね。原 緑
ご参加ください。
安倍改憲を許さない意見交流会を行います。
支持率が急落する安倍首相ですが、9条改憲に執念を燃やしています。この野望を打ち砕くために、どんなことをすべきか。渡辺治さんの最新講演ビデオを見て、率直な意見交換を行います。
● 9月20日(水) 14時~16時半
● 新所沢公民態学習室5・6号
8月初旬の涼しさは何処へやら、暑さが戻ってきました。
▼国民の声に背を向ける安倍首相は退陣を
核兵器禁止条約が国連加盟122カ国の賛成で、史上初めて採択されました。被爆者の方々の血のにじむような72年の運動が実ったのです。しかし、日本政府は条約に反対し会議を欠席しました。8月6日広島、9日長崎で、安倍首相は「あなたはどこの国の総理ですか」と被爆者に詰め寄られました。国民の反対の声を無視し、秘密保護法、安保法制、共謀罪法を強行し、核兵器廃絶に背を向ける安倍政権は退陣させるしかありません。
▼安倍改憲を許さないために
1面で案内しましたように、9月20日、意見交流会を行います。いま何をすべきか、日頃思っていることを率直に出し合いましょう。多くのみなさんの参加をお願します。
▼憲法カフェ
自衛隊をどう考えるか、共謀罪法と関連する戦前の「治安維持法」の非道さ、憲法9条はどのように成立したか、明治初期に作られた五日市憲法とは…。憲法カフェで取り上げるテーマを世話人会で検討しています。リクエストを世話人までお知らせください。
▼映画「スノーデン」試写会
個人情報監視の事実を暴き世界を震憾させた米国家安全保障局員スノーデンを、オリバー・ストーン監督が映画にしました。11月に上映会が計画され、試写会が9月3日9時半から新所沢東公民館で行われます(無料)。