��؏��́u�������ז�����Θb�ɖ҃^�b�N���H�v

�@�֎��P�S�S���@�i2018�N7��3�����s�j
�~�c�@���ȁi���ЕҏW�ҁj
�@�Q�O�P�W�N�U���P�Q���A�Ē���]��k���s��ꂽ�B
�@���P�R���̊e���͂������傫�����ʂ������Ă��́u���ʁv����B���������́̕A���̕]�������Ȃ�����A������ċ�̐��Ɍ�����Ƃ��ė��ۂ����Ă����B
�@�Ⴆ�A�����R�ʂ̉��̑匩�o���́u��j���@�����܂����Ӂv�A�ǔ��R�`�Q�ʂ̓����������o���A�u��j���@�ۑ葽���@�k�̎p���@���ɂ߁v�A���o�R�`�Q�ʂ̉����o���A�u��j���@���ԉ҂����O�@�Ē��G�Ή��������o�v�A�А���������Ă��̂��Ƃ��w�E���Ă����B
�@�܂��A��������B
�u���ӂ͉���I�ƌ����ɂ͒���������ȓ��e�������v�u�������ꂽ�����������݂����ł́A�č�����k���}���K�v���������̂��傢�ɋ^�₪�c��v�B����ɂ́u���̌y�X�����ɂ͋��������ƂƂ��ɐ[���s�����o����v�u�d�v�Ȃ͖̂��������ꂽ�s���v��ł���v�B���́u���m�Ȋ���������H���\�v��������ĂȂ�����u��k�̐��ʂƌĂԂɒl�v���Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�@�����̎А������l�̗��ۂ�����B�u�ł��̂悤�����A���O�͑傢�Ɏc��v�u���������k���N���b�h�u�c�i���S�����؉\�ŕs�t�I�Ȕ�j���j�ɓ��ӂ������ǂ������͂����肵�Ȃ��v
�@�ǔ��А����A�u�]���Ɣᔻ���������錋�ʂ��ƌ����悤�v�Ƃ��Ȃ�����A�z���l�͔ᔻ�̕��ɌX���Ă���悤���B�u���O�����̂́A�g�����v�����L�҉�ŕĊ،R�����K�̒��~��݊ؕČR�̏����̍팸�Ɍ��y�������Ƃ��B�a���ɑO�̂߂�Ȃ��܂�A�������߂���̂ł͂Ȃ����v
�@���o�̎А������l�̘_�����B�u�^�ɐV���ȗ��j�����Ƃ݂Ȃ��̂͂܂������v�ƌ�������ŁA�������đ��̑O�̂߂��ᔻ����B�u�đ��͂��łɁi�k���N�́j�̐��ۏŏ�����]�V�Ȃ����ꂽ�B���H�̕Ē��ԑI�����T���A�ڐ�̐��ʂ��ł�g�����v�����̑O�̂߂�Ȏp�����A�k���N���I�݂ɗ��p�����Ƃ����Ȃ����Ȃ��v
�@�ȏ�̂悤�ɁA�S�����e���͍���̕Ē���]��k�ɂ��āA�ł��邾�����̐��ʂ���������ĕ]���������ƌ��Ă���悤���B�e���r�ɂ����Ă��A�o�ꂷ��R�����e�[�^�[�̖w��ǂ͓��l�̌��������Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v��ꂽ�B
�@�ł́A����]�����������������������߂Č��Ă݂悤�B�u��j���v�Ɋւ��镔��������ƁA����������Ă���B
�@���u�g�����v�哝�̂͂c�o�q�j�i���N�����`�l�����a���j�ɑ��Ĉ��S�̕ۏisecurity guarantees�j����邱�Ƃ���A�������ψ����͒��N�����̊��S�Ȕ�j���icomplete denuclearization�j�Ɍ��������łŗh�邬�Ȃ��ifirm and unwavering�j���ӂ��Ċm�F�����v
�@���u�R�@�Q�O�P�W�N�S���Q�V���̔�X�錾���Ċm�F���A�c�o�q�j�͒��N�����̊��S�Ȕ�j���icomplete denuclearization�j�Ɍ����Ď��g�ނ��Ƃ����v
�@�e���̎А����A�e���r�̃R�����e�[�^�[�������������낦�āA�b�h�u�c�i���S�����؉\�ŕs�t�I�Ȕ�j���j����̓I�ɏq�ׂ��Ă��Ȃ������j����M����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����B�܂苤��������2�x�ɂ킽���Ė�������Ă���u���S�Ȕ�j���icomplete denuclearization�j�v�ł͕s�\���Ƃ����킯���B
�@�������A���ׂĂ̎��҂��w�E����悤�ɁA�b�h�u�c�͙ˑ傩���G�Ȏ�ԂƎ��Ԃ�������B���L����j���e��~�T�C����p������ق��A�֘A�̌����{�݂���H��ȂǃC���t���̉�́A����ɂ͊J���ɏ]�������Ȋw�҂�Z�p�҂̏����ȂǁA�R�ς���������ׂď������Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B
�@����ɂ́A�P�O�N�A�Q�O�N�̍Ό���v����Ƃ����̂����������̔F�����B���������āA�����А��������悤�ȁu���m�Ȋ���������H���\�v�������Ƃ����v�����̂��̂��A�����_�ł͂ǂ������蓾��͂����Ȃ��̂ł���B
�@����]�͐��E�����������钆�ŁA�u���S�Ȕ�j���v�Ƃ������t������Ԃ��L���ꂽ���������ɏ������A���̎��s���B���̐���ɂ��ƂÂ��āA���ꂩ�炻�́u�H���\�v�������̐��ƏW�c�ɂ���č쐬����A���s����Ă䂭�̂ł���B
�@����̎�]��k�ɂ��ǂ���܂łɂ͂V�O�N�߂����j�ߒ�������B���̊��ɉ������ő�̎����i���ԁj�͕č��Ɩk���N�����܂Ȃ����ݓI�Ȑ푈��Ԃɂ���Ƃ������Ƃ��B���̂��Ƃ�[�I�Ɏ����Ă���̂��A���N���{�����ČR�Ɗ؍��R�̍����R�����K���B���z�G���͂������k���N�ł���B
�@�e���r�ł悭���邻�̍����R�����K�̌��i�́A�C�݂ł̏㗤���̉��K�ł���B�z�肳��Ă���C�݂͂ǂ��̍��̊C�݂��H�@�k���N�̓��{�C���̊C�݂ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@���āA�����������ݓI�푈��Ԃɂ��Ȃ��āA�k���N�͂P�O�O���l�̌R���ێ����Ă����B�l���Q�T�O�O���̍��ŁA�����Ƃ��ē�������̐s�N�P�O�O���l��Y�I�ȌR���̒��ɕ����߂Ă����̂������ɉߏd�ȕ��S�A�����ł��邩�A�l���Ă݂�܂ł��Ȃ��i���Ȃ݂ɓ��{�̎��q���͐l���P���Q�T�O�O���l�ɑ��ĂQ�T���l�j�B
�@���̏�ɒ��N�ɂ킽�荑�A�̌o�ϐ��ق��āA�k���N�̌o�ϓI�����͂��܂�̂��҂��Ȃ�Ȃ��Ƃ���܂Œǂ��߂��Ă���B�l�X�̋���ׂ��Q�����̏́A�R��`������ł����܌���Ƃ��肾�B
�@�k���N�����������R���I�E�o�ϓI�ꋫ����E���邽�߂ɂ́A�푈��Ԃ̌p���ɏI�~����ł��A���̑S�͂������Čo�ϕ����ɂƂ肭�ނق��ɓ��͂Ȃ��B
�@����ɂ́A�č��E�؍��ƌ����āA���݂̒�틦���j�����A�V���ɕ��a�������Ԃ����Ȃ��B���̂��ߖk���N�͈�т��ĕč��ɍu�a�̂��߂̒��ڑΘb���Ăт����Ă����B�������č��͂���ɉ������A�k���N�Ƃ̑Θb�����ۂ������Ă����B�Ȃ����B�č������̔e����`�I���E�헪���ێ����邽�߂ł���B
�@����ȍ~�A���卑�E�č��́A�u���E�̌x�@���v�Ƃ��ĐU�镑���Ă����B���̃V�F���t�̒n�ʂ�ێ����邽�߂ɂ́A���E�̗v���A�v���ɌR����n���m�ۂ��A�����Ɏ����̌R��z�u���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�����Ă��̂��߂ɂ́A��ɌR���I�ْ���Ԃ�ۂ��Ă������Ƃ��K�v���B����������A��ɉ��z�G��ݒ肵�Ă����K�v������B���ė�펞��ɂ́A�\�A�����z�G�������B�������P�X�X�P�N�Ƀ\�A�͏��ł����B�����Ƃ͂P�X�V�O�N�ォ�獑�����J���A���łٖ͋��Ȍo�ϋ��͊W�ɂ���B�Ȃɂ��뒆���͕č����{�̔��s���鍑�̍ő�ۗ̕L���Ȃ̂��B�č��̃h���̉��l�͒����̎�ɂɂ����Ă���Ƃ�������B
�@�ł́A����̖k���A�W�A�ɂ����āA�R���I�ْ��̐k���Ƃ��Đݒ�ł���̂͂ǂ����H�@���܂��ɐ��ݓI�푈��Ԃɂ���k���N�������đ��ɂ͂Ȃ��B���́u�k���N�̋��Ёv�����邩�炱���A�č��͊؍��ɂR���A���{�ɂT���̕ČR��z�u���Ă������Ƃ��ł���̂ł���B��������ؗ����Ɂu���Ӂv����Ȃ���B
�@�����������Ɛ헪�������āA�č��͖k���N�����틦��̔p���Ƃ��̕��a���ւ̓]�������߂��Ȃ���A��т��Ă�������ۂ������Ă����B
�@�k���N���Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ͂킩���Ă���B���������āA����ɗv�����邾���Œ��ڑΘb�������ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�č���Θb�̃e�[�u���Ɉ�����ɂ́A�����I�ȗ͂��֎����Ă������Ă邵���Ȃ��B
�@�����l���āA�k���N�͍��������̋������]���ɂ��Ȃ���A�܂����E��������𗁂сA���ق��Ȃ�����A�j����ƃ~�T�C���̊J���ɖv�����Ă����̂ł���B�j�ƃ~�T�C���̑Ώۍ��́A������A���߂���č��ȊO�Ɋᒆ�ɂȂ������B
�@���̊j�Ƒ嗤�Ԓe���~�T�C�����A�k���N�͍��悤�₭��ɂ��邱�Ƃ��ł����i�ƕč��Ɏv�킹��i�K�Ɏ������j�B
�@���̌��ʁA���ɕč��哝�̂������قȃL�����N�^�[�̎�����ɑ������Ƃ������Ƃ������Ĉ�꒼�ڑΘb�̏�ɓo�ꂵ�Ă��ꂽ�B�K�^�ɂ��A�k���N�����w���҂̔O�肪���ɂ��Ȃ����̂ł���B�i�U���P�S���L�j

�@��n�����f���铌���A�����H���݁A�A���e�i�̌��đւ��A�w���R�v�^�[�̕p�ɂȔɂ�鑛���ȂǁA����ČR��n�ւ̊S�����܂�Ȃ��A�T��26���A���،����قŁA�s�̊�n���o�Ȃ��āu�o�O�u���v���s���܂����B��Ấu�����n�����l�����v�B�p�ӂ����������Ȃ��Ȃ�A��ꂢ���ς��̂P�R�O�����Q�����܂����B
�@�J��̈��A�ŌĂт����l�̐�������́A��n�Ԋ҂̗��j��U��Ԃ������ƁA�������H���݂��@�ɕς������n�̌���A�S�ʕԊ҂��ǂ��������Ă������A�݂Ȃ���Ƃ�������ɍl���Ă��������Ƃׂ̂܂����B�����đ̑�ق���A����44�N�ɊJ�݂��ꂽ�����s��̕ϑJ�A���̕ČR�ɂ���n�ڎ��A�s���^�������܂�Ȃ��ł̈ꕔ�Ԋ҂������������ƁA�������H�̍H�����e�Ȃǂɂ��āA�p���[�|�C���g���g���ďڂ�����������܂����B
�@���̌�A���^�ɓ���܂������A�͂��߂Ɂu�l�����v���܂Ƃ߂�����E�v�]�T�_�ɂ��Ẳ�����܂����B
�@�@�s�̕��S���S������17���~�ɂȂ����̂͂Ȃ��H�i�F�S���́A�����A�Œ���K�v�Ȃ��̂Ƃ��č������ς����z�B���H���ݔ�͊܂܂�Ă��Ȃ��B����27�N�x�ȍ~�A�ڍאv���A���ϊz��17���ɂȂ����B���H���ݔ�A�h�ΐ����̓P����A�V�ݑq�ɂ̌��ݔ�A�ė��ϑ����A��n�^�c�p���H���E��ȂǁB���̊Ԃ̎��ޒP���E�J���P���̍���)�A
�A�@��n�ێ��̂��߂̔�p���S�́H(�F�s�͕��S���Ă��Ȃ�)�A
�B�@��ԁA�w���R�v�^�[����ɂ�鑛�����Ђǂ��B�@��̊m�F������肷��\��́H(�F����l�̔��f��A�@�I����Ȃ����ߎ��{���Ă��Ӗ����Ȃ�)�A
�C�@���H�J�ʂɂ���ʗʁA�M���̐ݒu�Ȃǂ̑�́H(�F��T�U�O�O��Ǝ��Z�A�M���͓��H�̏o�����E�������̂R����)�A
�D�@��n���ӂ̕������L���Ăق����i�F�s���̕��������������i�߂Ă��ė\�Z�������Ă���A�����ɂ͓��)�B
�@����ɎQ���҂���́u��n���̗�p���̉������邳���v�u�w���R�v�^�[�̔��{�����A�P�T�O���[�g���̍����������j���Ă���A�������Ђǂ��v�u���H�ƕ����̎d�l�́H�v�u�H�����e���s�̍L��Œm�点�Ăق����v�u�������̑�őS�ʕԊ҂������������v�u��n�̋����E�Œ艻���͂����A�S�ʕԊ҂����̂��̂ł́v�Ȃǂ̎����ӌ����o����܂����B�܂��A�A���P�[�g�ɂ́u��n�H���̑S�̑��������Ȃ��v�u���H�J�ʂɂ��o�ό��ʂ́H���̕��S���܂߂�70���~�����ď���s���ɂǂꂾ���̌��Ԃ肪����̂��v�Ȃǂ̊��z�����܂����B
�@�Q���Ԃɂ킽���čs���܂������A���܂��܂Ȍ��O��s�����������ꂽ�Ƃ͌������A����̍u�������߂鐺���オ��܂����B(�����r�A)
���c�݂��q�i���ꌧ�{�����ݏZ�j
�@�T���Q�U������R���Ԃ̓����Łu�Ӗ�Óy�����o���ΑS���A�����c��v�̑�T�����s�ŊJ�����B�����Q�T���͖�����J����A���s�ψ��������C�^�[�̉Y���x�q����Ɠ�l�̐��łƂ߂鎄�́A�Ƃɖ߂�����̂P�O���ɂ��̒ʐM�������n�߂Ă���B
�@�u�̋��̓y���͈����Ƃ��Ӗ�Âɑ���Ȃ��v�Ƃ����X���[�K���́A�����{�𒆐S�ɂW���Q�O�c�̂��q�����B�e���Ŏ��R�ی�^���𑱂��Ă����O���[�v�������A������\�͈��Q���̈����x�q����(���˓��C��c)�Ɖ����s�̑�ÍK�v����(���R�ƕ�������鉂����c)�̂���l�ł���B
�@�����������������͈����x�q���T�N�O�ɓߔe�̃z�e���Ŗڂɂ��������V��̋L���������B�ޏ��́u�Ӗ�Óy�����B�P�R�O�O���~�v�u�̎�ꏊ�͐��˓��C�ȂǂX��������v�̕����ɂт����肵�A�u���̔������Ӗ�Â̊C��푈�̂��߂ɖ��ߗ��Ă�A����������Z�ސ��˓��C���璲�B����Ƃ́I�@���͂R�O�N�߂��w���˓��C��c�x�Ő��˓��ߗ��Ă�C���̎悩���邽�߂Ɋ������Ă��Ă���̂ɁA���ꂪ���݂ɂ�������肩�A������Q���邱�ƂɂȂ�c�c�����Ȃ��Ǝv���܂����v�Əq������B�����Ċe����K�ˁA�W���̒c�̂̋��^�邱�Ƃɐ����A�u�Ӗ�Óy�����o�����v�Ɍ��������B
�@��N�A�k��B�s�ŊJ���ꂽ��S��ɏo�Ȃ������́A���茧�̖̉�炳��̕Ɋ��������B����́A���茧�̒S���ۂ��u���ꌧ����v����������͂���v�Ƃ������̂������B���ꌧ�͉ߏd�Ȋ�n���S�������t�����Ǘ����Ă���ƍl���鎄�ɂ͖]�O�̊�т������B����ɋA���Ă����Ӗ�Â̏W��ł��̘b���Љ�A���c�����ɂ��`�����B���ЁA���ꌧ����e���ɋ��͗v�������Ăق�����S�������B
�@�������A�P�N�o���Ă����ꌧ����̗v���͏o����Ă��Ȃ��B�����̖�����ł́A���̖��̉����Ɍ����ĔM�S�ɋc�_�����킳�ꂽ�B��N�̂V���ɂ́A�����x�q����̑��Ƀs�[�X�f�|�O��\�̓����Y����ƕӖ�Âœ������y�؋Z�t�̖k��c�B���A���c�����ƌ��̒S���ۂɐ������Ă���B����̑S�������I�����闂���̂Q�X���ɉ����m���Ɩʒk������j�ŁA���ꌧ�Ɠy�����o���̘A�g�̉\���ɂ��Ęb�������B
�@�e�n�ŃR�c�R�c�Ɖ���̂��߂Ɋ������Ă���ꂽ���������ꓰ�ɏW���A�V���̖{�i�I�����čH����ڑO�ɂ��ĉ����m���ƘA�g��b�������B�u����͌Ǘ����Ă��Ȃ��B�S���ɐ^���ɍl���s�����Ă���Ă���l�тƂ�����v�B����̓��N���N���Ė��ꂻ�����Ȃ��B
�O���i�P�S�R���j�́u����ʐM�v�ɁA����č�N�V���̌f�ڕ����ڂ��Ă��܂��܂����B���c����A�ǎ҂̊F����ɐ[�����l�т��A�O�����M���������Ɍf�ڂ��܂��B
�j�@�s�O�Y�i�f��v���f���[�T�[�j
�@�������̑n�݂���T�O�N�ڂ��@�ɁA�������͕�������̑����I�Ȑ��i�ƕ������̋@�\�����̂��ߋ��s�ړ]��{�i�������Ă���B2021�N�x�܂łɑS�ʈړ]���v�悳��Ă��܂��B�@���I�ŕ�������W�c�Ƃ��Ă̐V�E��������ڎw���A�V���ȕ����|�p�����ւ̎Љ�I�E�o�ϓI���l����ޕ�������ւ̓]�����͂�����j�ł��B�����A���s�ړ]�ւّ̐��ɔ����镶���W�҂���������A�������͐^���ɔ��Έӌ��ւ̐T�d�ȑΉ������߂��܂��B
�@���āA�Q�O�P�W�N�x�̕������\�Z�͂P�O�V�V���~�ƑO�N�x�R�S���~���ł��B���̒��g�́A�V�K�ɕ������Ɉڊǂ���鍑���Ȋw�����ى^�c���t���̂Q�V���~���g�ݍ��܂�Ă���A�����̑��z�͂V���~�ł��B
�@�Q�O�P�W�N�x�\�Z�̓����́A���{�̕��j���āA�ό��╶�����̊��p�ɂ��u�҂������v���ł��o����Ă��邱�Ƃł��B�����|�p�n�������̌��ʓI�Ȏx���Ƃ��ē��{�f��U���\�Z�i���f�C�A�|�p�U���̃A�j���[�V�����f�搻��x���͊܂܂��j�́A�X���U�S�O�O���~�ƑO�N��P�W�O�O���~�̑����ƂȂ��Ă��܂��B�f�敶�����䂪���̑��݊������ߓ��{�����̑��i�A�܂��A�f�悪�C�O�ւ̓��{�������M�̗L���Ȕ}�̂ł���Ƃ̔F���ł��B
�@�������A�u���{�f��̑n���E�𗬁E���M�v���f�����������ڂł���D�ꂽ���f��A�L�^�f��̓��{�f�搻�슈���x���ɂU���P�R�O�O���~���v�コ��܂������A���̓��{�f��x���Ώۍ�i�Ƃ��Č��f��ւQ�P��i�A���ۋ�������x���ւS��i��\�肵�Ă��܂��B���A�L�^�f��͂P�O��i�̎x�����\�肳��Ă��܂��B�������A�������N�O����{�i�I�Ɏn�߂�ꂽ���ۋ�������ւ̐��쏕�����A���̐���x�����ƂɊ܂܂�Ă��܂��̂ŁA�����̐��쏕�������̕������I�Ɍ��z����邱�ƂɂȂ�܂��B���{�f��̖��͓I�ȑ��l���̊g��ɋt�s���鎖�ł���A�啝�Ȑ���x���\�Z�̊l�����s���ł��B���̐��쏕�����ւ̕������ւ̗v�]�^�����������ׂ��Ǝv���܂��B
�@�X�ɁA�䂪���̒��������Ђ�Ɨ��n�̍���̍ő�̔Y�݂́A�n��@������鐻���̃t�@�C�i���X�̍���ɂ���܂��B�������̐���x�����Ƃ̍�����Ղ̉��P�Ƒg�ݕς����d�v�ł��B
�@����ł́u���{�f��̑n���E�𗬁E���M�v�̋�̓I���g���l�@�v���܂��B�䂪���̉f��E��S���V���Ȑl�ވ琬�̎��f���ƈ琬���ƂƂ��āA�u�h�o�n�f���Y�ƐU���@�\���������̈ϑ������A����f��ē̔��@�ƈ琬��ڎw���x�����ƂɂP���Q�R�O�O�����v�サ�A��w�E���w�Z���Ɖf��W�c�̂Ƃ̘A�g�̍s����w���C���^�[���V�b�v�l�ވ琬�x�����x�ւS�P�O�O���~�̗\�Z�ł��B�����āA�A�j���[�V�����f�搻��ւ̎x�����ƂւP���Q�P�O�O���~�Ǝ����N�p���I���E�U�E�W���v�E�g���[�j���O��g�ݍ����ۂ̃A�j���[�V�������쌻��l�ވ琬�Ƃ��ĂQ���P�O�O�O���~���\�Z������Ă���B���̂悤�ɂQ�O�P�W�N�x�̕������\�Z���l�@����ƁA�f��\�Z�͍�N�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��\�Z�K�͂ł����A���h�i�R���j��̑啝�ȗ\�Z�̐L�тɔ䂵�ė]��ɂ��Ⴂ�\�Z���ƌ����܂��B�Q�O�P�W�N�x�̗\�Z�K�͂ł́A�f��l��|�p�c�̂���̗v���ɂقlj����\�Z�z�ł��B
�@�Ō�ɁA���{�̒��������Ђ�C���f�B�[�Y�̍���̍ő�̔Y�݂́A�����̃t�@�C�i���X�̍���ɂ���܂��B���ꂩ��̑��l�ȓ��{�f�敶���̑n���ƕ��y�Ɋ뜜���������܂��B���A�����|�p��{�@�̎�|�֔�������̂ƍl���܂��B�f�搻��҂Ƃ��ĕ����\�Z�̑��z��ɗv�]�������Ǝv���܂��B

��ؑ��Y�i���l�E�������C�^�[�@���V��ݏZ�j
�@���c�I���U��E���o�̐V�삪�ʔ����B�N�c�́u���{���w�����L�v�ł���B��������Y�̓������������삾���A�Ɠ��̕�������グ�����͂͑債�����̂ł���B
�@���S������ꂽ�̂͂S��\���̂��ׂĂ��A���l�̒ʖ邩���V�ō\������Ă��邱�ƁB���u�k�����J�̒ʖ�v�i�P�W�X�S�N�S���j�A���u�����q�K�̒ʖ�v�i�P�X�O�Q�N�X���j�A�O��u��t���l���̑��V�v�i�P�X�O�X�N�U���j�A�l��u�Ėڟ��̑��V�v�i�P�X�P�U�N12���j�B�����E�吳�̎���A����炪���܂��Ȃ����Ă����d�g�݁B��H���������L�����~�ŁA���X�ƗL���l���o�ꂵ�A���Ƃ����킵�Ă����B�����Ƃ��ɂ́A�Q�O�l�ȏ�̔o�D�����ꂼ��̗����ʒu�Ō��������������B���o�͂̍Ⴆ�ł���B
�@�B�X�����Ԃ�Ɉ��|�����B�X���O�i�R�����i�j�A�Ėڟ��i��������������ѕE�ōH�v�j���͂��߁A�����t�A�ΐ��A�k�����H�A�{���ȂǑ��m�ρX�A���]�����A�K���H���A�吙�h�ȂLjӊO�Ȑl���������B��ʂ����܂��Ȃ��̂��A�c�R�ԑ܁i���c�j�O�j�Ɠ��蓡���i��|���j�̖����B��l�̍D���őދ����邱�Ƃ��Ȃ��B�ؓ��ꡂœo�ꂵ���u��A���Y���ј\�̂��鏊�������Ă����B
�@���w�ւ̎v����l���ςȂǁA�v���v���Ɏ��b�Œm����G�s�\�[�h�����������N����B�q�K�̌̋��ł́A���v�w���̘b�肪�o��ȂNjɂ߂č����I�ȊS�����}������Ă���B���{���w���₪�ċ@�B���������������オ���邱�Ƃ��������B�����Ō�������{�̕��w�j�ł��������B
���g�ˎ��E�g�ˎ��V�A�^�[�A�U���W��������
��蒬�@���Y
�@�u�j�ڐ��̎��ʂ͎���x��v�u�P�O�N��̐V���ƊE�̓��������l����v�|�|�V���ЂȂǂœ������������𒆐S�ɁA���܂��܂��܂ȍs�����͂��܂��Ă���B
�@��̂��������́A���c�~��O�������������̃Z�N�n����肾�B�u���c���v�����������ɁA�T���A�V���A�e���r�A�o�ł�t���[�����X�œ��������������u���f�B�A�œ��������l�b�g���[�N�v�����������B�e���r�����̋L�҂ɂ�鍐���ɗE�C�t������ƂƂ��Ɂu���܂����Z�N�n�����܂ނ���Ƃ�����l���N�Q���Ȃ��������ƌ��Ӂv�����Ƃ��Ă���B�l�b�g���[�N�ɂ͒Z���Ԃ̂����ɂR�O�Ђ���l�����ƃt���[�����X�������A���f�B�A�œ����₷���������邱�Ƃ��߂����Ă���B����́u���������łȂ��N���������₷���Љ����邱�ƂɂȂ���v�Ƃ̍l�����炾�B
�@�V���Ђ̐V�K�̗p�͂��łɏ������S�����A�����ʐM�͂Q�N�A���łU�������ƂȂ��Ă���B�������A�E����͋��ԈˑR�B����u���b�N���i������蔭�s�����������A�������̌����J�o�[���Ă���V���Ёj�ł́u�q�ǂ������Ă��]��P�\���鐧�x���Ȃ��A�]�𗝗R�ɎЂ����鏗���Ј��������v�ƘJ�g�W�̉�c�ō����B���Г��ł̒����Łu�����̂͂R�O��܂Łv���R�O�����߁A�������u�q��ĂƎd���̗����ɕs��������Ă���v���Ԃ���������ƂȂ����B
�@���������̘J�����͐��x��̉��P�ł��ނ��Ƃł͂Ȃ��悤���B����̏�������オ�鐺�́A�u�ς��Љ�A�������ς��ʉ�Ёv�u�j������ł���V���́A���͂⎞��x��v�ƌ��������A�������B�Ⴆ�u�ۊ��v�i�q�ǂ���a����ۈ珊�������j��u�v�w�ʐ��v�ȂNJS�̍������ɐ[���荞��ł䂭�L�����ǂ����肠���邩�A�����҂̈ꕔ�ł����鏗���L�҂̎��_�Ɩ��ӎ��͌������Ȃ��B�u�P�O�N��̐V���ЁA�ǎ҂̊��҂ɉ����鎆�ʁv�Â���ɏ��������̒q�b�Ɨ͂��������Ǝv���B
�@�S�����̈ꕔ�ł͐����A�o�ρA�Љ�Ȃǂ̕����ɏ������A���A�u�����Ǘ��E�̓o�p���R�O�N�܂łɂQ�T���ȏ�A�Q�T�N�܂łɂP�R���ȏ�v�ƖڕW��錾�����Ђ�����B���̎Ђ̌���͂X���قǁB�O�o�̃u���b�N���Ј��́A�u���ʂɁw�����Ƃ��đ���x�Ǝv���悤�Ȋ��o�����f����Ă����Ȃ��v�ƌ����J���Ă���i�J�g��Â̏�����c�����j�B�V���ҏW�̗v�Ƃ�������f�X�N�E�ł́A���|�I�������j���ŁA���̂悤�ȁu���Q�v���w�E���鐺���������Ă���B
�@�`���ɏЉ���u�����l�b�g���[�N�v�́A��Ƃ�J�g�̕ǂ�������I�ȉ^���Ƃ��Ĕ��W������B��ƂƂƂ��ɘJ�g���傫���E�炷��@��B
�@�T���ɐV���J�A���J�����W��ł���Q���҂́u�i�Z�N�n����J�������P�ɂނ��j�������甭�M���邱�Ƃ��厖�B�Ƃɂ��������Ƌ@����Ƃ炦�āA�v�������荞�܂���B����������A���Ԃ𑝂₷�B���Ԃ𑝂₷���������̈�J���g��������v�Ɣ��������B�V���J�A�́A�V��������ŘJ�g�����̂R�����������S�����A�Ɩ���N����B
����@����q�i�F�J�s�w�������ܐV���x�j
�@�U���P�Q���A���͓��{�v���X�Z���^�[�̋L�҉��ɂ��܂����B�Ƃ���͂Q�N�Ԃ�̓���J�B���i�F�J���ӂŊX�̘b���ǂ������Ă��鎩���́A�y���ŐH�ׂĂ���킯�łȂ��A�w�����ė��Ŕ�����킯�ł��Ȃ��B�w�ނ̂������n��E���O�W���[�i���Y���܁x�����̏W���Ȃ�Đ���₩�Ȃ��͎̂����ɂ͖����A�Ƃ��̓��͕s�Q���̕��ɌX���Ă��܂����B
�@���A�����Ăт����l�ł��闎���b�q�E���c�d�E�����M�Ȃǂ̏����ɉ�邩���Ƃ����~�[�n�[���_�͎̂Ă������B�܂��A�O���A�m�l����u����ȍÂ������邩��s���Ă݂���v�Ɠd�b���������Ă��܂����B
�@���̐l�͌F�J�s�́w��t���x���ҏW���Ă��܂����B���ʂɂ́u�{�̏Љ�v���̃R�����A���O�ɂ͐܁X�̖���ȂǁB��ǂł͌��N���k���玞���k�c�܂ŁA����Ƃ�����肨������y���݂ɒʂ��Ă��܂��B�ނ������ɁA���݂��Ɂw�ނ̂������n��E���O�W���[�i���Y���܁x�E������������B
�@���́u�������ܐV���v�͍�ʁE�s���W���[�i���Y���u���̌Ăт����l�ł���A����Ȃ��Ƃ���ŔӔN�̂ނ̂���Ə���������NJւ�����o�܂�b���܂����B�ނ̂���̐��_�����K���āA�������ƂŎЉ�ƂȂ����Ă���Ƃ��������₩�Ȏ����B��{�̓d�b�Ɍ���������܂����B
�@������A���̓��v���X�Z���^�[�ɏo�������̂́A�U���P�T�����ӎ���������ł��B�����q�q����́A�u�x��Ă����N�v�ł��鎄�ɂƂ��Ă��Ռ��I�ȃG�|�b�N�B������������ǁA����c�����߂��Ŗٓ����悤�Ǝv�������܂����B
�@���͍�������̏��������̂��D���ł����B���͊��c����̎����ԍH�ꃋ�|��ǂ��̏Ռ����Y����܂���B���̈�i�́u�����q�q�Ǔ����W�v�́w�A�T�q�O���t�x���v�������ׂȂ���A�d��̕��X�̈��A���Ă��܂����B�ӂ��ӂ����O�~�̕����͎��ɂ͏�Ⴂ�ł������A�����Ɋm���ɂ����܂̓��肪�����܂����B�𓊂������邱�ƁI
�@�W���r�[�W���r�[�A�O�`���O�`���`���B
���ւ̊O�Ńc�o���̖��������܂����B�p�ɂɔ�ь����p��ڂɂ��Ă͂��܂������A���ɑ����̏ꏊ�����߂��̂�������܂���B
�@�c�o���̗���Ƃ͉��N���ǂ��ȂǂƁA�N�������o�����̂ł��傤�B�������ȁc��������Ăق����Ȃ��̂�����ǁB
�@�c�o���͐l�̏o����̑����ꏊ�ɑ�������K�������邻���ł��B�܂��ɁA���փh�A�̏�B�����͑D��V��ɂȂ��Ă��镔���ŁA�J��������ʂ��͗ǂ��ƍD�����ł��B
�@�O�������Č��グ�Ă݂�ƁA�l�����Ă��|����Ȃ��c�o���̂��ƁA�ǂɐ����ɂƂ܂��Ă����Ƃ���������Ă��܂��B�ǂ��������̂��Ƙr�g�݂����Ă����̂ł����A�����ނ��𔗂�C���ɕ������̂��A��ы���܂����B�ǂ������A����ŋS�k�̂悤��ⴂ������Ēǂ����ɍς݂܂����B
�@�߂낤�Ƃ���Ƒ����ƂɁu�����v������̂ł��B�Ђ�`�A�ցB�c�o���̂�����̕��ւP�O�Z���`�������������āA������������Ƃ��ē����܂���B�ւ͎���ɗ����Ă��������ȓy�̉��ׂ����Ȃǂ���A�������n�߂邱�ƂɋC�Â��Ă����悤�ł��B
�@���쑺�̏d�S�y���̓y�͉^�Ԃ̂ɏd�����ł��傤�ɁA�c�o���͉ʊ��ɂ��d���ɂ��������悤�ł��B�Q���Ԃقnjo�ƁA�ǂɂ͓_�X�ƓD�̉h������Ă��܂����B
�@���\�N���O�̂��Ƃł����A���ڂɐ��A���o����Ƃ������A�����M�[���o�����܂����B����ȗ��A���ɂƂ��Ē��͖]�����Ŋy���ނ��́A���Ɋ���ė��Ăق����Ȃ��Ώۂł��B�C�̓łł������A�ǂɕt�����D�̉����菜���A����т��Ēʂ���ځB�D�ꕔ���ւ̏o������֎~���܂����B
�@���X���A���x�͐��ʏ��̏o������̏�ɑ������n�߂Ă��܂����B�����߂ɂ��������菜���܂����B���ꂩ�疈���A�l���̕ǂ��`�F�b�N���Ă���̂ł����A�����̓h�A���J���ė������Ƃ����T���_���̂��������[���R�ɂ��܂�Ȃ��Ďւ��c�B�����A�₾���I�@�����畗���ł͉��N���ǂ��ƌ����Ă��˂��B
�@���������āA�ނ��܂��A�_���ׂ����̂Ƃ��ăc�o���̑����`�F�b�N���Ă���̂�����B
���@��
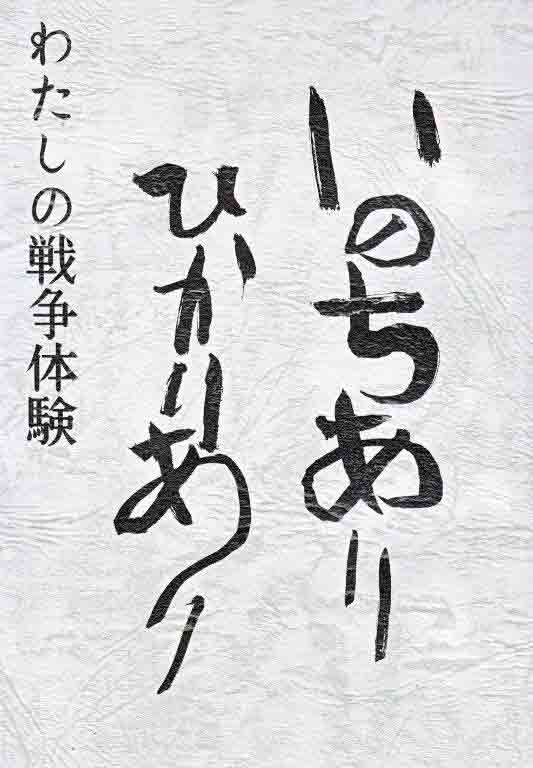
�@�u�X���̉�@�����܂����v���A�u�킽���̐푈�̌��@���̂�����@�Ђ��肠��v�����s���܂����B�������m�����Q�P�������M�B�Еz���i�T�O�O�~�B�X���̏ꍇ�͕ʓr�P�W�O�~������܂��B�w����]�҂͈ɐ��c�irokunigo@jcom.home.ne.jp�j�܂ŁB�������́u��v�̐��b�l�ɂ��\���o�������B
�@�~�J�̐���Ԃ̓������́A���炫��ῂ����������܂��B
���U��29���́u����v��55���Q��
�@�O���A�b�u�Q�Q�I�X�v���C���z������鉡�c��n�̌���ƍ���ɂ��āA��������ɏڂ������b���Ă��������܂����B�㔼�̑���ł́A���ꂩ��̊������߂����āA����ČR��n���A�Ē���k�Ƌ��������̈Ӌ`�A����Ƃ̘A�тȂǁA�����Ɉӌ������킳��܂����B�܂��A�V���ɁA��\�ψ��Ɍj�s�O�Y����A���b�l�Ɍ��c����A����r�q���A�������Ƃ��Љ��܂����B����̗l�q�͎����ŏڂ������܂��B�m�F���ꂽ�u���ꂩ��̊����ɂ��āv�u��v�v���A�������ɍ������݂܂��B
���u���{�X�������m�n�I�v�����P�R�T�O���l��������ɒ�o
�@�T�����̑�R���W��Ɍ����āu�S����ĊX��E�����T�ԁv���Ăт������A�������̉�́A�Q�W�A�Q�X���A�q������A�V����w���ŏ����Ɏ��g�݂܂����B�������킹�Ăׂ̂P�U�����Q���A���{�ւ̌������ᔻ�̐��Ƃ�������ɂP�O�T�M���܂����B�������̉�̏������͂X�U�V�M�ɂȂ�܂����B�U���V���A�S���ŏW�߂�ꂽ�P�R�T�O���l(��P����)�̏���������ɒ�o����܂����B���̌�������͏W�܂��Ă���A�ʏ퍑��I����A�W�����\�����\��ł��B
���X��A����ōu����
�@�Ē���]��k���������A���N�����̕��a�̐��̍\�z�A��j���Ɍ����đ傫�������o���܂����B����X��A����ł́u���A�W�A�̕��a���ǂ��������邩�v���e�[�}�ɍu������s���\��ł��B�u�t�A�����m�莟�您�m�点���܂��B