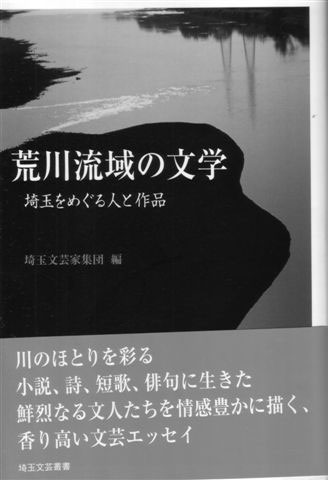機関紙15号 (2006年7月23日発行)
「軍隊を持たない国」コスタリカを取材して
藤森 研 (朝日新聞編集委員)
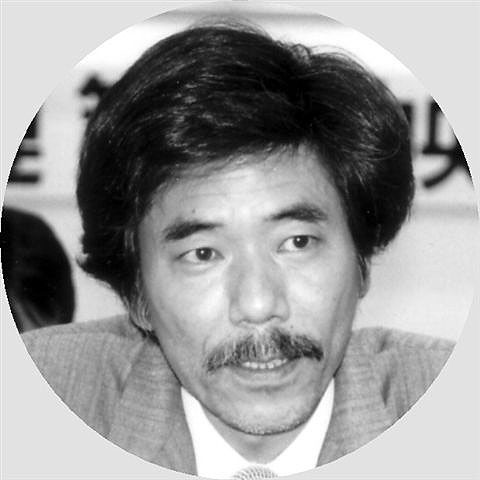
「寝ぼけちやいかんよ。憲法九条の戦力不保持なんて夢のまた夢さ」、「九条は理想だとは思うけど、残念ながら世界の現状では、まだまだ非武装は現実的ではないと思うなあ」そんな言葉をよく聞く。やっぱりそうかなあと思ってしまう。ただ、コスタリカという国は現に非武装政策をとっているともいう。本当なのか、本当ならどうしてそれが可能なのか、実際に行って取材してみた。
日本からコスタリカヘの直行便はない。米国のロサンゼルスかマイアミ経由で、10数時間かけて行く。もう赤道に近い地だが、首都サンホセなど人口の多い地域は高原にある。空港を降りると、しのぎやすい「常春」の気候だった。火山の多い高原地帯の風景は日本の信州に似ているように思った。

380万の人口の95%はスペイン系の白人かその混血だ。一人当たりGDPは4000ドル余り。バナナやコーヒーの輸出、いわゆる「デザート貿易」が主な産業だったが、最近、世界的な企業インテルの誘致に成功し、I Tが国の最重要産業となった。
さて、着いてすぐに聞いて回った第一の質問は「本当に軍隊はないの?」である。政府職員や学者、日本大使館の答えは同じで、「はい、ありません」。警察官は約1万人、沿岸警備隊もあるが小艇が数隻あるだけだという。「それじゃあ、海岸に敵が攻めてきても守れないじゃないですか」と聞くと、コスタリカ政府の職員は「もちろん守れませんよ」と涼しい顔で答えた。攻めてきたらどう戦うかに腐心するより、どこも攻めて来ない状況をつくることに精力を注いでいるのだと、後になって知った。
恒久的軍隊を廃止
コスタリカの現在の憲法が出来たのは、1949年、日本の3年後だ。選挙不正をきっかけに内戦が起きて、多くの同胞が死んだ。内戦に勝利した社会民主党の指導者ホセ・フィゲレスは、自らの率いる軍隊を解散し、新憲法の二一条に「恒久的な軍隊は廃止する」と規定した。なぜ、そうしたのか。
「最大の目的は民主主義を確立することでした。軍隊の恐怖の下で自由にものが言えるでしょうか。もう一つの理由は、軍備ではなく、教育や福祉に予算を注ぐためでした」
そう語ったのは故フイゲレス元大統領の妻のカレンさんだ。今も元気で活動している。「男の子が生まれたとき、『ああ、この子は軍隊にとられる心配がないんだ』と思える幸せは、世界の女性にとって共通の願いでしょう。夫の非武装の決断は、だれもしたことのない実験でしたが、大事なことは夢を持ち続け、実現の努力を継続することです」
それ以来半世紀以上、コスタリカは憲法を変えず、非武装を継続してきた。それにしても政情不安定な中米で、なぜ非武装政策の継続が可能だったのか。第二のこの疑問に答えてくれたのは、アルベルト・モンヘ元大統領だ。1983年に有名な「非武装積極永世中立宣言」をした人物である。
すべての人の避難場所
80年代、北の隣国ニカラグアの内戦は激化した。右派ゲリラを支援していた米国のレーガン政権は、コスタリカを自陣営に巻き込もうとして、飛行場建設の援助を申し込んできた。これに対し、時の大統領モンヘ氏は、「中立宣言」を世界に向けて高らかに発し、米国の圧力をかわすことに成功する。モンヘ氏はこう語った。
「宣言の直前にペンタゴン(米国防総省)の人間が来て、『宣言はやめてほしい』と言った。私は受け入れなかった。米国は複雑な国だ。ペンタゴンやタカ派は反対でも、議会は我々の立場を承認する方向にあった」
モンヘ氏の後を継いだ社会民主党のオスカル・アリアス大統領は「積極中立」路線を推し進め、中米地域の調停活動に尽力した。87年にノーベル平和賞を受ける。ニカラグア和平が最終的に実現する前に授賞が決定した背景には、レーガン政権をけん制しようとする欧州諸国の意思が働いていたとされる。
こうしたコスタリカ外交の特色を、富山大学の竹村卓教授は、1.米国内の動向の慎重な見極め 2.国際的な応援団(サポーター)獲得の努力 3.それを可能にした平和追求の持続的実践、とまとめている。
コスタリカ憲法は三一条で、「コスタリカの領土は、政治的理由で迫害を受けているすべての人の避難所である」と定めている。
人権を重視して政治亡命を受け入れる宣言だ。中南米ではクーデターが多い。亡命でコスタリカに恩を受けた政治指導者が復権する例も少なくない。結果として、近隣のあちこちの国の中枢に旧い友人が存在することになる。コスタリカを攻める国はますます無くなる。「情けは人の為ならず」なのだ。
人権重視が平和を強化し、平和の下でまた人権貢献や民主主義化を進める。そんな好循環を、コスタリカは意識的に追求している。コスタリカ最高裁の憲法小法廷は外国人の人権救済にも熱心だ。選挙の公正のための選挙最高裁という独特の制度も機能している。
隣国パナマも非武装政策
こうした普遍的価値での先進性が、世界から一目置かれて、国連平和大学や米州機構の人権裁判所はコスタリカに置かれている。そのことがまた倫理的威信を高める。「コスタリカを攻撃でもしたら、その国は国際世論から強い非難を浴びる」と言われるゆえんだ。
経済は米国の支配下にほぽあるといってよい。だが政治的には独自性を自負している。9・11テロの際、平和財団を主宰していたオスカル・アリアス氏は声明を発表し、哀悼を表しつつも米国民にこう呼びかけた。「非難すべきテロヘの怒りの中にあっても、憎悪と暴力には身をゆだねずにありたい」
アリアス氏は今春の選挙で、再び大統領に返り咲いた。
もちろんコスタリカにも、貧富の差など、多くの問題がある。だが、平和や民主主義や人権の価値を多くの国民が共通に認識し、その伸張に努力していることも事実だ。中米地域での人権向上の活動にも熱心に取り組む。10年ほど前から、南の隣国パナマも倣うように非武装政策に踏み切った。
コスタリカと日本は似た憲法を持つ国同士だが、違いもある。日本が再び非武装を目指すとしても、それは北東アジアの平和構築と並行しての段階的なものとなろう。
コスタリカの評価や、日本が何を参考とするべきかの考え方は、人によってさまざまだろう。ただ次の点だけは言えると思う。
「今の世界で非武装なんて、全く現実的じやないよ」と簡単に言う人がいるけれど、それは違う。現実にそういう国は中米にある。
コスタリカはこんな国です
◆世界で唯一の非武装永世中立国
◆国連平和大学及び地球評議会事務所設立
◆アリアス大統領(当時現役)ノーベル平和賞受賞
◆国家予算の21%が教育費(2000年度)
◆200海里経済水域を世界で最初に宣言
◆国土の約24%が国立公園(保護区)
◆地球上の全動植物種の約5%が生息
◆ペンショナート政策…年金生活者の受け入れ
◆世界人権裁判所
機関紙15 もくじへ
燈原の火のように広がる運動を再確認

「九条の会」発足2周年となる6月10日、同会として初の全国交流集会が、新宿区の日本青年館で開かれ、全国で活動する約900の「会」代表1550人が集まり、ぎっしり満員の盛況でした。
午前中の全体会議と午後は11の分散会で、「運動への悩み」、「いかに伝え拡げるか」、「地域での経験」などの活発な発言が相次ぎ、全国に「九条を守ろう」の運動が着実に進んでいることを如実に示しました。
「九条の会」は、同日、地域・分野別の「会」が5174に達したと発表しました。当会からは、3人が参加し、それぞれ分散会で「マスコミ・文化九条の会所沢」の活動状況を報告しました。
全体会議の前半、呼びかけ人の6氏が順に次きのように発言しました。
三木睦子さん、「憲法九条を守っていこうじゃないかという集まりにご賛同していただいてる方が大勢いて元気になります。運動を始めたのも、もう二度と戦争の苦しさを若い人たちに味わわせたくない思いからです。平和というものが世界にどれほど必要なものか。日本も世界も静かで楽しい世の中にしようではありませんか」。
鶴見俊輔さん、「かつて米国は文明の名において日本の戦争を裁き、今はイラクに戦争を仕掛けています。私は二つの国家に取り残された一人のもうろくの個人として戦争に反対します。さらに戦争を進め押し広げる日進月歩の文明に、もうろくの個人として反対していきたい。もうろくの個人としてできることの一つに戦争に反対することを選びます」。
澤地久枝さん、「私たちは希望を持たなければ1日たりとも生きてはいけません。希望を持ち続けることが困難な時代だから、いっそう希望を高く掲げて、市民たちが、それぞれの地域や職域において、憲法九条を守る努力を続けられ、日に日に増えています。いま私たちは新しいあけぼのにいるかもしれません」。
加藤周一さん、「2年前、『九条の会』をつくったときに、特徴が二つありました。一つは国民の意見と議会の中の意見が違うこと、議会の中では、改正が多数だけれど、国民の中では多数じやない。もう一つは、日本は市民運動が盛んだけれど、横の連絡がない。それにいくらか役に立ちたい。『九条の会』は上り坂です。勢いのある運動が勝ちます」。
小田実さん、「もっとも理想的であることが、もっとも現実的であることです。いま、昔に帰れ式の改憲論議は影をひそめ、逆に戦争の反省にたってまとめようという物分かりのいい議論が出ています。九条一項は残し、二項をやめようという、自民党案もそうです。改憲派の人は『自衛隊を軍隊と認めて憲法的に歯止めをかける』と言うが、いまでも勝手な行動をしている自衛隊を軍隊に認めたら、もっと勝手な行動をすると考えるのがリアリストです。非暴力の世界に向けて一歩でも進めることが、日本を守ることになります」。
大江健三郎さん、「憲法、教育基本法を読み返してみると、マッカーサー司令部や日本の旧支配層の思惑があったとしても受け入れた当時の日本人には倫理的想像力があったと思います。きょうは、独立した多様な声が重なり、憲法擁護のためのさまざまな運動が重なって、このような大きな結実を示していることを心から喜んでいます。私は悲観的人間ですが、倫理的想像力を考えること、憲法九条をいかに守るか考えることを続け、この運動にあわせて少しずつ声を発していきたい」と語りました。
後半は、「新潟・九条を守る阿賀野の会」、「千葉・小金原憲法9条の会」、「沖縄・大学人九条の会沖縄」、「大阪・府立夕陽丘高校九条の会」、「神奈川・横須賀市民9条の会」から、幅広い共同で活動を拡げる例が続々と報告され、参加者は、発言に聞き入りました。
機関紙15 もくじへ
長田道子 (子ども達の未来と教育を考える会)
政府自民党は、教育基本法「改正」案について念願(?)の「愛国」を盛り込みました。「“愛国心”と、“国を愛する態度”は同じではない」という小泉首相の詭弁を率直に受け入れるほど国民は愚かだと、稀代の独裁者に私たちは軽んじられているのでしょうか。教育基本法「改正」について訴えます。
強い国家意志が見え隠れ
多くの反対の声を無視したこの政府案は言うまでもなく、それ以上に“しっかりと”「愛国心」を規定した民主党案には、言葉もありません。政府でさえ公明党に配慮して少しは遠慮がちに表現した「愛国心」も、民主党は見事に明言しました。その案は、小泉首相に評価され、阿倍官房長官の“琴線”にふれ、「日本会議」の欲求を満たし、「国家護持」の復活を目指す右翼議員に喜びを与えたようです。このことは「民主党の本質を露呈してくれて立派!」とほめてあげるべきでしょうか。むろん、民主党案は論外ですが、政府案については、さらりと読むと、一般的には受け入れやすい、問題点を見つけにくい表現ですが、読み込むにつれて、子供達はもちろん、教師や家庭、地域をもある方向にからめとっていこうという、強い国家意志が見えてくるようです。
巧妙に言いまわされた教育への国家統制、教師・家庭・公共施設・地域にも及ぶ管理、そして何よりも、子供達への“国を愛する”態度の強制---それらひとつひとつは点ですが、それが線になった時、どこへ向かうかはおのずと明らかになってきます。
そもそも、人の心を操れると考えるほど傲慢なことはないはずです。「何を、どう愛するか」という根源的な精神の有り様まで法律で強制することを、本気で(?)具現化してしまうという、恐ろしくも不遜な人達が、経済界を含めて政治や社会の中枢をしめていることに、私達は怒るべきでしょう。
「逝って還らぬ教え児よ私の年は血まみれだ」とはじまる詩があります。終戦から、さほどの年を経ない頃に、ひとりの教師によって詠まれたこの痛恨の詩は、今、大きな意味をもって私達の前にあります。
彼が歌った「慚愧、悔恨、鐵悔」の念を、教え児を戦場へと駆りたてた教師だけではなく、多くの国民が深い共感をもって受け止めたことでしょう。その渦巻くような思いのなかで、「ニ度と戦争はしない」という強い決意をこめた日本国憲法と、それに則って、戦争中のような国家による教育統制を否定し、子供を平和な世界の担い手として育てることを規定した教育基本法を、未来を開く明るい道しるべとして、人々は迎えたのかもしれません。
しかし、平和への熱い思いは、今どこへいってしまったのでしようか。平和や平等を語ることは軽んじられ、かつては物陰から獲物の隙を窺うけもののようにこっそりと言われていた改憲論や教育基本法「改正」諭が、今やおおっぴらに足音高く迫ってきています。声高に叫ばれる「改正」論を容認してしまう状況が、今の日本にあるのでしょうか。憲法で規定されているはずの生存権や思想・信条の自由は保障されず、戦力を持ちながら「自衛隊は軍隊ではない」と詭弁を弄され、憲法前文さえも汚されてイラクヘの自衛隊派兵の根拠にされ、もてあそばされ踏みにじられて、憲法は満身創痍です。教育基本法もまた、行政の介入や「日の丸・君が代」の強制、競争原理の導入などで躁りんされ、まるで瀕死の白鳥です。
このような危機的状況にもかかわらず、憲法、教育基本法を空気のように“あって当たり前”と別認識もしない日常のなかで、しっかりと守り抜くことを、私達自身がしてこなかったのかもしれません。そして、「守ろう」という運動と思いを広げていく言葉を持ってなかったかも知れません。
さらに、大政党に有利な選挙制度のもとで国民は主権者たりえなく、「格差はあって当たり前、それを批判するのは、もたざる者のひがみ」とさえ公言する首相のもとで、税制、医療保険、老人保険、障害者支援、生活保護の改悪によって“富めない者”への締め付けはより厳しくなり、巧妙に権力に利用されているマスコミは、社会や政治の病巣をえぐろうともしない---。このような状況のなかで、多くの国民が悲鳴をあげているのだと思います。
子供の不安は大人と同じ
子供達の犯罪の増加が言われています。教育基本法「改正」論者は、そのような子供達の荒廃もその法律が原因だと、やくざの言いがかりのような論法で強弁しますが、決してそうではなく、子供達は、親を含めた大人達の生きにくさを敏感に感じとり、この社会での自分の未来を描けず、存在そのものが、とても不安なのかも知れません。大人達がそうであるように。
更に、自分を守ってくれるはずの“国家”が、「できん者はできんままで結構。無才は実直なる精神を養うだけでいい」という有名作家や、就学時の遺伝子選別を唱える科学者に代表される冷酷な子供観をもっていることを、直感で知ってしまっているのでしょう。自国の国民を愛せず悪意に満ちた“国家”と闘うために、たしかな言葉を持ちたいと、今、切に思います。
機関紙15 もくじへ
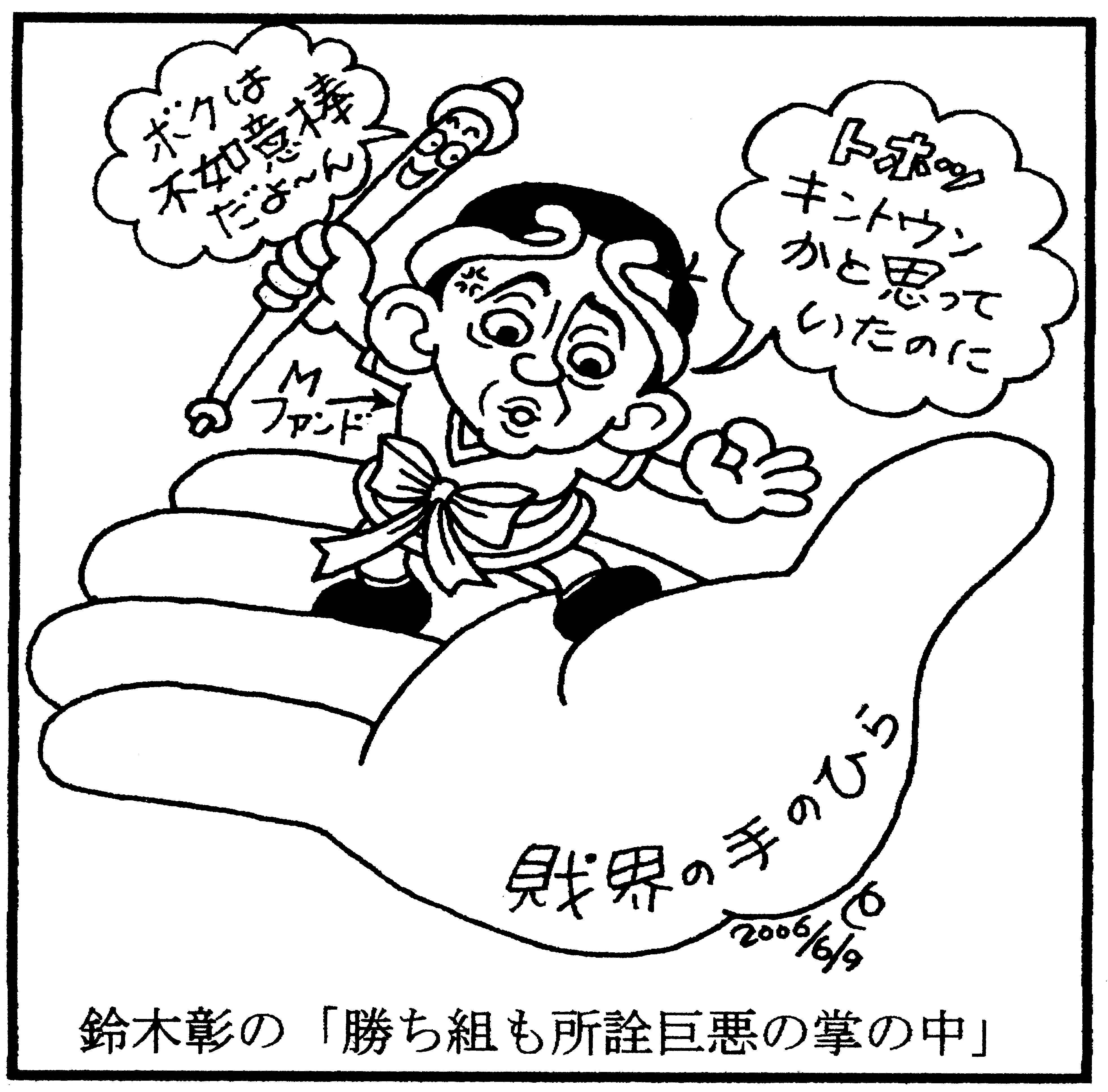 機関紙15 もくじへ
機関紙15 もくじへ
会場満員の155人が集う
日下部泰久
所沢市で6番目の「九条の会」が始動しました。松井在住10氏の呼びかけによる「松井九条の会」が、6月3日(土)松井公民館ホールで「発足のつどい」を開き、ほぼ会場いっぱいの約155人が参加しました。

つどいの冒頭、呼びかけ人の一人、元裁判所書記官の石山元信さんが「この会の設立を機に憲法九条のもつ意義を草の根から広めていきたい」と力強い開会挨拶をしました。合唱団「ききゅう」はピアノ演奏にのせて「ねがい」など3曲を美しいハーモニーで歌唱し、会場を魅了したあと、地元に住む彫刻家の田村興造さんが1時間以上、自らの戦争体験を語り、「上官の命令は朕の命令と思え」という狂信的な規律で固められた日本の軍隊の非人間性や理不尽さ、将来ある多くの生命を死に追いやった戦争責任がいまだ果たされていないことを、60年の時をへて、今なお湧き起こる怒りを露わに語りました。
また、呼びかけ人の一人、埼玉県弁護士会前会長の田中重仁さんは、「自民党新憲法草案が九条の改悪にとどまらない危険な内容(政教分離の骨抜き化、公共の秩序の強化、政党に対する規制など)を含んでいる」と指摘し、手続法として上程されている「国民投票法」を絶対に阻止する闘いを呼ぴかけました。
最後に、松井在住のエッセイスト、川北肇さんが自ら軍国少年に育て上げられた戦前の教育にふれながら、「そうした社会に二度とさせないために声をあげていかなければならない」と閉会の挨拶をしました。
なお、事務局からの入会とカンパの訴えに対し、当日入会24人(合計125人)、5万円をこえるカンパが寄せられました。「来てよかった」との感想も寄せられ、確信の持てる「つどい」になりました。これを第一歩に、憲法改悪阻止へむけてさらに取り組みを強めていかなければならないと決意を新たにしました。
機関紙15 もくじへ
勝木英夫 (マスコミ・文化九条の会所沢 代表)
この春、岩国市民は重要な回答を政府に突きつけた。どうして、そんなことができたのか、その訳を知りたくて、吉岡光則氏の話を聞きに出かけた(「平和のつどい」地区労など主催、6月8日、ミューズ・キューブホール)。
ご記憶のかたも多いだろう。今年3月11日、米艦載機の移駐受け入れの是非を問う住民投票が岩国市で行われ、移駐反対票が87.42%を占めた。(投票率58.68%)。圧勝である。周辺町村との合併を経、4月23日に実施された市長選挙でも、移駐撤回要求を公約に掲げた井原候補が68.06%を得て当選した。
報告者の吉岡氏は、山口県高教組の委員長もっとめられ、現在は「住民投票をカにする会」の会長。文字通り、このたびの住民運動をリードしてこられた人である。その報告を一言で要約するのは不可能であり、また失礼であろうが、「市民は政府のウソに気がついた」という言葉が記憶に残った。
同市では基地の滑走路を東側約1キロの沖合に移す工事が進行している。政府は、これを騒音軽減のためと説明してきたが、実は米軍機の移駐受け入れのためのものであったことが明らかになって、反対派が急増したということらしい。87.42%という数字は、たしかにそのような事情の介在を想定させる。
だが、吉岡氏も強調されたとおり、今回の米軍基地の再編は、日本と米軍の世界戦略により深く組み込むものであり、基地を抱える都市には、爆音だけでなく、事故、犯罪などの深刻な基地被害の増大をもたらす。このことを丹念に市民に周知させた努力が投票に結実したのであり、この点により多く留意する必要があるだろう。
わが所沢にも基地がある。物静かな基地だが、九条の精神から見れば、不要のはず。
機関紙15 もくじへ
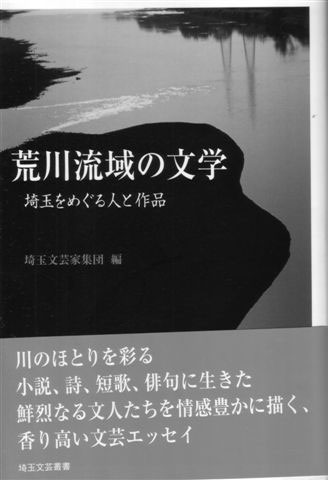
会員の高橋玄洋さん、中原道夫さんら、県内の文芸家約200人で構成する埼玉文芸家集団(加藤克巳代表)が、埼玉と作品を紹介した「荒川流域の文学」(写真)を出版しました。本は市内の書店で販売しています。
問い合わせは、さきたま出版会(048-822-1223)まで。
機関紙15 もくじへ
馬籠正雄 (ピースランナー)
今年も走ります。憲法を変える動きは、私の膝の治るのをまってはくれません。
7月12日(水)姫路市〜出雲街道を経て〜出雲市まで(268・3km)。
7月21日(金)出雲市〜山陰道を経て〜下関市まで(327・2km)
7月31日(月)下関市〜玄界灘を経て〜長崎(288km)
8月 9日(水)長崎市迄の29日間883・5kmです。
出雲街道は、ご存じのように後醍醐天皇島流しの古の道、1000mの四十曲がり峠。山陰道では内陸に入り「石見銀山」、金子みすずの長門市や吉田松陰の萩市。虹の松原や唐津・伊万里焼の玄界灘です。風光明媚なアップダウンのコースです。
無理せずにスケッチもしながら頑張ります。「平和憲法を守ろう・核廃絶」のチラシを配布しながら、署名を集め、山陰道を走り抜きます。
機関紙15 もくじへ
トップページへ
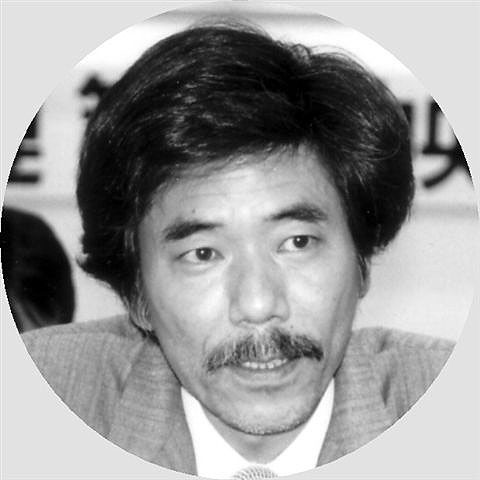


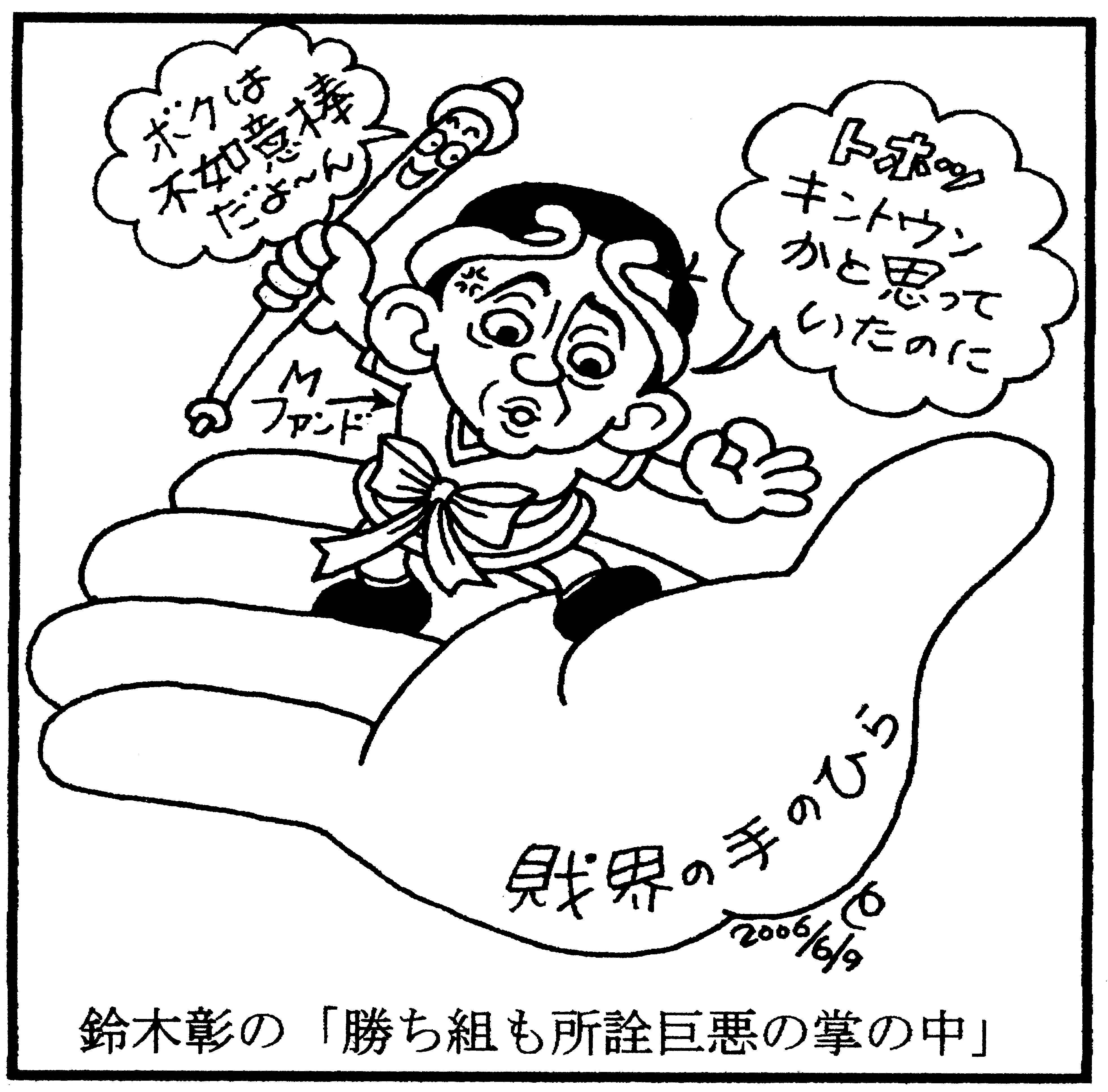 機関紙15 もくじへ
機関紙15 もくじへ