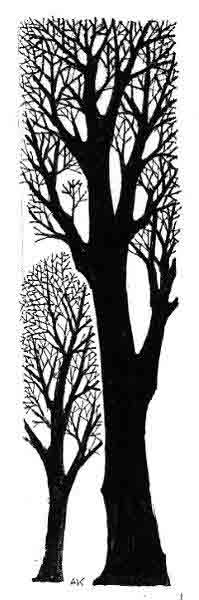機関紙99号 (2014年5月22日発行)
岡部 昭(彫金家・山口在住)

今から40年以上も前、私は北信州の標高1500mにあるカヤの平という高原に行き、初めてブナの原生林を見た時、その美しさは言葉には出来ませんでした。
アンデルセンの民話を生んだ森はブナの原生林だったということを思えばその美しさを想像できるでしょうか。氷河期が終わってから1万年間、ヨーロッパ大陸には産業革命が始まる前まで、このブナの原生林が広がっていたのですが、今その類まれな美しい原生林はまだ日本には残っています。
私がこの森に出会えたのはまさに偶然そのものだったのです。しかしそのころ政府機関はこのブナは全くの役立たずの木として、林学の学者達の提言で、皆伐を進めていました。その時地元の木島平村では役場と村民あげて反対していました。
私は具象に徹する美術家として、底知れぬ美には、深い深い哲学的真理があるに違いないと考えていて、身も心もその森に引きずり込まれました。しかし自由に伸び伸びと生きている森はそのままでは全く絵になりません。やがて森の皆伐も中止となりブナを守ろうという意見が全国に起こり、やがて東北の白神のブナの原生林が世界遺産登録となるのです。
私はこの森に行くたびに写生を重ね、7年も過ぎた頃、この森の美しいシルエットを利用した小品を作り、その後、絵になる様な形が少しずつ見え始め、出会ってから20年も過ぎた頃、一つひとつの若木も巨木も自由に幹と枝を伸ばしている形から、地球の重力に逆らって生きている形が見えてきました。
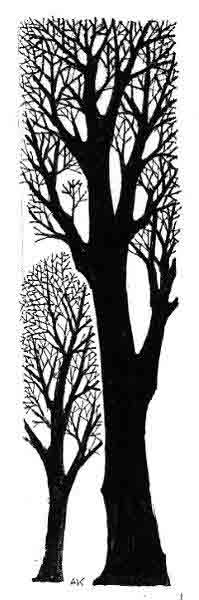
更に何年も経ったころ、何トンも何十トンもある巨木を支えている根っこが素晴らしく美しく見えて来ました。それまでは、根っこは気持ち悪くて絵にならないと思っていました。この木が重力に逆らう形の中に素晴らしい命の形が見えるのです。
今86歳を迎え、自動車の運転も6年前返上し、あの森には行けませんが、頭の中に詰まった記憶で作品を創り続けています。
私達人類をはじめ動物植物の生命とその進化を支えてくれた森に対して、私は心から尊敬と愛着を持ってこの森を作っています。
●地球の叫び
近世人類が物質的幸福を追求してきた結果、空気中のC02濃度はこの150年の間に、0・03から0・04に増加し、今迄にはない暑さは誰でもが実感しているところです。
気温上昇により、今シベリヤやカナダの永久凍土の解氷が始まると、ついこの前まで予想もしなかった、何万年も前の腐蝕植物の分解が始まり温室効果がC02の20倍もあるメタンガスの放出が始まり、更なる気候変動の加速が予想されます。近い将来、人間の浅知恵では予想も出来ない新しい現象が現れないか不安です。
この想定外の現象を私は人間に対する地球の反逆と考えています。この不安の全てを込めて森を作るのです。
7世紀百済から仏教と共に日本に渡来してきた彫金も今終焉を迎えようとしています。私を最後の一人という人もいます。私は今、百済人が法隆寺に作った高さ5mを越す灌頂幡、仏教の素晴らしい未来を願ったこの様式で、私達人間の幸を願い込め、彫金美術の最後を飾ろうと思い7作目の灌頂幡(『命溢れる森【2】』高さ3m)を作りました。
もくじへ
畑中 繁(牛沼在住)
ラジオ深夜便で「24時間いつでもどこでも安心をお届けするNHKのラジオ放送。NHKのラジオ放送は皆様の受信料で成り立っています」と女性アナウンサーの声が流れる。皆様の受信料だから皆様のNHKとなっているのでしょうか。
かつて、NHKは日本軍のお先棒を担ぎ戦争を先導し、戦況をあたかも皇軍が勝っているかのように伝え、日本国民だけでなく、東南アジアの人々に甚大な被害を与えた。
福島原発事故の時、原発推進派の御用学者を集め、深刻な問題など起きていないと隠蔽し、初期報道が「大本営発表」を彷佛させると国民の批判を浴びた。「権威」というお墨付きを盾に、発表記事に依存し、公正なジャーナリズムから逸脱しているのではないのか。
脱原発、再稼働や原発輸出で国民の怒りの金曜日の首相官邸や国会議事堂を包囲する大きなうねりに対しても冷ややかな報道姿勢を繰り返す。
NHKの予算や事業計画は毎年度、国会でチェックされ承認される。国会議員もそのシステムを盾にいろいろ要求してくる。安倍首相が任命した経営委員やその委員が選んだ籾井勝人会長の言動は常軌を逸したもので、辞任をするかと思いきや居直った。経営委員の長谷川三千子氏は「天皇は現入神」とまで言う。お騒がせな百田尚樹氏は「国に命を差し出すことを美化」と皇国史観丸出しだ。
4月13日、自局番組「とっておきサンデー」に出演した籾井会長は「会長の個人的な意見など入り込む余地はない。個人的な見解を放送に反映することは断じてない」と否定したが、カメラワークから見る表情には優越感が溢れ出ていた。誠実ある対応なのか疑った。
プロデューサー達の会長の顔色を見ながらの報道は、これで安倍政権に対して公平な報道ができるのかと疑義を深めただけだった。報道に携わる者は、私利私欲を捨て去り、社会に与える影響や責任の重さを最大限に自覚しなくてはならない。公共放送として国民(視聴者)からの信頼を得るためには「安倍さまのNHK」から、「皆様の受信料で成り立っているNHK」になるよう、意識面でも変革を見せてもらいたい。
5月から受信料も値上げになった。不払いの動きも一部にあると聞く。会長のスタンスの問題だけでなく、公共放送として襟を正さなければならないことも多々ある。放送は民主主義を育む道具である。私たちは放送内容を常に監視し、公共放送の公正・公平が民主主義の基盤であることを再認識したい。
もくじへ
葛西建治(本紙編集長・山口在住)
日本国憲法は3日、昭和22年の施行から67年を迎えた。
戦災の廃墟から生まれ、二度と戦争はしないと誓った「平和憲法」が、安倍首相の集団的自衛権の行使を認める解釈改憲で、憲法九条が存在しても「戦争ができる国」に変えようとしている。国のかたちを決める憲法がいま岐路に立たされている。
毎日新聞が憲法記念日前に行った全国世論調査は憲法九条の改正に反対するとの回答は51%と半数を超し、前年比14ポイント増となった。賛成の36%を15ポイント上回った。憲法解釈変更で集団的自衛権行使をしようとすることへの国民の不安が数字に表れている。
一方、大震災と原発事故の復興は遅々として進まない中、消費税増税、TPP促進、さらには原発や武器輸出と眼を覆うばかりの愚行が続く、改憲に執念を燃やす安倍首相は15日、集団的自衛権の行使を検討する考えを表明した。憲法記念日に大手各紙は紙面で憲法をどう伝えたのか。
解釈改憲は認められない(朝日、毎日、東京)
朝日新聞
憲法に最も多くのスペースを割いたのは朝日新聞だ。1面の特集記事で「改憲に執念首相の源流」と題して、改憲の旗を振る安倍晋三首相の論理や狙いを詳しく掘り下げた好記事を掲載した。
安倍氏は93年の初当選直後から憲法改正に向けた発進を繰り返してきた。94年に自民党基本問題調査会が「自主憲法制定」の党是見直しを検討したさいに、これに激しく挑んだのが安倍晋三氏だった。穏健派の大物に挑んだ安倍氏の言動に、保守系の学者は「筋のよい若手」と注目した。その後、安倍氏は憲法学者の八木秀次氏や政治学者の中西輝政氏らの改憲派の識者や団体に人脈を広げていった。
首相の周辺からは「災害など緊急時の対応も憲法で規定されていないので、国民の誰もが賛成するようなテーマがいい。9条改正は後回しでいい」との声もあるが、安倍氏は憲法改正が自らのルーツであるからこそ改正に執念を燃やすと説く。
2面にその突き進む理由を特集した。安倍氏の憲法観は「憲法は国家権力を縛るものだという考え方はある」としつつ「かつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方」と答弁したが、これは首相に近い憲法学者の西修・駒沢大学名誉教授が2年前の参院憲法審査会で参考人として述べた考え方と同じであった。
立憲主義は、憲法で権力を縛り、権力分立や基本的人権を保障するとの考え方で、憲法を貫く基本理念だが、日本の国の形を急ぐ安倍氏の答弁に憲法学者から大きな批判を受けた。
3面には長谷部恭男氏(早稲田大教授)と杉田敦氏(法政大教授)の大型対談を掲載した。長谷部氏は「推進派の議論は訳が分からない。日米安保条約は日本を守るための条約であり、この条約の枠組みから、どうして日本が集団的自衛権を行使すべきだという話が出てくるのか理解できない」と政府の解釈のあやふやさを指弾した。
杉田氏は「日本が集団的自衛権を行使できるようにし、日米安保体制を強化すべきだと。その発想自体が冷戦的な対立構造を再生産し、緊張を高める危険性があることを、あまりにも軽視している」と対立を煽る思考に警鐘を鳴らした。
15面のオピニオンで、作家の小林信彦氏が「列強国」入りを望む政権の危うさを、戦争中、小学生だった筆者の敗戦と、戦後、新憲法を素直に受け入れたことなど、読みごたえがあった。
大型社説では「いまの政権のやり方は『憲法を国民の手に取り戻す』のではなく、『憲法を国民から取り上げる』ことにほかならない」とクギをさした。
全頁にわたって護憲の姿勢を明確にし、朝日新聞らしい力量を感じさせる紙面構想であった。
毎日新聞
中面で見開きの「憲法記念日特集」を組んだ。地方議会で集団的自衛権行使に対する反対意見書が保守系会派も加わり、61市町村議会(4月30日現在)で採択され、件数が増える傾向を伝えた。
集団的自衛権の行使容認を目指す自民党は55年前の「砂川事件」の最高裁大法廷判決を理論的な支えにしようとしていることに、「(当時)集団的自衛権のことなど話題にも上がらなかった。自衛権と言えば個別だった」と判決文を起案した松本一郎・元獨協大副学長は明確に証言する。
砂川事件最高裁判決の解釈について、蒲田一郎・明治大学教授は「権力の拡張を目的に判決を読み直すのは立憲主義に反する。解釈改憲は事実上の改憲で、国民投票を経るのが筋だ。半世紀前の判決を無理に意義付けて解釈改憲をしようとする行為は『国民の意見は聞かない』と表明しているのも同然で、民主主義に背いている」と鋭く切り込む。
1面で毎日新聞の世論調査を掲載。9条改正反対は51%と半数を超し、すべての年代で賛成を上回り、前年比14ポイント増加した。内閣支持層でも「反対49%」が「賛成40%」を上回った。
社説では集団的自衛権は「改憲せず行使はできぬ」としたうえで、「集団的自衛権さえ行使できれば抑止力が高まり平和が維持されると解釈改憲に走るのは、憲法という国家の体系を軽んじた、政治の暴走」と指弾した。
社会面には「憲法九条、ノーベル平和賞候補に」も掲載。昨年に比べて一段と歯切れがよくなった。
東京新聞
東京新聞は自民党で戦争体験をした世代の加藤紘一、森田一、二階俊博、野田毅の4氏を登場させ、安倍政権の強硬路線に警鐘を鳴らした。
加藤氏は「集団的自衛権を本気で議論すると徴兵制までいってしまいかねない問題。『再び銃を持たない』これが守るべき日本の立場だ」と語る。
憲法について考える集会を地方自治体が後援を拒否する動きを3面で伝えた。千葉市の後援を拒否された市民団体は、担当者から「自民党の改憲案とか書かなかったら、通ったのに」と言われたという。講演のテーマに「自民党の改憲案で何が変わるか」の文言が問題になったという。市ではその後、論点の分かれているものや、その恐れのあるものは後援しないという基準を新たに設けた。
こうした動きに早稲田大学の水島朝穂教授は「集団的自衛権行使容認に強い意欲を示す安倍政権の意向を自治体側が過度に忖度し、迎合していることの表れ」と語った。東京新聞の取材で確認できた事例は全国で八件。事前の問い合わせで「門前払い」をしている事例を含めれば、水面下でさらに広がっている可能性もあると指摘する。これでは、集会に参加して自らの意見を表明する場を保障した憲法の理念が揺らぐと警鐘を鳴らした。
社説も歯切れがいい。解釈改憲を怪人二十面相にたとえ、安倍政権も変装が得意と指弾。憲法九条は専門家が研究しても、集団的自衛権行使など、とても考えられない。それを政権が強引に解釈を変えようとするのは変装と指摘。集団的自衛権行使を封じることこそ、九条の命脈である。政権はこの無理筋を閣議決定するつもりだ。事例を限定する「限定容認論」もまた変装である、と語る。最後に怪人二十面相の戦争批判を語らせ「まだ戦争をやろうとしているじゃないか、そんなことを考えているやつは、おれたちの万倍も、悪ものじゃないか」と結んだ。
昨年より憲法関連記事は薄くなったが、原発事故の報道姿勢に見られる、多面的な分析を重視する同紙に共感のエ−ルを贈りたい。
集団的自衛権で抑止力高めよ(読売、産経)
読売新聞
一面に小さく、憲法施行67年とあるだけで、日米TPP交渉で豚肉関税大幅下げの記事がトップだ。大型の社説は例年のごとく、改憲の応援団。集団的自衛権で抑止力を高めよと声高に解釈改憲を賞賛した。「集団的自衛権の解釈変更は、戦争に加担するのではなく、戦争を未然に防ぐ抑止力を高めることにこそ主眼」と安倍内閣を全面的に持ち上げ、集団的自衛権は憲法上、行使できないとする内閣法制局の従来の憲法解釈は国際的に通用しない、と煽る。憲法をないがしろにする巨大メディアの堕落を思い知る。
憲法記念日討論会なるものも企画したが、前原誠司氏(民主党)、船田元氏(自民党)など改憲派ばかりの座談会、「現行憲法が連合国軍総司令部に押しつけられたとの認識はない。それなりに国民になじんできた」と、語る22歳の学生以外は論議が希薄だ。この新聞には改憲に反対する読者はいないのだろうか。ジャーナリズムを放棄した紙面作りと言わざるを得ない。
産経新聞
これもひどい紙面だ。磯崎首相補佐官を登場させ、自衛権は国家の自然権だから、解釈変更は憲法を曲げることにならないと強弁。社説(主張)で集団的自衛権の容認が出発点であくまで九条改正を目指せと読売新聞と同じ論調だ。そのほかの憲法記事はない。「磯崎さん、あなたこそ憲法を守る立場ではないのですか」、と突っ込みたくなる紙面だ。
日経は昨年と論旨が同じ社説を掲載したが、ほかに憲法記事の掲載はなかった。
もくじへ
お染の七役、国太郎の至芸
鈴木太郎(詩人・演劇ライター 中新井在住)
前進座5月国立劇場公演は「お染の七役」(10日〜21日)。河原崎国太郎が七役を早替わりをふくめて演じきっている。国太郎の至芸に、客席からのどよめきや歓声、拍手が何度も起きていた。
四代目鶴屋南北の作「お染久松色読訓」(通称「お染の七役」)は、江戸時代初期におこった質店・油屋の娘と丁稚の心中を題材にした「お染久松」もののひとつ。前進座では渥美清太郎の改訂・演出で1938年に五代目国太郎(現在の国太郎の祖父)によって上演されたのが始まり。その後、歌舞伎の世界では、歌左衛門、玉三郎、福助など、花のある女形によって上演が繰り返されてきた。
当代の国太郎にとっては、16年前の襲名披露演目として初挑戦に続く2度目である。七役とは、油屋の一人娘・お染、店の丁稚・久松、奥女中・竹川(久松の姉)、芸者・小糸、土手のお六、油屋の後妻・貞昌、お光(久松の許嫁)。お染から久松、さらに竹川から芸者小糸へと扮装を変えて登場してくる。さらにはお六という悪婆の役までこなしていくのだ。
妙見さまの境内からはじまる物語は、久松の主家の宝刀・牛王義光を密かに探していることが主題となってくる。そこにからまる恋の行く末、悪党たちの企みなどがからむ。最期の隅田川の場面は浄瑠璃で、明るく締めている。中村梅之助、嵐圭史、藤川矢之輔たちの看板も顔を揃え、歌舞伎の醍醐味が十分に楽しめる。
もくじへ

もくじへ
山崎晶春(本会世話人・元小学館)
全滅を「玉砕」、侵略戦争を「聖戦」と呼び、特攻隊の若き兵士には爆弾や魚雷という兵器に代わって、人間が「肉弾」となって自爆する特攻戦術で、命を投げ棄てさせた。戦時下こうした驚愕と畏怖は国民にまで及ぼされ、天皇制のもとで日本軍部の思考は、兵士、一般庶民の「いのち」に対し、人間としての観念が通用しないものになっていた。
ほとんどの軍艦、戦闘機は戦闘能力を失っていても、いつも「わが方の損害は軽微なり」の報道で国民は騙された。女、子供達は戦意高揚につくし、家を守ること、隣組の動向に注意をむけることなども喚起された。日常の食糧も欠乏していった日々であった。
こうした戦時中に体験した日々の事柄を、戦争を知らない若い人たちに語り継ぎ、現憲法の理念、非核3原則の堅持、平和の大切さを伝える運動を「憲法九条の会」に結集する人々総がかりで強化する時ではないかと私は考えます。
一例として朝日新聞の「声」で特集した読者が語り継ぐ戦争体験の特集は運動に役立てることが出来ると思う。
私が現役時代の80年代に職場の「R(ルート)の会」(平和委員会の独自の組織)で、1975年ベトナム戦争でベトナムがアメリカに勝利。それを記念して「語り継ぐ戦争体験」の冊子を年一回発行し、97年まで続けてきました。この冊子を中心に運動の実態をつくり、若い活動家が育っていった。
★敗戦(1945年8月15日)から3・11(東北津波、地震、福島原発)までの総括の視点を明確にすえる。
・市民一人ひとりがなぜ脱原発に結集しなければならないのか、その話し合う場を無数に作り、真の民主主義運動を草の根から押し上げる。
・占領下時代はGHQから下りてきた民主主義運動であった。天皇の戦争責任問題、戦争犯罪人の追及などできなかった。
・小関彰一氏の「憲法九条はなぜ制定されたか」(岩波ブックレットNo674)での問題提起を考えてみる
私は再読する基本的な書籍を以下のように選びました。
色川大吉氏「近代国家の出発」「ある昭和史」「自由民権」など。
井上幸治氏「秩父事件」。「昭和の歴史」(全10巻別1 小学館)など。
「『世界』主要論文選 1946?1995 戦後50年の現実と日本の選択」。この中に敗戦直後の丸山真男、久野 収などの論文も掲載されていますが、特に、大内兵衛の「新憲法と学問」は一読の価値があります。 (図書館に保存されています)
前坂俊之氏「太平洋戦争と新聞」(講談社学術文庫)
門奈直樹氏「民衆ジャーナリズムの歴史」自由民権から占領下沖縄まで(講談社学術文庫)
更に
・ジョン・ダワー「敗北を抱きしめて」(上・下)。
ジョン・ダワー(著)日、米、世界を見直す「忘却のしかた、記憶のしかた」日本、アメリカ、戦争(訳 外岡秀俊 岩波書店)
・また、朝日新聞2月11日の添谷芳秀氏(慶大教授)「靖国参拝と世界秩序」へのインタビューで「・・・東京裁判に問題がないわけではない。しかし東京裁判を受け入れない議論の最大の問題は、戦争に敗れた側が勝者に対して持つ怨恨の情(ルサンチマン)や被害者意識が強いあまり、ではその代替は何だったのかという発想が不在な点です。戦後日本の民主主義が、日本を無謀な戦争に駆り立てた国の指導者を自ら裁こうとしなかったのは、日本人が深く内省すべきことです。・・・九条を核心とする戦後憲法は、日本の非武装化を進める論理から生まれました。その後冷戦が深刻化し、米国は日本に再軍備を求めましたが、吉田首相は九条を維持したまま日米安保条約を締結する道を選び、サンフランシスコ講和条約の際、調印した。この吉田路線こそが『戦後レジーム』であり、土台にあるのは侵略戦争への反省です」と指摘しています。
安倍首相がとっている態度はまさにサンフランシスコ講和体制への挑戦であり、中国のプロパガンダに利用されている、歴史認識のない無謀な「積極的平和主義」の本質なのです。こうした問題指摘からも討論を深めることが大切ではないでしょうか。
また、日本人は先の戦争に対して、強い被害者意識を持つが、なぜ加害者としての意識が薄いのでしょうか。その要因を掘り下げるためにも、以下の書籍を参照してみたらいかがでしょうか。
吉岡吉典著「韓国併合」100年と日本(新日本出版社)
梅田正己著「近代日本の戦争」台湾出兵から太平洋戦争まで(高文研)
色川大吉著「近代日本の戦争」20世紀の歴史を知るために(岩波ジュニア新書)
山田 朗著「歴史修正主義の克服」ゆがめられた〈戦争論〉を問う(高文研)
吉田 裕(監修)ハーバート・ビックス「昭和天皇」上・下(講談社)など。
(C) 憲政史上初の両院強行採決を許さない安倍政権の退陣と国民の信を問い直す総選挙を求める
なぜ都知事選挙が安倍政権打倒を目指す闘いにならなかったのか?
昨年12月7日に「マスコミ九条の会」日本ジャーナリスト会議(JCJ)でこの声明を出し、この記者会見を1月14日(火)プレスセンターで行われた。
「呼びかけ人」62名。(前述しているので重複しますが、今回のこの記者会見は重要な位置づけですので、再度記します)
早い段階からすでに「特定秘密保護法」反対、共同行動及び賛同者58団体、個人258人の人たちから意見は寄せられていた。
「細川候補の政策発表が遅れ、候補者たちの政策討論がないまま推移した。ようやくそれぞれの候補の主張が明らかになってきたが、候補者たちの論議は行われなかった。都知事選を直前に、『脱原発』に関する政策と主張が共通する宇都宮候補と細川候補が共同して、安倍政権を打倒する選挙戦を行うべきであるという文化人、有権者からの訴えが急速に高まっていた」。それに応えるべく、マスコミに足場を置いてきた私たちと脱原発1,000万人運動を進めている団体と共同して,両候補が話し合う場を2月3日(月)と6日(木)に設定した。宇都宮候補、細川候補ともに欠席、両選対の見解は届けられたが、その発表で終わった。この事態をなぜ切り拓けなかったのか。
運動を進める側である私たちの情勢に対する考え方、歴史から学び取る視座、経験主義、政党からの呪縛からの解放など、もっと率直に語り合えないのだろうか。
一致した要求を共同で掲げ、安倍政権打倒をめざし、市民主体の自覚した運動として発展させなければ、憲法を守り、歴史認識を深める運動にならない。
「憲法の基本理念を掲げ、非核三原則を堅持」し、市民の自立した「真の民主主義運動」を基本にすえた闘いなのです。
安倍首相のいう「積極的平和主義」はアメリカに従属し、戦争が出来る国にすることであり、このことは自民党の憲法改悪案をみれば一目瞭然です。
(イ)「いのち」を守り、自然環境を保全する位置づけが基本。
(ロ)「原発」と放射能の「核」は表裏の関係であり、「原発」推進を進めようとする安倍政権(自・公)をはじめとする議員、財界、東電、大手のマスコミなどの動向を見逃してはならない。
(ハ)子供たちの未来社会を創るのは大人の責務である。
(ニ)原発被害未解決のまま、原発「安全神話」を復活させようとしている。「神話」を作り上げた財界の動きと、それを支える団体、専門家、マスコミ人の責任追及をより徹底する。
(ホ)有権者の一票の責任、憲法理念を深める運動の強化が必要である。
靖国を参拝した議員の歴史認識を問う闘いを居住する自治体で起こし、そうした議員を次の選挙に当選させないことが安倍政権打倒への具体的な運動ではないでしょうか。
もくじへ
長い間待っていた米軍通信基地を貫通する東西連絡道路が開通に向けて予算化されました。
所沢平和委員会は、昭和51年から道路用地の返還を市民と一緒に要望していました。測量は終了し、国との協議の結果、倉庫や防火水槽、施設出入口、道路境界柵などは市の負担になります。
幅員は16m、延長約580m、面積は約9400㎡となり、今回計上された4300万円は東西連絡道路・基地運営用道路の設計予算になります。開通は18年度の予定です。
市民の粘り強い要求が一歩前進しました。次の課題は道路開通で分断され、使用停止になるといわれている南側の基地の返還を求めて運動することが課題になります。
もくじへ
戦争する国ゴメンです 九条の会東京のつどい
・6月4日(火曜日)午後6時30分〜
・なかのゼロ・大ホール
・講師=孫崎享さん 青井美帆さん 小森陽一さん
・コント=松本ヒロさん
・参加費999円
九条の会「1O周年記念講演会」
・6月10日(火曜日)午後6時〜
・渋谷公会堂
・メーン講演者 阪田雅裕元内閣法制局長官
もくじへ
トップページへ